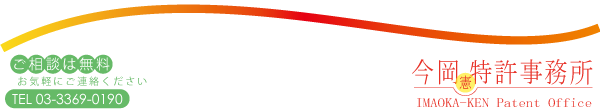
|
●昭44(行ケ)84号
事実に反する命題の評価/進歩性を否定する根拠となる命題の範囲/進歩性
| [事件の概要] |
| ①原告は、「接着用銅材料の表面処理法」という発明について特許出願し、進歩性の欠如により拒絶査定を受け、拒絶査定不服審判を請求しました。同審判で出願公告されましたが(特公昭40-15327)、特許異議申立の結果請求は成り立たない旨の審決を出され、審決取消訴訟に至りました。 ②本件発明の構成は次通りです(訴訟の提起時点)。 「銅材料の表面に銅のヤケ鍍金を施した後、該面に接着剤を使用し、または使用せずして合成樹脂含浸紙または布からなる積層板を密着せしめることを特徴とする銅貼積層板の製造法」 ③本発明の目的は、次の通りです。 “電着銅の粗表面に直接絶縁材料を接着して銅貼積層板を製造する方法が本願出願前当業者間に周知であつたが当該方法による場合は銅材料と絶縁材料との間の剥離抗力が極めて劣弱であつたことから、本願発明は周知方法の欠陥を改善することを目的とする。” ③本発明の特徴及び作用は次の通りです。 “銅材料と絶縁材料である合成樹脂含浸紙または布からなる積層板との接着力を強化させるために、予め銅材料の表面に、出願前周知の電気鍍金の方法を用い、限界電流密度を越える電流を流して銅材料と一体をなすヤケ鍍金層を形成させたうえ、銅材料を直接絶縁材料と接着させることを主要な構成要件とするものである。” ④主引用例は「電着銅の銅粗表面に合成樹脂含浸紙からなる積層板を密着して銅被覆積層板を製造する」もので、次のことが開示しています。 ア.引用発明も前記周知方法の欠陥の改善を目的としていること。 イ.銅材料と絶縁材料との接着力を強化させるために、予じめ銅材料の表面に、酸化剤を加えたアルカリの水溶液にこれを浸漬するなど周知の方法によって、銅酸化物層を形成させたうえ、銅材料をこれとは別の物体である銅酸化物層を介して絶縁材料と接着させることを主要な構成要件とすること。 ウ.銅材料の粗表面自体を使用することはないこと。 ⑤審決は、進歩性を否定する理由として、本願発明は同引用例に示された銅粗表面(銅粗表面自体および銅粗表面に銅酸化物層を形成させたものの両者を指す)として、単にヤケ鍍金を施した銅電着粗面を用いた構成のものである旨を説示しています。 ⑥また被告(特許庁)は、第一引用例には表面粗度を大きくすれば接着力が大きくなる旨の記載があるから、本願発明は同用例の記載から容易に推考できた旨を主張しました。 |
| [裁判所の判断] |
| ①裁判所は、審決の説示に関連して次のように事実認定しています。 ア.証拠によれば、表面の粗度、すなわち真の表面積の幾何学的表面積に対する比率を大きくすれば接着力が大きくなるという命題は、本願出願前俗説としては存在したが、学説または理論としてこれを主張するものは皆無である。 イ.当時の学説ないし理論によれば、表面粗度を大きくした場合には、清浄な面または反応性に富む面を作るなどの長所があると同時に、空隙が残りその部分に応力が集中しそこから破壊がはじまるなどの短所があること、表面粗度のほかに表面粗化の方法、例えば機械的方法によるか化学的方法によるかによって接着力が異なることが指摘され、表面粗度と接着力との関係は複雑で一義的に説明することはできないとされていた。 ウ.以上の事実が本願出願前における当業者の技術常識であつた。  ②さらに裁判所は上記事実認定に基づいて次のように判断しています。 ア.上記命題が真実に反しており、かつそのことが本願出願前当業者間に周知であつたとすれば、被告の主張を採用することができない。 ロ.そうだとすると、第一引用例の発明においては銅材料の表面に酸化物層を形成させるものであるのに対し、本願発明においては銅材料の表面に銅のヤケ鍍金を施すものであること前認定のとおりであるから、両者は銅表面の粗化の方法を異にし、かつ、銅材料と絶縁材料との間に銅酸化物層が介在するかどうかの構造にも差異があるというべきである。 ロ.よって上記事項を本願発明の進歩性を否定する論理に用いるのは相当でない。 ハ.本願出願前ヤケ鍍金の現象は産業上価値ない不良現象として当業者に認識されていた。 ニ.発明者は、ヤケ鍍金の現象が本願発明の目的である銅材料と絶縁材料の接着力の強化のため有益な作用効果を有すること、すなわち、ヤケ鍍金の現象を本願発明の目的を達成するのに適した態様において利用するならば、前認定の周知方法による場合と比較して剥離抗力が約3.4倍ないし八倍増大することを発見し、この知見に基づいて本願発明を完成したことが認められるから、ヤケ鍍金の前記作用効果の発見が当業者にとつて容易な場合でなければ、ヤケ鍍金の現象自体が周知であっても、本願発明が容易に推考できたものと認めることはできず、進歩性を否定することはできない。 |
| [コメント] |
| 特許法第29条第2項(進歩性)の規定には、特許出願の前に新規性を喪失した発明に基づいて当業者が容易に発明できたときには、特許を受けることができない旨が規定されていますが、講学上は、ここでの“新規性を喪失した発明”は公知の事実に読み替えるべきであり、発明ではない科学上の発見なども含まれると解釈されています。そこから一歩進めて事実に反する引用文献の記載は進歩性を否定することができるかということが問題となりますが、進歩性否定の根拠とすべきではないというのが判例の立場です。 |
| [特記事項] |
| 戻る |
今岡憲特許事務所 : 〒164-0003 東京都中野区東中野3-1-4 タカトウビル 2F
TEL:03-3369-0190 FAX:03-3369-0191
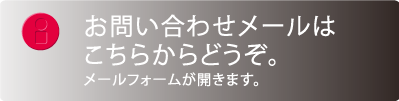
営業時間:平日9:00~17:20
今岡憲特許事務所TOPページ | はじめに | 特許について | 判例紹介 | 事務所概要 | 減免制度 | リンク | 無料相談
Copyright (c) 2014 今岡特許事務所 All Rights Reserved.

