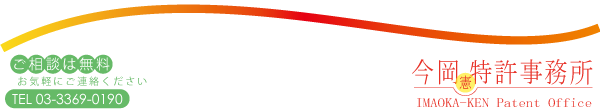
|
●昭和53年(行ツ)第69号「一眼レフ・カメラ」事件
新規性進歩性審査基準/特許出願の要件/刊行物/カメラ
| [事件の概要] |
|
①甲(原告)は、発明の名称を「一眼レフ・カメラ」とする特許第615517号の特許権者であり、無効審判により外国特許庁が提供した実用新案の出願書類の複製物を刊行物として特許が無効とされ、審決取消訴訟が提起しました。そして審決を維持する判決が出されたため、上訴して本件訴訟に至りました。 ②甲の上告理由の要点は次の通りです。 (イ)頒布された刊行物という場合の「刊行物」とは、公開的の出版物を指し、出版とは発売し又は頒布するために文書図画を印刷することをいい(出版法第一条)、手で書いたもの或は炭酸紙、その他機械等で複写したものは、ここにいう刊行物と解すべきでない。 (ロ)また公開的のものであるから印刷物の内容を秘密にしているもの或は、私文書を多数の友人に配布するために印刷又は複写した物はここにいう刊行物というべきではない。 (ハ)更に「頒布」とは上記のような刊行物が不特定多数の者が見得る状態におかれることをいうものと解すべきであり、いうまでもなく、複写物は不特定多数人に頒布するために出版されたものではないから刊行物とはいえない。複写物は公知(二九条一項一号)即ち不特定多数人の知り得る状態とはなし難いからである。 (ニ)同出願明細書自体又はその複写物が「刊行物」の一般定義語にあたらないことが明白であるにかかわらず現行特許法制度にあたって特許法にいう「刊行物」について何ら特段の規定(みなし規定等)が定められなかつた事実を考えれば特許法の刊行物は一般の辞典にも明示されている語義と同一に解すべきであり前記逐条解説をなした法案作成者もその意図であつたことが明白である。 (ホ)従ってこれらの点から考察しても出願明細書それ自体又は希望者にのみ複写して渡される同出願明細書の複写物等を特許法の「刊行物」と解することはできない。 |
| [裁判所の判断] |
|
①裁判所は、特許法第29条第1項第3号の「刊行物」に関して次のように判断しました。 刊行物とは、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図画その他これに類する情報伝達媒体であって、頒布されたものを指すところ、ここに公衆に対し頒布により公開することを目的として複製されたものであるということができるものは、必ずしも公衆の閲覧を期待してあらかじめ公衆の要求を満たすことができるとみられる相当程度の部数が原本から複製されて広く公衆に提供されているようなものに限られるとしなければならないものではなく、右原本自体が公開されて公衆の自由な閲覧に供され、かつ、その複写物が公衆からの要求に即応して遅滞なく交付される態勢が整っているならば、公衆からの要求をまってその都度原本から複写して交付されるものであっても差し支えないと解するのが相当である。 ②裁判所は、第1引用例の刊行物該当性について次のように判断しました。 (イ)第一引用例は、西独国実用新案登録第一八五九四九〇号明細書(以下「本件明細書」という。)の複写物である。 (ロ)本件特許出願前同国特許庁又は右ドイツ特許サービス社の配布したものであると推認することができるものであるところ、本件明細書は、本件特許出願前の前同年一〇月四日に登録された前記実用新案の出願書類として同日以降同国特許庁において公衆の閲覧に供されていたものである。 (ハ)しかも、本件明細書のような登録実用新案の出願書類原本の複写物を望む者は、誰でも同国特許庁から又は私的サービス会社、例えば、前記ドイツ特許サービス社を介して通例注文書発信後約二週間で入手することができるものであった。 (ニ)そうすると、本件複写物ないし第一引用例は、公衆に対し頒布により公開することを目的として本件明細書から複製された文書であって、本件特許出願前に頒布されていたものであるということができるから、特許法第29条第1項第3号に掲げる頒布された刊行物に該当するものであると認めて差し支えないものである。 |
| [コメント] |
|
①新規性・進歩性審査基準には、「『刊行物』とは、公衆に対し公開することを目的とした文書、図面その他これに類する情報伝達媒体をいう。『頒布』とは、上記のような刊行物が不特定の物が見得るような状態におかれることをいう。現実にその刊行物を見たという事実を必要としない。」と記載されています。本件は、こうした基準の基礎となった判決の一つであります。 ②特許法第29条第1項第1号の“公知発明”及び第2号の“公用発明”とは別に第3号の“文献公知発明”が規定された理由は、特許出願の審査のたびに公知・公用となった時点を調べて、認定しなければならないとすれば、特許調査の負担が過大となるということであると考えます。 ③そうであるならば、外国の特許制度で、特許公報に相当するものを“公衆の注文に応じて直ちに交付する”という運用をしているのであれば、“直ちに交付”する状態を以て文献公知の状態になったと考えるのが、現実的であると考えられます。仮に交付された複製物が現実に注文者に配達された時点を以て刊行物になったとすると、特許公報の日付を新規性・進歩性の判断することができなくなるからです。 |
| [特記事項] |
| 新規性進歩性審査基準に関連する事例 |
| 戻る |
今岡憲特許事務所 : 〒164-0003 東京都中野区東中野3-1-4 タカトウビル 2F
TEL:03-3369-0190 FAX:03-3369-0191
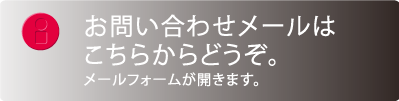
営業時間:平日9:00~17:20
今岡憲特許事務所TOPページ | はじめに | 特許について | 判例紹介 | 事務所概要 | 減免制度 | リンク | 無料相談
Copyright (c) 2014 今岡特許事務所 All Rights Reserved.

