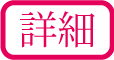
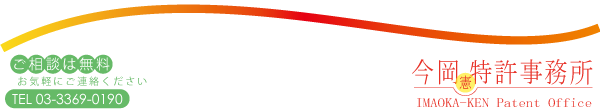
|
���W�ɂ͗ގ�����ߎ����Ƃ����T�O������܂��B�������ŋ߂̎���܂��Ĕ���Ղ�������܂��B
�������P�O�N�i�s�P�j��R�P�W��
�����P�O�N�i�s�P�j��R�P�W���^���W�̗ގ��^�������W�^�n���^�ɕ{���~
| �m�ٔ��N�����n |
| ����11�N 5��27�� |
| �m�������n |
| �R������������� |
| �m�啶�n |
| �����̐��������p����B �i�ה�p�͌����̕��S�Ƃ���B |
| �m�����n |
| ��P�@���� �@�@�������������W�N�R����Q�O�P�O�T�������ɂ��ĕ����P�O�N�W���P�S���ɂ����R�����������B ��Q�@�����ҊԂɑ����̂Ȃ����� �@�P�@�������ɂ�����葱�̌o�� �@�@�퍐�́A�w�菤�i�����W�@�{�s�߁i�����R�N���ߑ�Q�X�X���ɂ������O�̂��́j�ɒ�߂鏤�i�敪��Q�W�ށu��ށi��p���������j�v�Ƃ��A�ʎ��Q�̂Ƃ���A�u�ɕ{���~�v�̕����������ĂȂ�o�^��Q�R�U�S�W�U�S�����W�i���a�U�R�N�P�Q���V���o�^�o��A�����R�N�P�Q���Q�T���ݒ�o�^�B�ȉ��u�{�����W�v�Ƃ����B�j�̏��W���҂ł���B �@�@�����́A�����W�N�P�P���Q�W���A���W�@�S���P���W���A�P�P���y�тP�T���Ɉᔽ���邱�Ƃ𗝗R�Ƃ��āA�{�����W�̓o�^���Ƃ��邱�Ƃɂ��R���𐿋������B �@�@�������́A�������N�R����Q�O�P�O�T�������Ƃ��ĐR���������ʁA�����P�O�N�W���P�S���A�{���R���̐����͐��藧���Ȃ��|�̐R�������A���̓��{�́A���N�X���V�������ɑ��B���ꂽ�B �@�Q�@�R���̗��R �@�@�R���̗��R�́A�ʎ��P�R�����̗��R�ʂ��i�ȉ��u�R�����v�Ƃ����B�j�ɋL�ڂ̂Ƃ���ł���A�R���́A�{�����W�́A���W�@�S���P���W���A�P�P���y�тP�T���Ɉᔽ���ēo�^���ꂽ���̂Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ�����A���̓o�^���Ƃ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ɣ��f�����B ��R�@�R���̎�����R �@�P�@�R���̔F�� �@�@(1)�@�{�����W�� �@�@�{�����W�i�R�����Q�łR�s�Ȃ����U�s�j�A�����l�i�{�i�����j�̈��p�e���W�i���Q�łW�s�Ȃ����Q�R�s�j�A�����l�̎咣�i���Q�Ŗ��s�Ȃ����P�T�łQ�O�s�j�y�є퐿���l�i�{�i�퍐�j�̎咣�i���P�T�łQ�Q�s�Ȃ����Q�R�łS�s�j�͔F�߂�B �@�@(2)�@���W�@�S���P���P�P���ɂ��Ă̔��f �@�@�q�P�r�@�R�����Q�R�łV�s�Ȃ����X�s�u������Ă�����̂ł���A�v�܂ł̂����A�u�܂Ƃ܂�悭�v�̓_�͑����A���̗]�͔F�߂�B���Q�R�łX�s�u������v����P�P�s�܂ł͑����B���Q�R�łP�Q�s�A�P�R�s�͔F�߂�B���P�S�s�Ȃ����Q�P�s�͑����B �@�@�q�Q�r�@���p�e���W���琶����̌ē��̔F��i�R�����Q�R�łQ�Q�s�Ȃ����Q�S�łS�s�j�͔F�߂�B �@�@�q�R�r�@�̌Ăɂ��Ă̔��f�i�R�����Q�S�łT�s�Ȃ����X�s�j�y�ъϔO�ɂ��Ă̔��f�i���Q�S�łP�O�s�Ȃ����P�Q�s�j�͑����A�O�ςɂ��Ă̔��f�i���Q�S�łP�R�s�A�P�S�s�j�͔F�߂�B�܂Ƃ߁i���Q�S�łP�T�s�A�P�U�s�j�͑����B �@�@�q�S�r�@�����l�i�����j�̎咣�ɑ��锻�f�i�R�����Q�S�łP�X�s�Ȃ����Q�U�łQ�s�j�̂����A�u�w�ɕ{�x�̌�́A�w���ɕ{�x�̗��̂����Ӗ������ł���A�܂��A���ɕ{�V���{�ߕӂ̍s����於�̂ł���v���Ɓi�R�����Q�S�Ŗ��s�Ȃ����Q�T�s�Q�s�j�A�y�сu�s����於�̂Ƃ��Ắw�ɕ{�x�����ɕ{�s�̈ꕔ�̒n��ł���A���̒n����̑��ɕ{�V���{�̖��̂��������^�����Ղ�_�ЂƂ��āA���邢�͔~�̖����Ƃ��āA��ʐ��l�ɍL���m���Ă���Ƃ��Ă��A�R������V���Ȃ�������X���ɂ��A�w���ɕ{�s�̑��ɕ{�V���{�x�̂悤�ɋL�ڂ���Ă��邱�Ƃ��F�߂��A�v�i�R�����Q�T�łS�s�Ȃ����W�s�j�͔F�߁A���̗]�͑����B �@�@(3)�@���W�@�S���P���W���y�тP�T���ɂ��Ă̔��f �@�@�R�����Q�U�łS�s�Ȃ����P�V�s�͔F�߁A���̗]�͑����B �@�@(4)�@�܂Ƃ� �@�@�R�����Q�V�łP�R�s�Ȃ����P�U�s�͑����B �@�Q�@������R �@�@�R���́A�{�����W�̏��W�@�S���P���W���A�P�P���y�тP�T���Y�����ɂ��Ă̔��f����������̂ł��邩��A��@�Ȃ��̂Ƃ��Ď��������ׂ��ł���B �@�@(1)�@������R�P�i���W�@�S���P���P�P���j �@�@�R���́A�{�����W�͏��W�@�S���P���P�P���Ɉᔽ���ēo�^���ꂽ���̂Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��|���f���邪�A���ł���B �@�@�q�P�r(a)�@�u�Y�n�E�̔��n�{���錾�t�����v�́A�u�Y�n�E�̔��n�v�̕����Ɏ������i�̎��ʐ����Ȃ����߂ɁA�u�����v�̕������v���ƂȂ�A�u�����v�̕����Ɏ������i���ʐ�������ꍇ�ɂ́A�o�^����L����B �@�@(b)�@�퍐�́A��ނ̓��ꐫ���咣���邪�A�퍐�̎咣�����藧���߂ɂ́A �@�@�@�@�n���������K���Y�n�\���ł��邱�ƁA �@�@�A�@���ꂪ�^���̎Y�n��\�����Ă��邱�ƁA �@�@�B�@�e�Y�n�ɂ��A�Y�n���ɖ��⍁��̓�������肵�Ă��邱�ƁA �@�@�C�@����ҁA���v�҂����⍁������W�̎Y�n�\�������Ŕ��f���Ă��邱�� �@�@���K�v�ł���Ƃ���A�����͂����������Ƃ͍��v���Ă��炸�A�����ɔ����Ă���B �@�@���Ȃ킿�A�Ⴆ�A�����̑����̏��������������É��̔̔���Ђɔ̔����ꂽ��A���Y�̔���Ђ��u�����́����v�Ƃ̖����Ŕ̔����Ă����W�@�㉽����͂Ȃ��B���W���̒n���͕K���Y�n�\���łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ̐����͂Ȃ�����ł���B���W���̒n���͎Y�n�\���łȂ���Ȃ�Ȃ��Ɖ��肵�Ă��A�k�C�����݂̑������u�偛���v�Ƃ̓o�^���W��L���Ă����肷��悤�ɁA���W�@��^���̎Y�n�\���łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ̗v���͑S���Ȃ��B�܂��A�u�z�v�A�u�o�H�v�A�u����v�̂悤�Ȓn���ɊY������̈�͂��Ȃ�L���n��ł���A���Y�n����̗Ⴆ�Ζk���Ɠ암�Ƃł́u�d���݂̐��v�A�u�𑠂̗��n�����v�A�u���R���v�A�u���ӂ̕��y�v���قȂ��Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł��邩��A����̒n�������������{���ł����Ă��A���⍁��ɂ����ē���̓���������Ƃ͓��ꂢ���Ȃ��B����ɁA����ҁA���v�҂́A���⍁������W�̒n�������Ŕ��f���Ă���̂ł͂Ȃ��A���{�����������{��e��̃��x���ɋL�ڂ��ꂽ���̉�����Ŋm�F���čw�����Ă�����̂ł���B �@�@(c)�@�퍐�̐��i�u�}��̊��~�v�ɂ��āA����҂ɔ̔�����������X����A�u�}��v���̏ۂ��čL���̔����Ă��鎖���i�b��Q�W�A��Q�X���j���炵�Ă��A����ҁA���v�҂͒n�������ɂ����ڂ��Ă��Ȃ����̂ł���B �@�@(d)�@�퍐�́A�u�S�������ꗗ�\�v�i����Q���j�Ɋ�Â��A�����̏��W�Ƃ��āu�n���{�_�v���̂��̂������g�p����Ă���|�咣����B �@�@�������Ȃ���A�u�S�������ꗗ�\�v�i����Q���j�́A������g�p����Ă�������̖��̂�P�ɗ�L���������̂��ł���A���̒��ɂ́A���W�o�^����Ă��炸�A���Ȃ��Ƃ��`���I�ɂ͑��l�̓o�^���W�̐N�Q�ɓ�������̂�A�R���~�X���̗��R�ɂ��d���o�^����Ă�����̂����݂��Ă���̂ł����āA���̂悤�Ȏ�������A���W���̒n��A�n��̕\���͑��̋L�ڂƈ�̂ƂȂ��ď��i�����ʂ����ŏd�v�Ȕ�d���߂Ă���Ȃǂƌ��_���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����̂ł���B �@�@�q�Q�r(a)�@�{�����W���́u�ɕ{�v�́A���ɕ{�̗��̂ł���A���ɕ{�V���{�̏��ݒn�⋌�Ղ̑��ɕ{�Ձi�u��ɕ{�v�Ƃ̕\�L�����蓾�邪�A�ȉ��A�u���ɕ{�v�Ƃ̕\�L�œ��ꂷ��B�j�A���Ȃ킿���݂̕��������ɕ{�s��т��w�����̂ł���B������I�ɂ́A���ɕ{�V���{�̏��ݒn���ӂł��镟�������ɕ{�s�ɕ{�Ƃ������̂̍s�����������Ă���B���Ȃ킿�A�u�ɕ{�v�́A��ʂ̍��ꎫ�T�ɂ��u�w���ɕ{�x�̗��v�ł���|�L�ڂ���Ă���i�b��U�A��V���j�A�܂��A���������ɕ{�s�̑��ɕ{�V���{�̎��ӂ̒n��́A�����ɑ��ɕ{�s�ɕ{�Ƃ������̂̍s�����ł���i�b��W���j�B �@�@(b)�@�����āA���������ɕ{�s�ɕ{�ɂ����Ă��A���̏����X�͑��݂��Ă���i�b��P�P���j�A�܂��A���ɕ{�V���{�⋌�Ղ̑��ɕ{�͊ό��n�Ƃ��ėL���ł���A���{�S���e�n�̊ό��n�̓y�Y���X�ł͓��Y�n���̒n����̔����Ă���Ⴊ�ɂ߂đ������Ƃ͌o�����㖾�炩�ł��邩��A����ҁA���v�҂́A�{�����W�̑O�����ł���u�ɕ{�v���Y�n�A�̔��n�A���Ȃ��Ƃ��̔��n�Ƃ��ĔF��������̂ł���B �@�@�q�R�r�@���������āA�{�����W���́u�ɕ{�v�́A�P�ɖ{�����W�̎w�菤�i�ɂ��ĎY�n��̔��n��\������ɂ������A�������i�̎��ʐ��������Ȃ������ł���B �@�@��������ƁA�{�����W�u�ɕ{���~�v�ɐڂ������ҁA���v�҂́A�Y�n�A�̔��n�̊ϔO�u�ɕ{�v�n���Ƒ��܂��āA�u�ɕ{�v�����̂��āA�e���݂₷��������ۂÂ�����u���~�v�̕�����E�o����Ƃ�����̑I���ɂ��A�u���~�v�̏̌āA�ϔO�������Ď���Ɏ����邱�Ƃ͖��炩�ł���A�{�����W�ƈ��p���W�Ƃ́A�̌ċy�ъϔO�ɂ����đ�����킵���A�ގ����鏤�W�ł���B �@�@(2)�@������R�Q�i���W�@�S���P���W���j �@�@�R���́A�{�����W�͏��W�@�S���P���W���Ɉᔽ���ēo�^���ꂽ���̂Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��|���f���邪�A���ł���B �@�@�q�P�r�@�����u���~������Ёv�̗��̂́A�u���~�v�ł���B �@�@�q�Q�r�@���~�́A�����̒����ȗ��̂ł���B �@�@����Ȃ��A�����̑O�g�ł����؉Ƃ́A�����S�N�i����P�W�Q�P�N�j�A�u���~�v�̏��W��p���Đ����̏����A�̔����J�n���A���̌�A�l�c�Ƃ��獇����Ђɑg�D�ύX���A���a�Q�X�N�ɍ�����Ћ��R��؏��X���犦�~������ЂւƖ��̂�ύX���A���a�R�T�N�ɉ�Бg�D�̕ύX�ɔ����Ċ��~������ЂƂȂ����B �@�@�����́A���a�Q�X�N�ȗ��A��т��āu���~����v�̗��̂Őe���܂�Ă���A�����u���~�v�ƌ����Ό����u���~�v���A�����u���~�v�ƌ����ΐ����u���~�v���F�������悤�ɂȂ��Ă���B �@�@�܂��A�����y�т��̐��i�ł��鐴���u���~�v�́A�ߋ����猻�݂܂ŁA�e��̓��{���̎��T�⃀�b�N�{�̓��{���̎G�����ɍL���Љ��Ă��Ă���i�b��P�T�Ȃ�����Q�T���j�B �@�@����ɁA�����́A���{���̊ӕ]��Ȃǂɂ����āA��������܂��Ă���B�����Ƃ��Č������Ă���ł��Â����̂Ƃ��ď��a�R�P�N�x�̑S������i�]��̗D������i�b��Q�U���j�A�ŋ߂̂��̂Ƃ��ẮA�����W�N�x�̑S���V���ӕ]������邪�i�b��Q�V���j�A���̑��ɂ��A�u�֓��M�z�ǂ̊ӕ]��Ɏl����܁A�m���g���̎�����i�]��ł͗D���܂����т��ю��B�v�i�b��P�V���j�A�u���~�u�����h�͕������N�Ɋ֓��M�z���ŋǎ�ފӕ]��łR���A���̋���܁B���a�U�R�N�x�ɂ͏t�i���Ď�j�E�H�i�����j�ŘA����܂��ʂ����Ă���B�v�i�b��Q�P���j�A�u�����T�N�ӕ]���ܑ����v�i�b��Q�S���j�Ȃǐ��X�̏܂��Ă���B �@�@�ȏ�̂Ƃ���A�����̗��́u���~�v�������ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B �@�@(3)�@������R�R�i���W�@�S���P���P�T���j �@�@�R���́A�{�����W�͏��W�@�S���P���P�T���Ɉᔽ���ēo�^���ꂽ���̂Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��|���f���邪�A���ł���B �@�@�q�P�r�@�O�L(2)�q�Q�r�ɋL�ڂ̂悤�ɁA�����́A�����S�N�i����P�W�Q�P�N�j����p�����ĂP�W�O�N�߂��ɂ킽��A�����u���~�v�������A�̔����Ă���A���W�̓o�^�́A�����Q�S�N�R���P�U���ɂ���Ă���A�ȗ��A���W�u���~�v��t���������u���~�v�������A�̔����Ă����B �@�@�q�Q�r�@�퍐���{�����W��t���������u�ɕ{���~�v��̔�����ƁA����ҁA���v�҂ɂ����Ă��̏��i�̏o���ɂ��č������A���l���錴���̋Ɩ��ɌW�鏤�i�ł��鐴���u���~�v�ƍ������邨���ꂪ���邱�Ƃ͕K���ł���B ��S�@�R���̎�����R�ɑ��锽�_ �@�P�@�F�� �@�@�R���̔F��A���f�͐����ł���A�����咣�̌��͂Ȃ��B �@�Q�@���_ �@�@(1)�@������R�P�i���W�@�S���P���P�P���j�ɂ��� �@�@�q�P�r�@�u�ɕ{���~�v�ƊO�Ϗ�܂Ƃ܂�悭��̓I�ɍ\������Ă�����̂̏̌Ă��A�u�ɕ{�v�Ɓu���~�v�Ƃɂ��Ƃ��番�����āA�u���~�v�݂̂̏̌āA�ϔO�������Ď������Ȃ���Ȃ�Ȃ��i�ʂ̗��R�͌�������Ȃ��B �@�@�q�Q�r�@�u�ɕ{�v�ɂ́A�ɑ��̖����Ƃ����Ӗ�������A����������ʂɍL���m��ꂽ�n���I���̂ł���Ƃ������Ǝ��̂��^��ł���B �@�@�L���Ȋό��n�Ƃ��ĔF�������Ƃ���A�u���ɕ{�i�V���{�j�v�ł����āA���̗��̂ł���u�ɕ{�v���L���ł���Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��B �@�@�q�R�r(a)�@���Y���i�ƊE�̎�����l�����邱�ƂȂ��A�ꗥ�ɒn��E�n���̕\���͎Y�n�E�̔��n�̕\���ɂ������A�������i�̎��ʗ͂������Ȃ��Ƃ���̂��A�]��ɉ��I�ł���B �@�@(b)�@��ނ̏��i�̓��ꐫ�́A�����E���@���ɂ���ʂ��ꂽ�u�����v�A�u�{�����v�A�u���Ď��v�A�u����v�A�u�����v���̕i���\�����`���Â����Ă������A���Y�i���K�i���̂��̂ɂ����Ă��A�e�����ɂ������Ȗ��⍁��̑��Ⴊ�����邱�Ƃł���B�����āA���̂悤�Ȗ����ɂ�鑊��������炷�v���Ƃ��ẮA�m���̋Z�\�o���A����蓙�̋Z�@�A�̓���A�����̎u�����Ƃ��������Ƃ̂ق��ɁA�����āA�d���݂̐��A�̌����i�y���A�O����A�①���Ȃǁj�A�̗��n�����A���R���A���ӂ̕��y���̎��R�v�����A���i�̎Y�n�̓������d�v�Ȗ������߂Ă��邱�Ƃ��w�E����Ă���B���������āA�ʓI�Ȗ��������邱�ƂȂ���A�u�����̎��v�A�u��̎��v�ȂǁA�ǂ̒n��E�n��̏��i��������ҁA���v�҂̏d�v�ȊS���ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��ے�ł��Ȃ��B�܂�A��ނɂ����ẮA���鏤�i�������̐��Y�n��L���A�Ȃ����͕����̎Y�n��\�����邱�Ƃ͋ɂ߂Ċ�L�Ȃ��Ƃł����āA�W�͂ɑ}�����ꂽ�n��E�n��̕\���́A���̋L�ڂƈ�̂ƂȂ��āA���i�����ʂ����ŁA���폤�i�ȏ�ɏd�v�Ȕ�d��߂Ă���A���W�̎�v�ȍ\���������Ȃ��ꍇ�������Ƃ�����B����ҁA���v�҂ɂ����Ă��A���Y�n���͎Y�n����\�킵�Ă�����̂ƔF�����A���̒n���ɒ��ڂ��邱�Ƃ���A�n���̕������������i�̎��ʋ@�\���ʂ����Ă�����̂Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@�@(c)�@���{�g��������s�́u�S�������ꗗ�\�v�i����Q���j�ɂ́A�S���̊e�����̐����̔����Ă����\�I�����Q��ނ܂ł��L�ڂ���Ă��邪�A���̒�������Ɂu�n���{���v�̂��̂���������ƁA���̐��͑����ɏ��B �@�@���Ƃ��āA�u�n���{�_�v�̂��̂����ƁA���̂Ƃ���ł���i���ʓ��́A�����������E����Q���،f�ڕł������B�j�B �@�@�u�]��̗_�v�i�_�ސ�E�Q�j �@�@�u���̗_�v�i�_�ސ�E�Q�j �@�@�u���q�̗_�v�i��t�E�T�j �@�@�u�{���_�v�i���E�P�T�j �@�@�u�}�g�_�v�i���E�P�U�j �@�@�u�Ȃ̗_�v�i�ȖE�P�V�j �@�@�u�Q�n�_�v�i�Q�n�E�Q�O�j �@�@�u�z�̗_�v�i�V���E�R�R�j �@�@�u�����_�v�i���s�E�R�X�j �@�@�u���_�v�i���E�U�R�j �@�@�u�H�c�_�v�i�H�c�E�V�Q�j �@�@�u���C�_�v�i�H�c�E�V�Q�j �@�@�u�\�o�_�v�ΐ�E�X�V�j �@�@�u�o�_�_�v�i�����E�P�Q�R�j �@�@�u�B��_�v�i�����E�P�Q�T�j �@�@�u�}���̗_�v�i�����E�P�S�O�j �@�@�u���Y�_�v�i����E�P�S�S�j �@�@�܂��A�u�n���{�сv�̂��̂����ƁA���̂Ƃ���ł���B �@�@�u�����сv�i��ʁE�P�O�j �@�@�u�����сv�i�Q�n�E�Q�P�j �@�@�u�����X�сv�i����E�Q�R�j �@�@�u��ȋсv�i����E�Q�S�j �@�@�u�M�Z�сv�i����E�Q�U�j �@�@�u���n�сv�i����E�Q�W�j �@�@�u����сv�i�V���E�Q�X�j �@�@�u�����сv�i�ޗǁE�S�X�j �@�@�u��Ëсv�i�����E�U�X�j �@�@�u�H�c�сv�i�H�c�E�V�R�j �@�@�u�O�d�сv�i�O�d�E�X�O�j �@�@�u���Z�сv�i�E�X�Q�j �@�@�u�b�ߋсv�i�E�X�T�j �@�@�u�ԍ�сv�i���R�E�P�P�T�j �@�@�u�n���{���~�v�����Ă��A �@�@�u�z�T���~�v �@�@�u��˂̊��~�v �@�@�u�{���~�v �@�@�u���T���~�v �@�@�u���h���~�v �@�@�u�L�̊��~�v �@�@�u�O�d�̊��~�v �@�@���̑����̕W�͂����݂��Ă���B�Ȃ��A���̂����A�u�z�T���~�v�i�V�����E�Ζ{������Ёj�����|�I�ɗL���ł��邱�Ƃ͎��m�̎����ł���B �@�@(2)�@������R�Q�i���W�@�S���P���W���j�ɂ��� �@�@�q�P�r�@�������W�ɂ����āA��Ђ̎�ʂ�Ǝ��\����������ɏȗ�����ė��̂ƂȂ���̂ł͂Ȃ��B �@�@�܂��A�u�����d�@�v�̓d�@��u�������쏊�v�̐��쏊����T�ɏȗ��ł��Ȃ�����A�u���~�v�̎��ȗ������Ɖ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B �@�@�q�Q�r�@���ɁA�u���~�v�������̗��̂ł���Ƃ��Ă��A���ꂪ�S���I�Ɏ��m�E�����Ƃ͓��ꂢ���Ȃ��B �@�@(3)�@������R�R�i���W�@�S���P���P�T���j�ɂ��� �@�@���p�e���W�́u���~�v�������Ɏg�p����錴���̏��W�Ƃ��đS���ɍL���m���Ă���Ƃ͓��ꂢ���Ȃ��B �@ |
| �m���R�n |
|
�P�@������R�P�i���W�@�S���P���P�P���j�ɂ��� �@(1)�@�{�����W�̊O�ρA�̌āA�ϔO�ɂ��� �@�@�q�P�r�@�{�����W�̍\���A�w�菤�i���i�R�����Q�łR�s�Ȃ����U�s�j�͓����Ҋԑ������Ȃ��A���R�i�R���j�̔��f�̂����A�{�����W�́A�ʎ��Q�̂Ƃ���̍\���������Ȃ���̂ł���Ƃ���A�Y��́A����̏��̂������ē���̑傫���A����̊Ԋu�ň�̓I�ɏ�����Ă�����̂ł��邱�Ƃ́A�����ҊԂɑ������Ȃ��B �@�@�����āA�{�����W�̍\�������̂����A�u�ɕ{�v�̕����́A�u�T�C�t�v�Ə̌Ă���邪�A��L�q�R�r�ɂ����ĔF�肷��悤�ɁA��ʂɂ͓���݂̔�����ł���A�u�ɕ{�v�̕�������A�L���m���Ă���u���ɕ{�v�Ȃ����u���ɕ{�V���{�v�Ɖ��炩�̊W�̂���Ӗ���L�����ł͂Ȃ����Ƃ̐��������邱�Ƃ͂ł��Ă��A���̐��m�ȈӖ��E���e����ʂɍL���m���Ă���Ƃ͔F�߂��Ȃ��B�����A�u���~�v�̕����́A�u�J���o�C�v�Ə̌Ă���A�����ɍ炭�~�Ƃ����Ӗ��̖����Ƃ��Ĉ�ʂɗ������꓾�邱�Ƃ͖��炩�ł���B �@�@���������āA�{�����W�ɐڂ���҂́A���̈Ӗ��𗝉�������u���~�v�̕��������ɒ��ڂ���Ɠ����ɁA�O�L�̂Ƃ��萄���͂ł��Ă����m�ȈӖ����L���m���Ă���Ƃ͂����Ȃ��u�ɕ{�v�̕��������ɂ��������Ē��ڂ�����̂Ƃ݂�̂����R�ł���A�O�Ϗ�̈�̐��Ƃ����܂��āA�����ꂩ����̕����݂̂������ď̌Ă����邢�͊ϔO������̂Ƃ͔F�ߓ�A�ނ����̂Ƃ��ď̌Ă��ϔO������̂ƔF�߂�̂������ł���B �@�@�q�Q�r�@�ȏ�̎����ɂ��A�{�����W�́A����̏��̂������ē���̑傫���A����̊Ԋu�ł܂Ƃ܂�悭��̓I�ɏ�����Ă�����̂ł���A����ɂ�萶����u�T�C�t�J���o�C�v�̏̌Ă��璷�Ƃ����قǂ̂��̂ł͂Ȃ��A��ǂ݂Ȃ��̌Ă�������̂ł��邩��A�{�����W����́A�u�T�C�t�J���o�C�v�Ƃ̈�A�̏̌Ă������A�P�Ɂu�J���o�C�v�Ƃ̏̌Ă���������̂Ƃ͔F�߂��Ȃ��B�ϔO�ɂ��Ă��A�{�����W�́A��L�̂悤�ɁA�O�Ϗ�A�̌ď�̈�̐����������̂ł��邩��A�P�Ȃ�u���~�v�Ƃ͈قȂ邠���ނ̓��ʂȊ��~�Ƃ̊ϔO�A���͑O�L�̂悤�Ȑ������瑾�ɕ{�Ȃ������ɕ{�V���{�ɂ䂩��̂��銦�~�Ƃ̊ϔO����������̂ƔF�߂���B �@�@�q�R�r�@�����́A�u�Y�n�E�̔��n�{���錾�t�����v�́A�u�Y�n�E�̔��n�v�̕����Ɏ������i�̎��ʐ����Ȃ����߂ɁA�u�����v�̕������v���ƂȂ�Ƃ���A�{�����W���́u�ɕ{�v�́A���݂̕��������ɕ{�s��тȂ������ɕ{�V���{�̏��ݒn���ӂł��镟�������ɕ{�s�ɕ{�Ƃ������̂̍s�����������Ă�����̂ł��邩��A�{�����W����́u�J���o�C�v�Ƃ̏̌Ă�������|�咣����B �@�@(a)�@�{�����W���́u�ɕ{�v�̕��������́A�u�ɑ��̖����A���ɕ{�̗��v���Ӗ������i��g���X�u�L������S�Łv�j�ƔF�߂��邱�Ɓi�R�����Q�R�łP�Q�s�A�P�R�s�j�͓����ҊԂɑ����͂Ȃ��A�b��U���ɂ��A�v������ďC�u�V�������V�����ꎫ�T�|�����E�Ì�|�v�i���a�T�V�N�P�O���Q�T�����s�j�ɂ���L�L�����Ɠ��|�̐���������Ă��邱�Ƃ��F�߂���B�����āA�b��W���ɂ��A�u�ɕ{�v�̌�́A���ɕ{�V���{�ߕӂ̍s����於�̂ł��邱�Ƃ��F�߂��A�R���̔F��̂����u�s����於�̂Ƃ��Ắw�ɕ{�x�����ɕ{�s�̈ꕔ�̒n��ł���A���̒n����̑��ɕ{�V���{�̖��̂��������^�����Ղ�_�ЂƂ��āA���邢�͔~�̖����Ƃ��āA��ʐ��l�ɍL���m���Ă���Ƃ��Ă��A�R������V���Ȃ�������X���ɂ��A�w���ɕ{�s�̑��ɕ{�V���{�x�̂悤�ɋL�ڂ���Ă��邱�Ƃ��F�߂��i��j�v���Ɓi�R�����Q�T�łS�s�Ȃ����W�s�j���A�����ҊԂɑ������Ȃ��B �@�@�������Ȃ���A��L�L�����ȊO�̂�菬�^�̎��T�ނɂ����Ă��u�ɕ{�v�̌ꂪ���^����A��������Ă��邱�Ƃ�F�߂�ɑ����؋��͂Ȃ��A�܂��A�u�ɕ{�v�����ɕ{�s�̈ꕔ�̒n�於�ł��邱�Ƃ��S���I�ɍL���m���Ă��邱�Ƃ�F�߂�ɑ����؋����Ȃ��B �@�@��������ƁA�u�ɕ{�v�͈�ʂɂ͓���݂̔�����Ƃ��킴����A�{�����W�ɐڂ������ҁA���v�ҁi�����̎���ҁA���v�҂́A��������k��B�n���ɋ��Z����҂����ł͂Ȃ��B�j�̑������A�u�ɕ{�v�̕�����S���I�ɒm���Ă��镟�����̑��ɕ{�Ȃ������ɕ{�V���{�Ɖ��炩�̊W������Ӗ���L�����ł͂Ȃ����Ƃ̐��������邱�Ƃ͂��蓾�邪�A���ꂪ�������̑��ɕ{�s�̈ꕔ�̒n��̖��̂Ȃ����s����於�̂ł���Ɛ��m�ɔF�����A�u�ɕ{�v���Y�n�E�̔��n�Ɠ��R�ɗ���������̂Ƃ͔F�߂��Ȃ��B���������āA�u�ɕ{�v�����v�ғ��ɂ��n���Ɨ�������邱�Ƃ�O��Ƃ��āA�{�����W����͒P�Ɂu�J���o�C�v�Ƃ̏̌ē���������|�̏�L�����̎咣�͗��R���Ȃ��B �@�@(b)�@����ɁA�{�����W���́u�ɕ{�v�����v�ғ��ɂ���Ēn���Ɨ�������邱�Ƃ�����Ƃ��Ă��A�{�����W�́A�u�ɕ{���~�v�ƈ�̂̂��̂Ƃ��ĔF������A�������i�̎��ʋ@�\��L���Ă�����̂Ƃ������Ƃ��ł���B �@�@���Ȃ킿�A����Q���؋y�ѕ٘_�̑S��|�ɂ��A���{�g��������i�����U�N�R���j���s�́u�S�������ꗗ�\�v�i����Q���j�ɂ́A�S���̊e�����̐����̔����Ă����\�I�����Q��ނ܂ł��f�ڂ���Ă��邪�A�u�n���i�n�������܂ށj�{���v�̖����̐��͋ɂ߂đ����ɏ��A���Ƃ��āA�u�n���{�_�i�ق܂�j�v�̂��̂����ƁA�O�L�R���̎�����R�ɑ��锽�_�Q(1)�q�R�r(c)�ɋL�ڂ̂��̂��܂߁A���Ȃ��Ƃ��P�X����A�u�n���{�сv�̂��̂��A���Ȃ��Ƃ��P�U���邱�Ƃ��F�߂���B���̑��ɂ��A�u�n���{�߁v�i�P�V�j�A�u�n���{���@�v�i�P�Q�j�A�u�n���{��v�i�U�j�A�u�n���{���v�i�T�j�A�u�n���{�j�R�v�i�S�j���̖������F�߂���̂ł���B�����āA���̎����y�ѕ٘_�̑S��|�ɂ��A�{�����W�ƈ��p�e���W�Ƃɂ����ċ��ʂ���w�菤�i�u�����v�͒n�搫�̋������i�ł���A�����̎���ҁA���v�҂́A�u�n���`�{�����v��u�n���a�{�����v�̂����A�n��������K�������Y�n���Ɨ��������ɁA�u�n���`�{�����v��u�n���a�{�����v�����ꂼ���̂̂��̂Ƃ��Ĕc�����邩�A���邢�́A�n���������Y�n���Ɨ������Ă��A�u�n���`�{�����v��u�n���a�{�����v��O���l�Ɉ�̂̂��̂Ƃ��Ĕc�����A������̏ꍇ���S�̂Ƃ��Ď������i�̎��ʕW���Ƃ��ĔF������ꍇ���������̂ƔF�߂���B �@�@�����́A�u�S�������ꗗ�\�v�́A������g�p����Ă�������̖��̂�P�ɗ�L���������̂��̂ł���A���̒��ɂ́A���W�o�^����Ă��炸�A���Ȃ��Ƃ��`���I�ɂ͑��l�̓o�^���W�̐N�Q�ɓ�������̂�A�R���~�X���̗��R�ɂ��d���o�^����Ă�����̂����݂��Ă���̂ł����āA���̂悤�Ȏ�������A���W���̒n��A�n��̕\���͑��̋L�ڂƈ�̂ƂȂ��ď��i�����ʂ����ŏd�v�Ȕ�d���߂Ă���Ȃǂƌ��_���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��|�咣���邪�A���ɁA�u�S�������ꗗ�\�v�Ɍf�ڂ���Ă�������̒��ɁA���W�o�^������Ă��炸���Ȃ��Ƃ��`���I�ɂ͑��l�̓o�^���W�̐N�Q�ɓ�������̓����ꕔ�܂܂�Ă���Ƃ��Ă��A��L�u�S�������ꗗ�\�v����́A�u�n���{�_�v�A�u�n���{�сv�A�u�n���{�߁v�A�u�n���{���@�v�̂悤�ɁA����̌��ɈقȂ�n�����g�ݍ��킳�ꂽ���̂������ɏ��W�Ƃ��đ����g�p����Ă��鎖���͔F�肷�邱�Ƃ��ł�����̂ł���A��������ׂď��W���N�Q�ɓ�������̂�R���~�X�ɌW����̂��P�ɗ�L����Ă���ɂ����Ȃ��ƔF�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ�����A���̓_�̌����̎咣�͍̗p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B �@�@�܂��A�b��Q�W�A��Q�X���ɂ��A�퍐�̗L���鏤�W�u�}��̊��~�v��t�������p�b�N���萴�����������̏����X�̂��炵���I�̕\���ɂ����āu���~�p�b�N�v�ƕ\������A�b��R�S���ɂ��A�T�����̘A�ږ��撆�̐����o���䎌�ɂ����āA�u�z�T���~�v���u���~�v�ƌĂ�Ă��邱�Ƃ��F�߂��邪�A�����̎����́A�{�����W�Ƃ͈قȂ鏤�W�ɂ��A�������ꕔ�̏����X�▟��ɂ�����\���ɂ����Ȃ����̂ł��邩��A�����̎�������{�����W�ɂ��Ă��A�u���~�v�Ə̌ē��������̂ł���ƔF�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B �@�@��������ƁA�{�����W���́u�ɕ{�v�����ɕ{�ƊW�̂���n���ƔF�������Ɖ��肵�Ă��A�{�����W�́A����ҁA���v�҂ɂ���āu�ɕ{���~�v�ƈ�̂̂��̂Ƃ��Ĕc������A�u�T�C�t�J���o�C�v�Ƃ̈�A�̏̌Ă������A�P�Ɂu�J���o�C�v�Ƃ̏̌Ă͐������A�ϔO�ɂ��Ă��A�u���ɕ{�Ȃ������ɕ{�V���{�ɍ炭���~�v�̂悤�ȊϔO������̂ƔF�߂���B �@(2)�@�{�����W�ƈ��p�e���W�Ƃ̑Δ� �@�@�q�P�r�@���p�e���W�̔F��i�R�����Q�łW�s�Ȃ����Q�R�s�j�A�y�ѓ��R�i�R���j�̔��f�̂����A���p�e���W���琶����̌āA�ϔO�̔F��i���Q�R�łQ�Q�s�Ȃ����Q�S�łS�s�j�́A�����ҊԂɑ������Ȃ��B �@�@�q�Q�r�@�{�����W�ƈ��p�e���W�Ƃ��r����ƁA�{�����W���琶����u�T�C�t�J���o�C�v�̏̌Ăƈ��p�e���W���琶����u�J���o�C�v�̏̌ẮA�u�T�C�t�v�̉��̗L���ɂ�薾�Ăɋ�ʂ��邱�Ƃ��ł�����̂ƔF�߂���B �@�@�q�R�r�@�܂��A�{�����W�́A�O�L�̂悤�ɁA�P�Ȃ銦�~�Ƃ͈قȂ邠���ނ̓��ʂȊ��~�Ƃ̊ϔO���́u���ɕ{�Ȃ������ɕ{�V���{�ɍ炭���~�v�̂悤�ȊϔO����������̂ł���̂ɑ��āA���p�e���W�́A�P�Ȃ�u���~�v�̊ϔO������̂ł��邩��A�����W�͊ϔO�㓯��ł���Ƃ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ����̂ł���B �@�@�q�S�r�@�����W���O�Ϗ㖾�炩�ɋ�ʂ����鍷�ق�L���邱�Ƃ́A�����ҊԂɑ������Ȃ��B �@�@�q�T�r�@�ȏ�ɂ��A�{�����W�ƈ��p�e���W�Ƃ́A�̌āA�ϔO�A�O�ς̂�����̓_�ɂ��Ă��قȂ��Ă���A�����I�ɑΔ䂵�Ĕ�ގ��̏��W�ł���Ƃ����ׂ��ł��邩��A�{�����W�͏��W�@�S���P���P�P���Ɉᔽ���ēo�^���ꂽ���̂ł͂Ȃ��Ƃ̐R���̔��f�Ɍ��͂Ȃ��A�����咣�̎�����R�P�͗��R���Ȃ��B �Q�@������R�Q�i���W�@�S���P���W���j�ɂ��� �@(1)�@�u���~�v�������u���~������Ёv�̗��̂ł���Ƃ��Ă��A���̗��̂��u�����ȗ��́v�ƔF�߂��邩�ۂ��̓_�ɂ��Ĕ��f����B �@�@�q�P�r�@�b��R�Ȃ�����T���̊e�P�A�Q�i���{�o�^���W��S���j�A�b��P�T���i����O�`���u���{��厖�T�v���a�T�R�N�P�Q�����s�j�A�b��P�U���i��w�Ɛ����Еҁu���{��S�����S�����v���a�T�V�N�P�P�����s�j�A�ǔ��V���Ёu���{�̖��𑠖��m���S�I�v���s���s���j�A�b��P�W���i��_�^���ďC�u��������v���a�U�R�N�P�Q���P�T�����s�j�A�b��P�X���i�u�k�Еҁu���{�̖������T�v�����Q�N�S�����s�j�A�b��Q�O���i��_�^���ďC�u���{���܂��r�`�j�d�@���ܐl�C�̋�����Q�U�T�I�v�����R�N�P�P�����s�j�A�b��Q�P���i��_�^���ďC�u���{�̂r�`�j�d�@�������䂭���Ď��Q�W�T�I�v�����S�N�P�P�����s�j�A�b��Q�Q���i�����Ғ��u���{�����T�v�����T�N�P�P�����s�j�A�b��Q�R���i�j��ވ�ҁu�ŐV�@���{����Ӂv�����U�N���s�j�A�b��Q�S���i���ԏ��X�u�����ɐ����v�����U�N�P�O�����s�j�A�b��Q�T���i�u�k�Еҁu���{�̖������T�v�����V�N�T�����s�j�A�b��Q�U�A��Q�V���i��j�ɂ��A�����̑O�g�ł����؉Ƃ́A�����S�N�i����P�W�Q�P�N�j�A�u���~�v�̏��W��p���Đ����̏����A�̔����J�n���A���̌�A�l�c�Ƃ��獇����Ђɑg�D�ύX���A���a�Q�X�N�ɍ�����Ћ��R��؏��X���犦�~������Ђ֏����ύX���������̂ł���A���a�R�T�N�Ɋ�����ЂւƑg�D�ύX�����āA���݂̊��~������ЂƂȂ������̂ł��邱�ƁA�����y�і{���e���W��t���������u���~�v�́A����܂Ŋe��̓��{���̎��T�⃀�b�N�{�̓��{���̎G�����ɑ��̎𑠂ƂƂ��ɏЉ�ꂽ���Ƃ����邪�A�{���Œ�o���ꂽ�؋��̂����A�{�����W�̓o�^�o�莞�܂ł̂��̂́A���s���s���̂��̓����܂߂Ă��A�O�L�b��P�T�Ȃ�����P�W��������ɂƂǂ܂邱�ƁA�����́A���{���̊ӕ]��Ȃǂɂ����Ă��т��ѓ��܂��Ă���A�������N�ɂ͊֓��M�z���ŋǎ�ފӕ]��ɂ����ĂR���A���ŋ��܂���܂��A�����W�N�x�̍��Œ�������������Â̑S���V���ӕ]��ŋ��܂���܂���Ȃǐ������̎�܂����Ă��邱�ƁA�������A�����́A�u���~�v��t������������ʌ��Ƃ��̋ߌ��𒆐S�Ƃ��Ĕ̔����Ă���A���̒n��ł̔̔��ʂ͂��قǑ����͂Ȃ����Ƃ��F�߂���i�Ȃ��A�����̐����u���~�v���֓��n���ȊO�ɑS���I�ɑ����̔�����Ă������Ƃ�F�߂鑫���I�m�ȏ؋��͂Ȃ��B�j�B �@�@�܂��A����Q���A��R���i��_�^�����u���{�̖����v�V���I���@���a�T�X�N�P���P�T���j�y�ѕ٘_�̑S��|�ɂ��A�{�����W�y�ш��p�e���W�ȊO�ɂ��A�����̏��W�Ƃ��āu���~�v���܂ނ��̂��p�����Ă����́A�������݂��Ă���Ƃ���A�{�����W�̓o�^�o�莞���͐ݒ�o�^�����A�u���~�v�̖��̂��܂ޏ��W�Ƃ��đS���I�ɍL���m���Ă����̂́A�u�z�T���~�v�i�V���s�̐Ζ{������Ёj�ł��邱�Ƃ��F�߂���B �@�@�q�Q�r�@�ȏ�ɔF��̎����ɂ��A�����̗��̂ł���u���~�v�⌴���̐������w�菤�i�Ƃ�����p�e���W�A���Ɉ��p���W�b�́A�{�����W�̓o�^�o�莞�i���a�U�R�N�P�Q���j�ɂ����āA�֓��n���𒆐S�ɒm����悤�ɂȂ�A�S���I�ȏo�ŕ��ɂ��Љ��邱�Ƃ����������Ƃ͔F�ߓ�����̂́A����炪�S���I�ɍL���m���Ă����Ƃ܂ŔF�肷�邱�Ƃ͂ł����A���ɂ��̔F����ɑ����؋��͂Ȃ��B �@�@����ɔ����錴���̎咣�͍̗p���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B �@(2)�@��������ƁA�u���p�e���W�������̋Ɩ��ɌW�鏤�i�u�����v��\�����邽�߂̂��̂Ƃ��āA�܂��A�u���~�v�̕\���������̗��̂�\�����̂Ƃ��āA�{�����W�̓o�^�o��O�����v�ҊԂɍL���F������Ă������̂Ƃ͔F�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�|�̐R���̔F��Ɍ��͂Ȃ��A�����咣�̎�����R�Q�́A���̗]�̓_�ɂ��Ĕ��f����܂ł��Ȃ��A���R���Ȃ��B �R�@������R�R�i���W�@�S���P���P�T���j�ɂ��� �@(1)�@�O�L�Q(1)�ɐ����̂Ƃ���A���p�e���W�������̋Ɩ��ɌW�鏤�i�u�����v��\�����邽�߂̂��̂Ƃ��āA�{�����W�̓o�^�o��O������ҁA���v�҂̊ԂɍL���F������Ă������̂Ƃ͔F�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ����̂ł���B �@(2)�@��������ƁA����Ɠ��|�̐R���̔F��Ɍ��͂Ȃ��A�����咣�̎�����R�R�́A���̗]�̓_�ɂ��Ĕ��f����܂ł��Ȃ��A���R���Ȃ��B �S�@���_ �@�@����āA�����̖{�i�����͗��R���Ȃ����炱������p���邱�ƂƂ��A�啶�̂Ƃ��蔻������B �@�i�����٘_�I���̓��@�����P�P�N�S���P�R���j �@�i�ٔ����ٔ����@�i��I���@�ٔ����@�����G���@�ٔ����@�s�쐳���j �@ �@ ���R �P�@�{�����W �@�{���o�^��2364864�����W�i�ȉ��u�{�����W�v�Ƃ����B�j�́A�u�ɕ{���~�v�̕����������ĂȂ�A��28�ށu��ށi��p���������j�v���w�菤�i�Ƃ��āA���a63�N12��7���o�^�o��A����3�N12��25���ɐݒ�o�^���ꂽ���̂ł���B �Q�@�����l�̈��p���W �@�����l�����p����o�^��45256�����W�i�ȉ��u���p���WA�v�Ƃ����B�j�́A�ʎ�(1)�Ɏ������\�����Ȃ�A��38�ށu�����v���w�菤�i�Ƃ��āA����44�N2��15���o�^�o��A��44�N3��23���ɐݒ�o�^����A���̌�A���a5�N6��30���A��26�N1��19���A��46�N8��30���A��56�N12��25���A����3�N5��29����5��ɂ킽�菤�W���������Ԃ̍X�V�o�^���Ȃ���Ă�����̂ł���B�������A�o�^��380356�����W�i�ȉ��u���p���WB�v�Ƃ����B�j�́A�ʎ�(2)�Ɏ������\�����Ȃ�A��38�ށu�����v���w�菤�i�Ƃ��āA���a23�N7��7���o�^�o��A��24�N12��20���ɐݒ�o�^����A���̌�A���a45�N11��28���A��55�N6��27���A����1�N12��19����3��ɂ킽�菤�W���������Ԃ̍X�V�o�^���Ȃ���Ă�����̂ł���B�������A�o�^��1010683�����W�i�ȉ��u���p���WC�v�Ƃ����B�j�́A�ʎ�(3)�Ɏ������\�����Ȃ�A��28�ށu�����v���w�菤�i�Ƃ��āA���a45�N11��20���o�^�o��A��48�N4��26���ɐݒ�o�^����A���̌�A���a58�N5��20���A����5�N5��28����2��ɂ킽�菤�W���������Ԃ̍X�V�o�^���Ȃ���Ă�����̂ł���B �R�@�����l�̎咣 �@�����l�́A�{�����W�̓o�^���Ƃ���A�R����p�͔퐿���l�̕��S�Ƃ���A�Ƃ̐R�������߂�Ɛ\�����āA���̗��R�y�ѓ��قɑ���ٔ������̂悤�ɏq�ׁA�؋����@�Ƃ��čb��1���Ȃ�������40���i�}�Ԃ��܂ށB�j���o���Ă���B (1)�{�����W�́A�ȉ��ɏڏq����悤�ɁA���W�@��4���1����11���A����8�����͓���15���A���@��8���1���A���@��46���1����1���ɊY��������̂ł��邩��A���̓o�^�͖����Ƃ����ׂ��ł���B (2)�{�����W�y�ш��p�e���W�́A���ꂼ��O�L�\�����Ȃ���̂ł���Ƃ���A�{�����W�ƈ��p�e���W�Ƃł́A�`���Ɂu�ɕ{�v�Ƃ������t���t����Ă��邩�ۂ��̍��ق͂���B�������A���́u�ɕ{�v�Ƃ������t�́A�u���ɕ{�v�̗��̂ł���A���Ղ́u���ɕ{�v�Ղ�u���ɕ{�V���{�v�̏��ݒn�A�����A���݂̕��������ɕ{�s��т̖��̂ł���i�b��T���؋y�эb��U���j�A���ό��̖����Ƃ��ėL���ȁu���ɕ{�V���{�v�̏��ݒn�ߕӂ͕��������ɕ{�s�ɕ{�Ƃ������̂̍s�����ł���i�b��7���j���Ƃ��炵�Ă��u�ɕ{�v���n���ł��邱�Ƃ͈�ʂɓ���݂��[�����̂ł���B �@���������āA�u�ɕ{�v�́A�P�Ɏw�菤�i�ɂ��ĎY�n��̔��n��\������ɂ������A�������i�̎��ʐ��������Ȃ������ł���B �@��������ƁA�u�ɕ{���~�v�ɐڂ������ҁA���v�҂́A�Y�n�A�̔��n�̊ϔO�u�ɕ{�v�n���Ƒ��ւ��āA�u�ɕ{�v�����̂��āA�e���݈Ղ�������ەt������u���~�v�̕�����E�o����Ƃ�����̑I���ɂ��A�u���~�v�̏̌āA�ϔO�������Ď���Ɏ����邱�Ƃ͖��炩�ł���i���Ȃ݂ɁA���������ٔ����̔����m���a27�N5��30���@�s�ٗ�W��3����4��784�ňȉ��n�́u�n���������`�e���́E�E������ȗ����āA�P�ɂ��̍\���������ł������ȕ����E�E�̗��̂��Ȃď̌Ă���ɂ�����̂��ʏ�ł���v�Ɣ������Ă���j�B �@���������āA�{�����W�ƈ��p�e���W�́A�̌ċy�ъϔO�ɂ����đ�����킵���������鏤�W�Ƃ����ĉߌ��ł͂Ȃ��B �@���W�̖`���ɒn����t�����ꍇ�A�n�������͎w�菤�i�̎Y�n�A�̔��n�Ɣ��f����A�n���ȊO�̕������������ʕW���Ƃ��Ď���Ɏ������Ƃ�������28�ނ̐R����Ƃ��āA�u���B�ւ̐��@�v�Ɓu���@�v�A�u�������g�v�Ɓu���g�v�y�сu�����单�v�v�Ɓu�单�i���@�j�v�����݂���i�b��8���Ȃ�������10���j�B �@��ވȊO�̏��i�ɂ��Ă̐R����i�A���A�u�َq�v��u�G���v�Ƃ������A�u��ށv�Ɠ��l�Ɉ�ʏ���҂�����I�ɏ����X�Ŗڂɂ��鏤�i�ɂ��Ă̐R����ł���A���i���قȂ�Ƃ͂����u��ށv���w�菤�i�Ƃ���{���̐R����ł���B�j�Ɍ��y����ƁA�n�������W�̖`���ɕt�����ꍇ�ɒn�������͎w�菤�i�̎Y�n�A�̔��n�ł���Ɣ��f���ꂽ�R����Ƃ��ẮA�u�������v�Ɓu���������v�A�u���}���v�Ɓu��ネ�}���v�A�u�����v�Ɓu�������Ⴂ�v�A�u�����i�̖��j�v�Ɓu���������v�A�u�A���o�C�g���v�Ɓu�����A���o�C�g���v�A�u�R�`���v�Ɓu�����R�`���v�A�u�ԗ�v�Ɓu���̉Ԃ���݁v�A�u�Ɋy���v�Ɓu���Ɋy���v�A�u���ъہv�Ɓu�암���ъہv�������݂���i�b��11���Ȃ�������19���j�B�������{���R���f�����ŏ\���ɎQ�l�ɂȂ�R����ł���B �@�Ȃ��A���������ٔ����̔����Ƃ��āA�u�n���{���錾�t�v��̏��́A����̑傫���̕����ɂāA��A�ɏ����ĂȂ鏤�W���A���Y�u���錾�t�v����Ȃ鏤�W�ɗގ�����|���������̂Ƃ��āA�u�����G��v�Ɓu���������G�v�y�сu�_���v�Ɓu���R�_���v�����݁i�b��20���؋y�ѓ���21���j���A��҂͍ō��ٔ����ł��ގ��Ɣ��f����Ă���i�b��22���j�B �@���������āA�{�����W�́A���W�@��4���1����11���A���@��8���1���ɊY������B (3)�����l�̑O�g�ł����؉Ƃ͕���4�N�i����1821�N�j�ȗ��A�p������180�N�߂��ɂ킽��u���~�v���W��p���Đ����������A�̔����Ă���B�����l�́A���a31�N�����͊��~������Ђł���A���a35�N�Ɋ��~������ЂƂȂ�A�u���~�v�̖��̂̏����̂��Ƃ�40�N�ȏ�ɂ킽�萴���u���~�v���������̔����Ă��Ă���A�����u���~�v�ƌ����Ί��~���A���~�ƌ����ΐ����u���~�v��F����������m�ƂȂ��Ă���A���̌��ʂƂ��āA�u���~�v�́A�����l�̏��W�Ƃ��Ă����łȂ��A�����l�̗��̂Ƃ��āA����ҁA���v�ҊԂɍL���F�������Ɏ����Ă���B �@���a53�N12�����s�u���{��厖�T�v�i�b��23���j�A���a57�N���s�u���{��S�����S�����v�i����24���j�A1990�N���s�u���{�̖������T�v�i����27���j�A1993�N���s�u�V�ғ��{�����T�@���I���𖼎��v�i����30���j�A1995�N5�����s�u���{�̖������T�v�i����33���j�ɂ́A���ꂼ�ꐿ���l�̐����u���~�v�������l�̖��̂Ƌ��Ɍf�ڂ���Ă���A1988�N���s�u��������v�i����26���j�ɂ́A�����l�́u���~�����v���u���I����260�v��1�ɁA����3�N���s�u���{���܂�SAKE�v�i����28���j�ɂ́A�����l�́u���~�����v���u���ܐl�C�̋����265�I�v��1�ɁA����4�N���s�u���{��SAKE�v�i����29���j�ɂ́A�����l�́u���Ď����~�v���u�������䂭���Ď�285�I�v��1�ɁA���ꂼ��I��A�����l�̖��̂Ƌ��Ɍf�ڂ���Ă���B�܂��A���a61�N���s�u���{�̖��𑠁E���m���S�I�v�i����25���j�y��1994�N���s�u�ŐV���{����Ӂv�i����31���j�ɂ����āA�����l�́A�O�҂͖��𑠁u�S�I�v��1�ɁA��҂́u���I542�����v��1�ɁA�I��A�����l�̐����u���~�v���Љ��Ă���A����6�N���s�u�����ɐ����@����4�N����6�N�S�����ŋǕʊӕ]���ܑ����ꋓ�f�ځI�v�i����32���j�ɂ́A�����l�͕���5�N�ӕ]���ܑ����Ƃ��āA�����l�̐����u���~�����v�Ƌ��ɏЉ��Ă���B �@��L�̊e��̓��{���Љ�G���̖��́A�{�����W�̓o�^�o����ȍ~�̔��s�ɌW����̂ł��邪�A����́A������u�n���u�[���v�����a60�N������J�n���A���̍����炱�̎�̎G�����p�ɂɔ��s���ꂽ���ƂɊ�Â����̂ł����āA����ȑO�ɂ����Đ����l�̐����̖��̂ł���A�����l�̖��́i���́j�u���~�v���L���ł͂Ȃ��������Ƃ��Ӗ�������̂ł͂Ȃ��B�ނ���A�ȑO����L���ł��邩�炱���A�u�n���u�[���v�̊J�n�Ɠ����ɂ��̎�̎G���ɏЉ��A�����Ɏ���܂łقږ��N�̂悤�ɏЉ��Ă���̂ł���B �@��L�̏��Ђ̏Љ�L���ɉ����āA�����l�́u���~�v�́A���{���̊ӕ]��Ȃǂɂ����āA��܂��Ă���Ƃ�������������B�����Ƃ��Č������Ă���ł��Â����̂Ƃ��ď��a31�N�x�̑S������i�]��̗D����i�b��34���j�A�ŐV�̂��̂Ƃ��Ă͕���8�N�x�̑S���V���ӕ]�������i����35���j���A���ɂ��u�֓��M�z�ǂ̊ӕ]��Ɏl����܁A�m���g���̎�����i�]��ł͗D���܂����т��юE�E�v�i����25���j�A�u���~�u�����h�͕������N�Ɋ֓��M�z���ŋǎ�ފӕ]���3���A���̋���܁B���a63�N�x�ɂ͏t�i���Ď�j�E�H�i�����j�ŘA����܂��ʂ����Ă���E�E�v�i����29���j�A�u����5�N�ӕ]���ܑ����v�i����32���j���A���X�̏܂��A���̂��Ƃ�����A�u���~�v�̏��W�͗L���ɂȂ�A����ҁA���v�ҊԂɍL���F�������Ɏ����Ă��邱�Ƃ��킩��B �@�{�����W�́A�����l�̒����ȗ��́u���~�v���܂ނ��̂ł���Ȃ���A�{�����W�̏��W���҂́A�����l�̏������ɖ{�����W�̏o����s�Ȃ��o�^�Ă���B���������āA�{�����W�́A���W�@��4���1����8���ɂ��Y������B (4)��L(3)�ŋL�ڂ����Ƃ���A�����l�̖��݂̂̂Ȃ炸�����l�̏��L�ɌW�鏤�W�u���~�v�́A�S���I�ɒm���Ă���ȏ�A�{�����W�̔@���u�ɕ{�v�̕������u���~�v�̕����̓��Ɋ����ďo��l����ށi��p���������j�u�ɕ{���~�v��̔�����A�����鏤�i�ɂ��A����ҁA���v�҂ɏ��i�̏o���ɂ��č������A���l���鐿���l�̋Ɩ��ɌW�鏤�i�ł��鐴���u���~�v�ƍ������邨����̂��邱�Ƃ͕K���ł���B �@����āA���ɖ{�����W�����W�@��4���1����8���y�ё�11���̂�����ɂ��Y�����Ȃ��Ƃ����ɂ���A�{�����W�́A���W�@��4���1����15���ɊY������B (5)���قɑ���ٔ� �q�P�r�퐿���l�́A����1���Ȃ�������3���i���ꎫ���j�������āA�u�ɕ{���s����於�ł���ɂ��Ă��A���Ԉ�ʂɍL���m��ꂽ�n���I���̂ł͂Ȃ��A�{�����W�͑��ꏤ�W�Ƃ�����v�|���_�Â��Ă��邪�A���̎咣�͋ɂ߂đÓ��łȂ��B �@�Ȃ�قlj���1���Ȃ�������3���ɂ́A�u�ɕ{�v�̍��ڂ͂Ȃ����A���̂��Ƃ��璼���ɁA�u�ɕ{�v���n���Ƃ��Ēm���Ă��Ȃ��A�Ƃ̌��_���������킯�ł͂Ȃ��B����1���́A���{���ɂ����đS���I�ɗL���Ȓn���ł���u�����v���u���v���A���ڂƂ��Ă͌������Ă���̂ł���i�b��36���j�B �@�܂��A�u���ɕ{�V���{�v���ό��n�Ƃ��ėL���ł���A���N�����̐l�X���K���ꏊ�ł��邱�Ƃ́A����7���Ȃ�������9�����疾�炩�ł���B �@�Ƃ���ŁA�b��37���́A�u���ɕ{�V���{�v�߂��̓y�Y�����̓X�����B�e�����ʐ^�ƁA���̌ˌ��ɕ\�����ꂽ�s�����̕\�����B�e�����ʐ^�̏ؖ����ł���B���̗ނ̕\���́A�u���ɕ{�V���{�v�ߕӂł͂����鏊�Ɍ����邱�Ƃ��炵�āA�u���ɕ{�V���{�v�N�K��鑽���̊ό��q�́A���n���u�ɕ{�v�Ƃ����s�����ł��邱�Ƃ�m���ċA�����̂ł���B �@���Ă݂�ƁA����1���Ȃ�������3���Ɂu�ɕ{�v�̍��ڂ��f�ڂ���Ă��Ȃ��Ƃ��A�ό����s��ʂ��āA�u�ɕ{�v���s����於�ł���n���ł��邱�Ƃ́A���Ԉ�ʂɒm���Ă�����̂ł���B����ɕt������ƁA�u�ɕ{�v�̌���u���ɕ{�V���{�v�ߕӂ̒n���Ƃ��Ďg�p���Ă���Ǝv�������u�ɕ{�̍g�~�v�u�ɕ{�̔��~�v�̏��W�������ɂȂ��Ă��鎖�������݂���i�b��38����1�y��2�j�B �@����炩�炷��A�u�ɕ{�v���u���ɕ{�V���{�v�ߕӂ̒n���ł��邱�Ƃ́A��ʂɒm���Ă���Ɖ�����̂��Ó��ł���B �q�Q�r�퐿���l�́A�u���ɕ{�v���u��ށv�̎Y�n�E�̔��n�Ƃ��ĔF�������悤�Ȏ����͂Ȃ��|�咣���邪�A����������ł���B �@���悻���i�u��ށv�̐��Y�́A���ꂪ�s�\�ƍl������悤�Ȓn���ȊO�A���{���ł́A�S���ÁX�Y�X�ŕĂ��͔|����A���������Ă���̂ł����āA����ҁA���v�҂͒n���ł���Ό����Ƃ��ď��i�u���{���v�̎Y�n�ƔF������B���������āA�u�ɕ{�v���Y�n�\���ƔF��������̂ł���B���̓_�ɂ��ẮA���{���̒ÁX�Y�X�ŕĂ��͔|������������Ă���Ƃ������R���鎖���Ɋӂ݂�A�u��O�́A���̗�O���咣����҂����ؐӔC���v�Ƃ̗��ؐӔC�̕��z�̖@�����炵�āA�퐿���l���u����ҁA���v�҂ɂƂ��āA�w�ɕ{�x���w�Y�n�x�ƔF������邱�Ƃ��L�蓾�Ȃ��v�|�ɂ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ɖ�����B �@�܂��A�ό��n�ł͓y�Y���������̓y�n�̒n����X���ȂǂŔ̔�����̂���ł��邩��A�u���ɕ{�V���{�v�Ƃ����ό��n�ߕӂł��A��ނ̔̔��͎���ҁA���v�҂ɂƂ��ė\�z����A����ҁA���v�҂́A�u�ɕ{�v�ɂ��A���Ȃ��Ƃ��̔��n�Ƃ̔F���͎����̂ł���B����ɁA���������ɕ{�s�ɕ{�ɂ���̓X�͑��݂��Ă���i�b��39���j�B �@�ȏォ�炷��A����ҁA���v�҂́A�u�ɕ{�v�ɂ��A�Y�n�A���邢�͏��Ȃ��Ƃ��̔��n�Ƃ̔F�������Ɖ�����̂��Ó��ł���B �q�R�r�퐿���l�́A�����l���������R������тɓ��������ٔ����y�эō��ق̔����ے肵�āA�u�z�T���~�v�Ɓu���~�v�ɂ��Ă̐R���i����4���j�������ɔ��_����̂ŁA�Y�R���̔w�㎖��ɂ��āA�܂����m�ɂ��Ă����B �@�u�n���{���錾�t�v�����Y�u���錾�t�v�ɗގ����邩�ۂ��Ƃ������ł��邪�A�Ⴆ�u�����^���[�v�Ɓu�^���[�v�̂悤�ɁA�u�n���{���錾�t�v���ŗL�����Ƃ��镨�����݂��A����ҁA���v�҂ɂƂ��ē��Y�ŗL�������L���m���Ă���ꍇ�ɂ́A�u�n���v�����Ɓu���錾�t�v�����Ƃ���̂Ƃ��ĔF������A�`���̒n�������͎Y�n�A�̔��n�ƔF������邱�Ƃ͂Ȃ����̂ł���B �@�������Ȃ���A��L�u�z�T���~�v�Ɓu���~�v�̐R���̂悤�ɁA�u�z�T���~�v�ɂ��āu�g�k�����n���̔����~�̉ԁh�̂��Ƃ��Ӗ������v�Ƃ̗��R�͑����ł͂Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�A�u�z�T���~�v������̔~�̉Ԃ̌ŗL�����Ƃ��đ��݂��Ă��炸�A����ҁA���v�҂́A�u�z�v���Y�n�A�̔��n�A�u���~�v��v���ƔF�����邩��ł���B �@���ɁA�u�z�T���~�v�Ɓu���~�v�̐R�����Ó��Ȃ��̂Ƃ���Ȃ�A�Ⴆ�A�u�������g�v�Ɓu���g�v�̐R����i�b��9���j�����l�̗��R�Ŕ�ގ��ɂȂ������ł���A�`���ɒn����t�������ׂĂ̏��W�́A�u�����n���́`�̂��Ƃ��Ӗ������v�Ƃ̗��R�ɂ���ގ��ƂȂ�Ƃ̌��_�Ɏ���A�Y�n�A�̔��n�\�������͎������i�̎��ʗ͂��Ȃ��A�Ƃ̏��W�@�̑�O����邱�ƂɂȂ�B �@�v���ɁA�u�z�T���~�v�Ɓu���~�v�̐R���̔w��ɂ́A�����l�́u���~�v�ȊO�Ɂu�z�T���~�v�Ƃ������W���o�^����Ă��鎖�������邽�߁A�u�z�T���~�v�Ɓu���~�v�Ƃɂ��Ă����l�ɔ�ގ��Ƃ��ׂ��ł͂Ȃ����Ƃ̔��f����ɗ����A���̏�ŁA���̗��R�Ƃ��āu�g�k�����n���̔����~�̉ԁh�̂��Ƃ��Ӗ������v�Əq�ׂ����̂Ɖ��߂����B �@�����ŁA�����l�́u���~�v�Ɓu�z�T���~�v�Ƃ̗������o�^����Ă��鎖���ɂ��āA�����������B�u�z�T���~�v�́A�������ł���Y�n�E�̔��n�\���ł���u�z�̍��v�̈Ӗ��́u�z�T�v���u���~�v�̖`���ɕt���������̂��̂ł���A���݂̏��W�@�̊�ɏƂ点�A�����l�̓o�^���W�u���~�v�Ɨގ����ēo�^�ł��Ȃ����̏��W�ł���B�������Ȃ���A�u�z�T���~�v�̓o�^�́A��������̏��W�@���œo�^���ꂽ���W�i�o�^��35980���A�b��40���j�ł���A�����̏��W�@�ɂ́A������u��g�p���v�̋K�肪�������Ă�����ւƂ��āA�P�ӎg�p�҂�ی삷�邽�߂ɑP�ӎg�p�҂ɑ��ē�d�o�^�𐳖ʐ��ĔF�߂Ă������̂ł���i�����n���ٔ������a39�N10��31�������A�������W��15��10��2626�ŁA����2634�ŎQ�Ɓj�B���̂悤�ȋK�肪��������̏��W�@�ɑ��݂��Ă������炱���A�����l�̗L����u���~�v������24�N�ɓo�^����Ă����ɂ�������炸�A�u�z�T���~�v���d���o�^���ꂽ�̂ł���B �@�u�z�T���~�v�Ɓu���~�v�̐R���́A��L�u�z�T���~�v�ɂ��Ă̖�������̏��W�@�ɑk�y�������Ȍo�܂̑��݂�m�炸�ɁA�u���~�v�Ɓu���T���~�v�Ƃ̗������o�^����Ă��鎖���ƃp�������ɍl���āA�u���~�v���o�^����Ă��Ă��u�z�T���~�v�͓o�^�����Ƃ̌��_��������s���A���̏�ŁA�u�g�k�����n���̔����~�̉ԁh�̂��Ƃ��Ӗ������v�Ƃ̕s�\���ȗ��R���t����ꂽ�̂ł��낤�Ɖ������B �@�ȏ�̂悤�ɁA�퐿���l�����Ȃ̎咣�̍����Ƃ��Ĉ��p����u�z�T���~�v�Ɓu���~�v�̐R���͑Ó��łȂ��A�u�����单�V�v�Ɓu�单���@�v�̐R���i�b��10���j�̂悤�ɁA�u�n���������邱�Ƃɂ��n���ƈ�̂ƂȂ������ʂȌŗL�����̊ϔO��������v�ꍇ�ɂ̂݁A�`���̒n���������Y�n�A�̔��n�\���ƂȂ�Ȃ��Ɖ�����̂������ł���B �q�S�r�퐿���l�́A�u�w�T�C�t�J���o�C�x�̏̌Ă�7���ŏ璷�Ƃ������A���݂Ȃ���A�ɏ̌Ă�������̂ł���v���Ƃ������ɁA�{�����W�́u���~�v�Ɣ�ގ��Ǝ咣���邪�A�u�������g�v�Ɓu���g�v�̐R���i�b��9���j�̗�ł��u�w�A�}�~�V���i�~�x�̏̌Ă�7���ŏ璷�Ƃ������A���݂Ȃ���A�ɏ̌Ă�������̂ł���v�Ƃ���A�u���g�v�ɗގ�����Ƃ̔��f��������Ă���̂ł���B���������āA�퐿���l�̂��̎咣�͗��R���Ȃ��B �@�܂��A�퐿���l�́A�u�������́A�����Ԋu�A�����傫���ň�A�ɕ\�L���A���Ɍy�d�̍������o�����Ƃ��ł��Ȃ����O�Ϗ�܂Ƃ܂�悭��̓I�ɍ\������Ă���v���Ƃ������ɖ{�����W�́u���~�v�Ɣ�ގ��Ǝ咣���邪�A�u�����单�V�v�Ɓu�单���@�v�̐R���i�b��10���j�̗�ł��u�����单�V�v�́u�������́A�����Ԋu�A�����傫���ň�A�ɕ\�L���A���Ɍy�d�̍������o�����Ƃ��ł��Ȃ����O�Ϗ�܂Ƃ܂�悭��̓I�ɍ\������Ă���v�i�b��41���j�̂ł��邩��A���̎咣���܂����R�ɂȂ�Ȃ��B �q�T�r�퐿���l�́A�{�����W�̊ϔO�ɂ��u���ꏤ�W�ł���A�ϔO��L���Ȃ��v�Əq�ׂ邪�A�����ɂ͌ŗL�̈Ӗ�������A�������W�ɐڂ���҂͂�����Ӗ��ɂ��܂Ƃ܂�Ƃ��Ēm�o������̂ł��邩��A�{�����W�ɐڂ������ҁA���v�҂́A�u�ɕ{�v�Ɓu���~�v�Ƃ�2�̂܂Ƃ܂�ƔF������͖̂��炩�ł���B �@�퐿���l�́A�u�q�P�r�̌Ăɂ��āv�y�сu�q�Q�r�ϔO�ɂ��āv�ɂ����āA�u�w���t�ɍ炭�������̔~�x�̊ϔO�������ď̌Ă����v�A�u�w�ɕ{�x���w���ɕ{�x���w���Ƃ��Ă��A�E�E�w���t�ɍ炭�������̔~�x�ƊϔO����̂���ʓI�v�Ƃ��邪�A�������Ƃ���ƁA���̂悤�Ȗ�����������B�u�ɕ{�̍g�~�v�u�ɕ{�̔��~�v�̏��W�i�b��38����1�y��2�j�́A�{�����W�ƊϔO������ƂȂ�A�����2���̏��W�͌�������Ȃ��������ł���B�u���ɕ{�V���{�v�́u�������̔~�v���܂ޔ~�ɂ��Ă͉���7���⓯��8���Ɏ������悤�ɁA�����܂ł��u��~�v�u���~�v�u�g�~�v�Ə̂���Ă���A������u���~�v�Ə̂��邱�Ƃ͊F���ł���Ƃ������R���鎖���ɔ�����B���������āA�{�����W�ɐڂ������ҁA���v�҂́A�Y�n�A�̔��n�́u�ɕ{�v�Ɨv���u���~�v�Ƃ̌����Ɣc������̂��ʏ�ł���B �q�U�r�퐿���l�́A�����W�̊O�ϔ�ގ����咣���邪�A�u�����单�V�v���W�̑ԗl�i�b��41���j�Ɓu�单���@�v���W�̑ԗl�i�b��10���j�Ƃ��r����A�O�Ϗ�̍��ق������Ă��o�^�����Ƃ���̂�W���Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���B �q�V�r�퐿���l�́A����11���Ȃ�������22���������Ă��邪�A�����l�́A����11���́u�����̊��~�v�ɂ��āA���łɏ��W�@46���1���Ɋ�Â��o�^�����R���𐿋����Ă���i����8�N�R����7364���j�B �@���������A����11���́u�����̊��~�v���o�^�Ɏ����Ă��܂����̂́A�u�z�T���~�v���o�^����Ă��邱�Ƃ���A�P���Ƀp�������ɍl���A�u�z�T���~�v�ɂ͖�������̓���Ȍo�܂����鎖����m�炸�ɁA���������o�܂̂Ȃ��u�����̊��~�v���o�^���Ă��܂����̂ł͂Ȃ����Ǝv������Ƃ���ł���B �@�܂��A�퐿���l�́A����23���������u�w���~�x�̕������܂ޏ��W��t�������i�������̎s��ɑ������݂���v�Ƃ��s��̍����͂Ȃ��A�Ƃ��邪�A����͘_���̔��ł���B����q�b�g���i�����������ƁA����Ɠ���̏��W��ގ��������W��t�������i���A�ǂ������u�֏揤�@�v���������u�C���Łv�Ƃ��Ē����ɂ��ӂ��̂́A�悭���邱�Ƃł���B�{���R��������A�u�����̊��~�v�ɑ���o�^�����R�������́A�����l�́u���~�v�ɂ��āu�֏揤�@�v���s�Ȃ��҂������Ă����̂ŁA�����U�u���~�v�u�����h�������܂낤�Ƃ̐����l�̕��j�Ɋ�Â����̂ł����āA�퐿���l�̗����́A���Ɂu���~�v�̐N�Q�҂��������邱�Ƃ������Ď��Ȃ̍R�قƂ��悤�Ƃ��Ă�����̂ł���A�s���ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���B �q�V�r�퐿���l�́A���m�A�������ɂ��āA��̓I�ȏ؋�����Ă��Ȃ��A�Ƃ��邪�A�����l�͍b��23���Ȃ�������35�����o���Ă���B���̂����A���Зނ͑S���{�ɗ��ʂ��Ă���B�N�Ԑ����ʂȂǂ̔퐿���l�E���̎����̏��������܂ł��Ȃ��A�����̑��Ƃ��ďo�ŎЂ̎�ނ̑ΏۂƂ���A��ދL���̌f�ڂ��ꂽ���Ђ��S���ɗ��ʂ��A�S���̏��X�ŏ���҂ɔ̔����ꂽ�����������Ă���A���m�A�������͖������Ă���B �@�퐿���l�́A�b��23���Ȃ�������25�����u�J�^���O�I�F�ʂ��Z���A�����l�̈�L���L���ɂ����Ȃ��v�Ǝ咣���邪�A���ꂱ�������̍������Ȃ���掂ł���B�����l�̏��i�u���~�v���f�ڂ������ЌQ�̏o�ŎЂ�����̏o�ŎЂň�Ђł���A���炩�̃R�l�ōL������Ɍf�ڂ��Ă�������̂ł͂Ȃ����Ƃ̍R�ق����藧�����悤���A���ꂼ��ɏo�ŎЂ͈قȂ�̂ł��邩��A�L���L���ł���͂����Ȃ��B�������A�b��25���́u�ǔ��V���Ёv�Ƃ������{�L���̏o�ŋƎ҂��A�������݂�����{���̑�������S������I��Ŏ�ނ��A���s�����{�ł���A���������鑠�́u���~�v�u�����h�����炱���f�ڂ��ꂽ�̂ł���B �@�܂��A�n���u�[����������ȑO�́A���̎폑�Ђ͔��s����Ă��Ȃ��������A�����l�́u���~�v�y�ѐ����l�̗��́u���~�v�́A����ȑO����L���ł��������Ƃ́A�O�L�����Ƃ���ł���B �@����ɁA�퐿���l�́A����24���؋y�ѓ���25���������Ĕ��_���邪�A�u�S���V���ӕ]��v�����Ђ���i�]��̈�ł��邱�Ƃ͔F�߂�ɂ��Ă��A���̕i�]��ȂǂŎ�܂������u���~�v�y�т��̑������̗��́u���~�v������ҁA���v�҂ɒm���Ă���������S���������A���������u�S���V���ӕ]��v�̎�܂łȂ���A���m�A�������̗��ɖ𗧂��Ȃ����̂��Ƃ��c�_�͕s���ł���B �q�W�r�퐿���l�́A�ō��ُ��a57�N11��12�������������ɁA�����l�̗��̂́A�u������Ёv���������u���~�v�ł���A�{�����W�ɂ́u���~�v�̕����͊܂܂�Ă��Ȃ��|���_���邪�A����́A���Y�ō��ٔ�������܂�Ɏێq��K�ɉ��߂������ʂł����đÓ��ł͂Ȃ��B �@��Ђ̏ꍇ�A���̏�������u������Ёv�u�L����Ёv�Ƃ������������������c�肪���̂ɂȂ�ꍇ���������A��L�����́u���̂́A�K���A��������w������Ёx�w�L����Ёx�Ƃ������������������c��ł���v�Ƃ܂ł͔������Ă��Ȃ��B�Ⴆ�A��N�H�Ɍo�c�j�]���ă}�X�R�~�ő傫�����グ��ꂽ�u������ЎR��،��v�́A�u�R��v�Ɨ��̂���Ă����B���̑��A�u������ЎO�a��s�v���u�O�a�v�A�u������Г������쏊�v���u�����v�Ɨ��̂����悤�ɁA�u������Ёv�u�L����Ёv�Ƃ����������݂̂Ȃ炸�A���̋Ǝ�������u�،��v�u��s�v�u���쏊�v���܂�������ė��̂ƂȂ�̂ł���B�i����28���؎Q�Ɓj �@�����l�̗��̂́A�u������Ёv�y�ыƎ�������u�v���������u���~�v�ł���B�i�b��25���ɂ́u���̒n�Ɂw���~�x�������n�Ƃ����̂́v�Ƃ̋L�ڂ�����A�܂��A����28���ɂ́u�����E���~�́A�E�E�v�Ƃ��邱�Ƃ������������悤�j���������āA�{�����W�́u���~�v���܂ނ͖̂��炩�ł���B �S�@�퐿���l�̎咣 (1)�퐿���l�́A���_���|�̐R�������߂�Ɠ��ق��A���̗��R�����̂悤�ɏq�ׁA�؋����@�Ƃ��āA����1���Ȃ�������28�����o���Ă���B (2)���W�@��4���1����11���y�ѓ��@��8���1���ɂ��āA �q�P�r�����l�́A�{�����W���́u�ɕ{�v�́A�n���ł���̂ŁA�w�菤�i�̎Y�n�A�̔��n�\���ɂ������A�������i�̎��ʐ���L���Ȃ�����A�{�����W�́u���~�v�̏̌āA�ϔO�������Ď���Ɏ�����A�����W�͗ގ����鏤�W�ł���|�咣���A�b��5���Ȃ�������7���������Ă���B �@�������Ȃ���A�荠�ȉ��i�ʼnƒ�ł���ʓI�Ɏg�p����鉳��1���Ȃ�������3���i���ꎫ�T�j�ɂ́A�u�ɕ{�v�̋L�ڂ��Ȃ����Ƃ��炷��A�u�ɕ{�v���s����於�ł���ɂ��Ă��A���Ԉ�ʂɍL���m��ꂽ�n���I���̂ł͂Ȃ��A�{�����W�͑��ꏤ�W�ł���B �@���������āA�{�����W���u���~�v�̕��������݂̂��������i���ʕW���Ƃ��Ď���Ɏ�����邱�Ƃ͂Ȃ����̂ł���B �q�Q�r���ɁA�S�������āA�u�ɕ{�v�̕������u���ɕ{�̗��́v�Ƃ����n���Ƃ��ĔF�����ꂽ�Ƃ��Ă��A�����ɒn�����Y�n�A�̔��n��\��������̂Ƃ��ďȗ�����A�n���ȊO�̕������������i���ʕW���Ƃ��Ď���Ɏ�����邱�Ƃ́A�ȉ��̗��R�ɂ��Ȃ����̂Ǝv�������B �@�܂��A�u���ɕ{�v���w�菤�i�u��ށv�₻�̌����ł���Ă̎Y�n�A�̔��n�Ƃ��ĔF�������悤�Ȏ����͂Ȃ��A�����l���A���炻�̂��Ƃɂ��Ă͗����Ă��Ȃ��B �@�܂��A�����l�́A�{�����W���u���~�v�̕����������Ď�������\��������؋��Ƃ��āA�b��8���Ȃ�������19���؋y�эb��20���Ȃ�������22���������Ă���B�������Ȃ���A�����̐R���ŋ�����ꂽ���W�̒n�������ɊY������u���B�v�A�u�����v�A�u�����v�A�u���v�A�u���v�A�u�����v�A�u�����v�A�u�암�v�A�u�����v�A�u���R�v�́A��q�̍��ꎫ�T�ɂ��n���Ƃ��ċL�ڂ���Ă���B�������A���̐R���y�є����̗��R������ɁA�P�ɏ��W�\�����̒n�������������Ƃ݂̂ŏ��W��ގ��Ɣ��f�������̂ł͂Ȃ��A���̑ΏۂƂȂ������W�̊O�ρA�̌āA�ϔO���тɎw�菤�i�A���i����̎���𑍍��I�ɍl�����������ŁA�ގ��ł���Ɣ��f���Ă���B���������āA�����̏؋��͖{���ɂ��č̗p����ɒl���Ȃ����̂ł���B �q�R�r�ȏ�̓_���ӂ܂��āA�{�����W�ƈ��p���W�̗ގ����ɂ��Ĕ��f�����ꍇ�A �@(a)�̌Ăɂ��āG�{�����W�́A����4���������́A�����Ԋu�A�����傫���ň�A�ɕ\�L���A���Ɍy�d�̍������o�����Ƃ��ł��Ȃ����O�Ϗ�܂Ƃ܂�悭��̓I�ɍ\������Ă���B�����萶����u�T�C�t�J���o�C�v�̏̌Ă�7���ŏ璷�Ƃ������A���݂Ȃ���A�ɏ̌Ă�������̂ł��邽�߁A�u���~�v�̕��������݂̂��Ɨ����ĔF������邱�Ƃ͂Ȃ����̂ł���B���������āA�{�����W�́A���̍\�������ɑ������āu�T�C�t�J���o�C�v�̏̌Ă݂̂��A���p���W���琶����u�J���o�C�v�Ƃ͏̌ď��ގ��ł���B �@���̂��Ƃ́A�w�菤�i�u��ށv�ɂ����āA�{���Ɠ������ꓪ�ɒn����t�������W�Ƃ��̒n�������������W�ŁA�����̔�r����2�̏��W���{���Ɠ���7����4���ł���u�z�T���~�v�Ɓu���~�v���̌ď��ގ��ł���Ƃ����R���i����4���j��������炩�ł���B���̐R���ɂ����āA�u��T���~�v�́A�u�\�����w�z�x�̕����́A���Ƃ̖k�����i�E�E�j��\���A�w���~�x�̕����͔��F�̔~�̉Ԃ��Ӗ����邱�Ƃ���A���̏��W�S�̂���g�k�����n���̔����~�̉ԁh�̂��Ƃ��Ӗ�������e�Ղɗ�����������̂Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂��A�O���́w�z�T�x�̕����ƌ㔼�́w���~�x�̕����Ƃ́A���́A�����̑傫���A�Ԋu���������A�O�Ϗ�܂Ƃ܂�悭��̓I�ɕ\������A���Ɍy�d�̍��������������Ƃ��ł��Ȃ����̂ł���B�������A���̏��W���琶����ƔF�߂���̌āw�R�V�m�V���E���x�����݂Ȃ���A�ɏ̌Ă�������̂ł���A�w���~�x�̕��������݂̂��Ɨ����ĔF�������ƌ���ׂ����i�̎���݂͂������Ȃ��B�����Ƃ���A�{�菤�W�́A���̍\�������ɑ������āw�R�V�m�V���E���x�̏̌Ă݂̂�����̂Ƃ݂�̂������ł���B�E�E�v�Ƃ����ӂ��ɁA���W��F������ۂ́A�n�������ނ���A�ϔO�A�O�ρA�̌Ẳ����𒆐S�ɔ��f���Ă���B�{�����W�����̐R����Ɠ��l�ɁA���W�S�̂�����̊ϔO���邱�ƁA�O�Ϗ����̕s���ł��邱�ƁA�̌Ă��璷�łȂ����Ƃ͑O�q�����Ƃ���ł���B �@�܂��A�{�����W�Ǝw�菤�i���قɂ���ɂ��Ă��A�{�����W�Ɠ��l�Ɉ�ʎ��v�҂�ΏۂƂ������i���w�菤�i�Ƃ����u�g���c�y�v�Ɓu�c�y�v�A�u���s�啧�v�Ɓu�啧�v���A��������̌ď��ގ��Ƃ����R����i����5���A����6���j�����邪�A��������O�Ϗ�̂܂Ƃ܂�̂悳��ϔO�A�̌Ẳ����̓_���珤�W�S�̂������ėޔ۔��f�����A���̏�Ŕ�ގ��Ɣ��f���Ă���B �@�������āA�{�����W���琶����̌āu�T�C�t�J���o�C�v�ƈ��p���W���琶����̌āu�J���o�C�v���r����ɁA���̌ẮA���\���̍��ٓ��ɂ��A���ꂼ���A�ɏ̌Ă�����A�\���Ɏ��ʂ�������̂ł���B �@�܂��A���ɐ����l�咣�̔@���A�u�ɕ{�v���u���ɕ{�v���w���Ƃ��Ă��A���l�́A�����ŗL���Ȕ�~��z�N���A�{�����W�͑S�̂Ƃ��āu���t�ɍ炭�����̔~�v�̊ϔO����B�������A�u���ɕ{�V���{�v���w��̐_�l�ł��鐛�����Ƌ��ɁA�~�̖����Ƃ��Ĉ�ʂɍL���m���Ă���i����7���Ȃ�������10���j���Ƃ��炷��A�u�ɕ{�v�̕��������W�S�̂ɗ^����e���͑傫���A�̌Ă���ۂɁA�\���S�̂���̕s���̂��̂Ƃ��āA�u���t�ɍ炭�������̔~�v�̊ϔO�������ď̌Ă����B �@����āA�����W�͏̌ď��ގ��Ǝv�������B �@(b)�ϔO�ɂ��āG�{�����W�́A���ꏤ�W�ł���A�ϔO��L���Ȃ����A�����Ă����A�u�ɑ��̖����ő��t�ɍ炭�~�v�̊ϔO������̂ł���B�����A���p���W�́u�����ɍ炭�~�v�̊ϔO����B �@�܂��A�S�������āA�����l�咣�̔@���A�u�ɕ{�v���u���ɕ{�v���w���Ƃ��Ă��A�O�q�̂悤�ɐ��l�́u��~�v��z�N���A�u���t�ɍ炭�������̔~�v�ƊϔO����̂���ʓI�ł���A�P�Ȃ�u���~�v�Ƃ͕ʈق̊ϔO���A�����W�̊ϔO�͖��炩�ɈقȂ�B �@(c)�O�ςɂ��āG�{�����W�͊����S�������S�V�b�N�̂�p���ĕ��ʂɏ����ĂȂ���̂ł���B�����A���p���WA�AB�́A���ɐ}�`�Ɗ���2��������Ȃ錋�����W�ł���A�����̕��������͓���ȏ��̂�p�������̂ł���B���p���WC���܂�����ȏ��̂�p���ĂȂ鏤�W�ł���B���������āA�{�����W�ƈ��p�e���W�́A���Ə����قɂ��Ċώ@�����ꍇ�ł��A�݂��ɈقȂ��ۂ�^���邱�Ƃ͖��炩�ł����āA�O�Ϗ��ގ��ł���B �@�ȏ�̂��Ƃ��A�{�����W�ƈ��p�e���W�͔�ގ��̏��W�ł���A�������邱�Ƃ͂Ȃ��B �q�S�r�Ȃ��A�w�菤�i�u��ށv�ɂ����āA�ߋ��̓o�^��y�ь�������T�ς���ƁA�\�����Ɂu���~�v�̕������܂ޏ��W�́A�{���Ɠ��l�ɒn�����ꓪ�ɗL������̂����ł��A�������݂���i����11���Ȃ�������22���j�B�����͂�������A�{���Ɠ��l�ɒn�����Y�n�A�̔��n�Ƃ��ďȗ�����邱�ƂȂ��\���S�̂���̕s���̂��̂Ƃ��ĔF������邱�ƂŁA���p���W�Ƃ͔�ގ��̏��W�Ƃ��Ĕ��f����A�����y�ѓo�^���ꂽ���̂ł���B �q�T�r�܂��A�u���{���x�X�g�Z���N�V����392�v�i����23���j�̏Љ�L������������炩�Ȃ悤�ɁA�u���~�v�̕������܂ޏ��W��t�������i�������̎s��ɑ������݂��邱�Ƃ��犨�Ă���A���ɂ����𐿋��l�̎咣�ǂ���ɒn�����t����Ă��邱�Ƃ𗝗R�Ɂu�J���o�C�v�Ə̌Ă�������s�����ꍇ�́A���݂̏��i�̎��ʂ��s�\�ƂȂ�A�s��͍�������͂��ł��邪�A���̂悤�ȍ����͌����ɂ͋N���Ă��炸�A����̎��ۂɂ����Ă��{�����W���u�ɕ{���~�v�ƔF������A���W�u���~�v�Ƃ͕ʈق̏��i�Ƃ��Ď������Ă��邱�Ƃ͖��炩�ł���B (2)���W�@��4���1����8���y�ѓ���15���ɂ��āA �q�P�r�����l�́A���m�A�������𗧏����̓I�ȏ؋��A�Ⴆ�A���p���W���g�p���鏤�i�̔N�Ԑ����ʁA�N�Ԕ��㍂�A�̔��o�H�A�̔��n�擙��������Ă��Ȃ��B�܂��A�؋��Ƃ��Ē������s���b��23���Ȃ�������33���A����34���؋y�ѓ���35���̂����A�{�����W�̓o�^�o����O�̂��̂́A�b��23���Ȃ�������25���؋y�ѓ���34����4���݂̂ł���B����9���́A��������{�����W�̓o�^�o����ȍ~�̂��̂ł��邽�߁A���p���W���L����ʂɔF����������m�ł��������Ƃ𗧏�����̂ɂ͂Ȃ蓾�Ȃ����̂ł���B �@�����l�́A��L�{�����W�̓o�^�o��ȍ~�̏؋���o�Ɋւ��A�u�n���u�[�������a60�N������J�n���A���̍����炱�̎�̎G�����p�ɂɔ��s����o�������ƂɊ�Â����̂ŁA�w���~�x���ȑO����L���ł��邩�炱���A�n���u�[���̊J�n�Ɠ����ɂ��̎�̎G���ɏЉ��A�����Ɏ���܂ŁA�قږ��N�̂悤�ɏЉ��Ă���v�|�������Ă��邪�A���̋L�q�ɂ͉��̍������Ȃ��A�؋��Ƃ��Ē�o�������̎�̊��s���̔��s���{�����W�o����ȍ~�ł��������Ƃ�ى�����ɂ����Ȃ��B �q�Q�r�{�����W�̓o�^�o����O�ɔ��s���ꂽ���s���ɂ��Č�������ɁA�b��23���Ȃ�������25���́A�J�^���O�I�F�ʂ��Z���A�����l�̈�L���L���ɂ����Ȃ����̂ł��邽�߁A���p���W�̎��m�A�������𗧏�����̂Ƃ͂Ȃ蓾�Ȃ��B �@�܂��A�����l�́A�b��34���i���a31�N�x�S������i�]��̗D����j�⓯��25���i�u�֓��M�z�ǂ̊ӕ]���4����܁A�m���g���̎������i�]��ł͗D���܂����т��ю��v�̋L�ځj�������āA���m�A�����ł��邱�Ƃ��咣���Ă���B �@�������Ȃ���A���m�A�������𗧏���悤�ȎƊE�ɂ����čł����Ђ�����{���̕i�]��Ƃ����A����44�N�ɔ��������݂ł������Ă���u�S���V���ӕ]��v�ł���A���̂��Ƃ͉���24���i���{�̎��Â���j�A����25���i���a60�N�R����24895���R���j�̋L�ڂɒ����A���炩�ł���B �@�u�S���V���ӕ]��v�̋��܂̑I�l���@�ɂ��ẮA����26���i���{���x�X�g�Z���N�V����392�j�ɋL�q�̂Ƃ���ł��邪�A���p���W���g�p�������i���A�{�����W�̓o�^�o��O�Ɂu�S���V���ӕ]��v�ɂ����ċ��܂���܂��������͂Ȃ��B �@�܂��A�u�S������i�]��v�i�b��34���j�́A����27���i������̗������j�ɋL�ڂ̔@���A�u���{��������v����ЂɌĂт�������40�N�ɊJ�n����A��O�́u�S���V���ӕ]��v�ȏ�ɐ���ɊJ�Â���Ă������A���a13�N�Œ��~�ƂȂ�A���͏��a27�N�ɕʒc�̂ɂ�蕜���������̂́A�u�N�J�Âŏ��a33�N�̑�4��������Ē��~�ƂȂ����o�܂����邽�߁A���̏�������āA�{�����W�̓o�^�o����ȑO�Ɏ��m�A���������擾���Ă������Ƃ𗧏���ɑ������̂Ƃ͓��ꌾ���Ȃ��B���ɁA�S�������āu�S������i�]��v�����Ђ���i�]��ł������Ƃ��Ă��A�{�����W�̓o�^�o������32�N���O�̘b�ł���A���݂ł͊J�Â���Ă��Ȃ����Ƃ��炷��A���m���𗧏�����̂ł͂Ȃ��B���������āA����琿���l�̂������܂̎�܂̎����������Ă��Ă��A���p���W�̎��m�A�����������痧������̂ł͂Ȃ��B �q�R�r�����l�́A�퐿���l�������l�̏������ɂ��̒����ȗ��́u���~�v���܂ޖ{�����W�̏o����s���o�^�Ă���̂ŁA���W�@��4���1����8���ɊY������|�咣���邪�A�����l�̖��̂́A�u���~������Ёv�ł���A���̗��̂́u������Ёv���������u���~�v�ł���B���̂��Ƃ́A�ō��ُ��a57�N11��12���̔����i����28���j�ŁA�u������Ђ̏������犔����Ђ̕����������������͏��W�@4��1��8���ɂ����w���l�̖��̗̂��́x�ɂ�����A�E�̂悤�ȗ��̂��܂ޏ��W�́A�E���̂����Y��Ђ�\��������̂Ƃ��āw�����x�ł���Ƃ��Ɍ���A���W�o�^���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�v�|���f�������Ƃ�������炩�ł���B �@���Ă݂�ƁA�{�����W�́u�ɕ{���~�v�ł���A���̗��́u���C�v���܂܂��A���A�����l�����̂ł���Ƃ���u���~�v���O�q�����悤�Ɏ��m�A�����łȂ����Ƃ͖��炩�ł���B (3)�ȏ�A�{�����W�́A���W�@��4���1����11���A����8���A����15���A���@��8���1���ɊY�������A���������āA���@��46���1����1���ɊY�����Ȃ����̂ł���B �T�@���R�̔��f (1)���W�@��4���1����11���A���@��8���1���ɂ��āA �q�P�r�{�菤�W�́A�O�L�\���������Ȃ���̂ł���Ƃ���A�Y��́A����̏��̂������ē���̑傫���A����̊Ԋu�ł܂Ƃ܂�悭��̓I�ɏ�����Ă�����̂ł���A�����萶����ƔF�߂���u�T�C�t�J���o�C�v�̏̌Ă��璷�Ƃ������̂��̂ł͂Ȃ��A���݂Ȃ��̌Ă�������̂Ƃ�����B �@�܂��A�{�����W���́u�ɕ{�v�̕��������́A�u�ɑ��̖����A���ɕ{�̗��v���Ӗ������i��g���X�u�L������S�Łv�j�ƔF�߂��邪�A��ʐ��l�ɂ͓���݂�������Ƃ����̂������ł��邩��A�Y���蒼���ɏ�L�ӂ𗝉�������̂Ƃ͔F�ߓ�Ƃ���ł���B �@���Ă݂�ƁA�{�����W�́A�O�L�����悤�ɁA�O�ϋy�я̌ď�s����̐��������Ƃ��납��A�S�̂Ƃ���1�̑����\�����Ɣc���A�F���������̂Ɣ��f����̂������ł���B �@�����Ƃ���A�{�����W�́A���̍\�������ɑ������āu�T�C�t�J���o�C�v�̈�A�̏̌Ă�����̂ł����āA�P�Ɂu�J���o�C�v�̏̌Ă͐����Ȃ����̂Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@����ɑ��āA���p���WA�AB�́A���ꂼ��ʎ�(1)(2)�Ɏ������Ƃ��蕶���Ɛ}�`�Ƃ̑g�ݍ��킹���Ȃ���̂ł���Ƃ���A���̍\���������ɏ����ꂽ���������́A�u���~�v�Ƒ������ɕ\����Ă�����̂ł��邩��A�Y�������u�J���o�C�v�i���~�j�̏̌āA�ϔO������̂ł���B �@�܂��A���p���WC�́A�ʎ�(3)�Ɏ������Ƃ���̍\�����Ȃ���̂ł��邩��A���̍\�������ɑ������āA�u�J���o�C�v�i���~�j�̏̌āA�ϔO������̂ł���B �@�����ŁA�{�����W�ƈ��p�e���W���r����ƁA�܂��A�̌Ăɂ��Ă݂�ɁA�{�����W��萶����u�T�C�t�J���o�C�v�̏̌Ăƈ��p�e���W��萶����u�J���o�C�v�̏̌ẮA�O�����ɂ����āu�T�C�t�v�̉��̍��ق�L������̂ł��邩��A���̌Ă͖��Ăɒ��ʂ�������̂ł���B �@�܂��A�{�����W�́A�O�L�����悤�ɁA������Ȃ���̂ł���̂ɑ��āA���p�e���W�́A�u���~�v�̊ϔO������̂ł��邩��A�����W�͊ϔO���r���邱�Ƃ��ł��Ȃ����̂ł���B �@����ɁA�����W�́A�O�L�����\�����݂ĊO�Ϗ㖾�炩�ɋ�ʂ����鍷�ق�L������̂ł���B �@���Ă݂�ƁA�{�����W�ƈ��p�e���W�́A�̌āA�ϔO�A�O�ς̂�����̓_�ɂ��Ă���ގ��̏��W�Ƃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �q�Q�r��L�q�P�r�Ɋւ��A�����l�͈ȉ��̔@���咣����̂��̓_�ɂ��Č�������B �@(a)�{�����W���́u�ɕ{�v�́A�u���ɕ{�v�̗��̂ł���A���ɕ{�V���{�ߕӂ̍s������\��������̂ł��邩��A�n���Ƃ��Ă悭�m���A�w�菤�i�Ɏg�p����Ƃ��́A���i�̎Y�n�A�̔��n��\������ɂ������A�������i�̎��ʋ@�\���ʂ������Ȃ������ł��邩��A�{�����W�ƈ��p�e���W�͗ގ�����|�咣���A�R����A������������Ă���B �@�b��5���Ȃ�������7���؋y�ѓ���37���ɂ��A�u�ɕ{�v�̌�́A�u���ɕ{�v�̗��̂����Ӗ������ł���A�܂��A���ɕ{�V���{�ߕӂ̍s����於�̂ł��邱�Ƃ��F�߂���Ƃ��Ă��A�u�ɕ{�v�̌�́A�O�L�����Ƃ���A��ʐ��l�ɓ���݂�������ł��邱�ƁA�s����於�̂Ƃ��Ắu�ɕ{�v�����ɕ{�s�̈ꕔ�̒n��ł���A���̒n����̑��ɕ{�V���{�̖��̂��������^�����Ղ�_�ЂƂ��āA���邢�͔~�̖����Ƃ��āA��ʐ��l�ɍL���m����Ƃ��Ă��A����7���Ȃ�������9���ɂ��A�u���ɕ{�s�̑��ɕ{�V���{�v�̂悤�ɋL�ڂ���Ă��邱�Ƃ��F�߂��A�u���ɕ{�s�v�Ɓu���ɕ{�V���{�v�Ƃ����т��ĘA�z����ꍇ������Ƃ��Ă��A�u�ɕ{�v�Ɓu���ɕ{�V���{�v�Ƃ����т��āA������֘A�t����ꍇ�͏��Ȃ����̂ƍl�����邱�ƁA�u�ɕ{�v����ށA�Ƃ�킯�����̎Y�n�A�̔��n��\��������̂Ƃ��āA�悭�m���Ă���Ƃ������������o�����Ȃ����ƁA����ɁA�������n�搫�̋������i�Ƃ������������炷��ƁA�g�p����鏤�W���ɒn�����܂܂�Ă���ꍇ�A���Y�n�Ő��Y���ꂽ���i�ł��邱�Ƃ�������x�Î������邱�Ƃ͂���Ƃ��Ă��A���Y�n�����ɎY�n���̕\���Ɨ��������A�ނ���A�n���ƌ������ꂽ���̌�Ƃ���̂̂��̂Ƃ��Ĕc�����A�S�̂Ƃ��Ď������i�̎��ʕW���Ƃ��ĔF������ꍇ���������ƂȂǂ��l�����A�O�L�ɔF�肵���A�{�����W�̈�̕s�������������ƂȂǂ��l����ƁA�{�����W���́u�ɕ{�v�̕����������Y�n�A�̔��n�\���Ɨ������A�u���~�v�̕��������݂̂𒊏o���ď̌āA�ϔO���A����ɓ�������̂Ƃ݂͂��Ȃ��Ƃ���ł��邩��A�����l�̂��̓_�Ɋւ���咣�͍̗p�ł��Ȃ��B �@�܂��A�����l�̋������R����A�����Ⴊ�{���R���ƕK���������Ă���������̂Ƃ͂�����A�{�����W�ƈ��p�e���W����ގ��ł���Ƃ��錋�_�����E������̂ł͂Ȃ��B (2)���W�@��4���1����8���y�ѓ���15���ɂ��āA �@�����l�́A���p�e���W�y�ѓ��l�̗��̂ł���u���~�v�́A���v�ҊԂɍL���F������Ă���|�咣���A�b��23���Ȃ�������35�����o���Ă���̂ŁA�Y�؋��ɂ��Ă݂�ɁA�{�����W�̓o�^�o��O�ɔ��s���ꂽ�ƔF�߂���؋��́A�b��23���Ȃ�������25���i�A���A�b��25���͐����l���������R���Łu���a61�N�ɔ��s�v�Əq�ׂ�݂̂ŏ؋�����͊m�F�ł��Ȃ��B�j�y�эb��34���ł���B �@�����āA�{�����W�̓o�^�o���ɔ��s���ꂽ�b��26���Ȃ�������33���ɂ́A�����l�́u����4�N�̑n�Ɓv�Ȃ�L�ڂ��F�߂��A�����l���Â����琴���̐����A�̔������Ă������Ƃ͔F�߂���B �@�܂��A�b��34�����͂��߁A����25���A����29���ɂ��A�����l�̋Ɩ��ɌW�鏤�i�u�����v�́A�S������i�]��A�֓��M�z�ǂ̊ӕ]��ɂ����Ď�܂������Ƃ��F�߂���B �@�������Ȃ���A�{�����W�̓o�^�o��O�ɂ����āA���p�e���W���g�p�����������N�Ԕ@���Ȃ鐔�ʂ����A�̔������̂��A�܂��A�@���Ȃ�n��Ŏ��������ꂽ���S�����炩�łȂ��A�b��23���A����24���ɂ��Ă��A�����l�y�ѓ��l�̎戵���ɌW�鏤�i�́A�����鐴���̏��W�y�ё������Љ����̂̂����̈�������Ă���ɂ����Ȃ��B�݂̂Ȃ炸�A�{�����W�̓o�^�o��O�ɔ��s���ꂽ�؋����ɂ́A�����l��P�Ɂu���~�v�Ɨ��̂��ĕ\�����Ă�����̂͌�������Ȃ��B �@���Ă݂�ƁA�����l�̒�o�����؋��������Ă��ẮA���p�e���W�������l�̋Ɩ��ɌW�鏤�i�u�����v��\�����邽�߂̂��̂Ƃ��āA�܂��A�u���~�v�̕\���������l�̗��̂�\�����̂Ƃ��āA�{�����W�̓o�^�o��O�����v�ҊԂɍL���F������Ă������̂Ƃ͔F�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B �@����ɁA�O�L(1)�q�P�r�ŔF�肵���Ƃ���A�{�����W�́A�����ꂽ�����S�̂���̕s���̂��̂Ƃ��āA�c���A�F���������̂ł��邩��A���̍\�����́u���~�v�݂̂��Ɨ����F���������̂ł͂Ȃ����Ƃ����ւ��āA�{�����W�́A���l�̖��̂̒����ȗ��̂��܂ނ��̂Ƃ͂������A���A�퐿���l����������̎w�菤�i�Ɏg�p���Ă��A���i�̏o���ɂ��č����������邨����͂Ȃ����̂Ƃ݂�̂������ł���B (3)�ȏ�̂Ƃ���A�{�����W�́A���W�@��4���1����11���A����8���A����15���y�ѓ��@��8���1���Ɉᔽ���ēo�^���Ȃ��ꂽ���̂Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ�����A���@��46���1���̋K��ɂ�肻�̓o�^���Ƃ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B �@����āA���_�̂Ƃ���R������B |
| ���o���֖߂� |
�����������������@�F�@��164-0003�@�����s����擌����R-�P-�S�@�^�J�g�E�r���@2F
TEL:03-3369-0190�@FAX:03-3369-0191�@
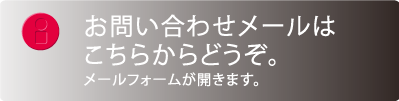
�c�Ǝ��ԁF����9:00�`17:20
����������������TOP�y�[�W�@|�@ �͂��߂��@|�@ �����ɂ����@|�@ ����Љ��@|�@ �������T�v�@| ���Ɛ��x�@|�@ �����N�@|�@ �������k �@
Copyright (c) 2014 ���������������@All Rights Reserved.

