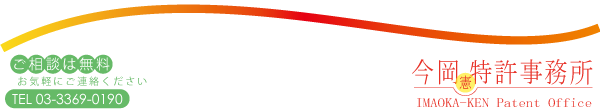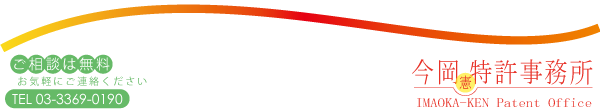| 内容 |
①損害専門家の意義
(a)特許出願が無事に審査をパスして特許査定の決定(Notice of
Allowance)に至り、特許料を支払うと、独占排他権である特許権が付与されます。
(b)特許権の行使として、特許侵害訴訟を提起する場合に、原告及び被告の間の攻防の両面において専門家(技術的専門家及び損害専門家)の意見が重要となります。
侵害論としては、原告の立場から、特許出願時の技術水準等を参酌して、被告が実施している製品(係争物)が特許発明と類似している旨を技術的専門家から意見して貰うことが有益です。他方、被告の立場からは、特許出願以前に公開された技術から特許発明が自明である(進歩性を欠く)などの意見を技術的専門家から引き出すことが、特許無効の抗弁を行う上で重要となります。
他方、損害論としては、損害額の算定に際して、合理的なロイヤリティがどの程度と評価するべきかを、知的財産の評価に関する専門家に意見して貰うことが有益です。損害額は合理的なロイヤリティの額以上でなければならないからです。こうした専門家を損害専門家と言います。

専門家の証言が証拠として裁判所に受け入れられるためには、まず事件の事象と関連性がなければならず、また専門家の意見が専門家のコミュニティにおいて一般に受け入れられているか、等の要件を課されるダウバートスタンダードに満たさなければなりません。
→ダウバートスタンダードとは
技術的専門家の証言及び損害専門家の証言のどちらも、裁判所が受け入れ可能かどうかがトライアルに先立って評価されますが、前者に比べて後者の方がより受け入れ可能性が問題となり易い傾向にあると言われています。損害専門家の意見が依拠する理論は、経済的な理論であり、こうした理論は、どれだけ精緻に考察を積み重ねても、自然法則をベースとする科学的な理論に比べて恣意的な性質が強いからです。
例えば合理的なロイヤリティは製品から得られる利益の何%が妥当という理論を、どれだけ沢山の事例から導き出したとしても、経済状況が変化したり、個々の事例の特殊性があったりなどの事情により、個別の事件にあてはめることが難しいからです。
ここでは、損害専門家の意見が、知財評価の専門家の間に広く支持された理論に依拠するものでありながら、当該理論が事案の事象に結び付かないために関連性を欠くとされた事例を紹介します。
②損害専門家の事例の内容
[事件の表示]UNILOC USA INC v. MICROSOFT
CORPORATION (632 F.3d 1292)
[事件の種類]特許侵害事件(控訴審・一部請求認容)
[発明の名称]ソフトウェア登録システム(System for software system)

[事件の経緯]
(a)UNILOC USA INC は、RICHARDSON III
FREDERICが特許出願したソフトウェア登録システムと称する発明に関して、特許権を譲り受けた。
この発明は、ソフトウェアを最初に使用する際の認証手続きとして、25語のアルファベットからなるプロダクトキーを用いることを内容とするものです。
(b)UNILOC USA
INCは、マイクロソフト社がオフィス及びウィンドウズ製品において自社の特許を侵害していると提訴しました。
(c)原審において、陪審は、損害額が5.64億ドルであるとする原告側の専門家の証言に基づいて、3,88億ドルの損害額を認めました。この賠償額は、原告(Uniloc)及び被告(Microsoft)の仮想交渉といわゆるジョージア・パシフィック・ファクターとに基づいています。
→ジョージア・パシフィック・ファクターとは
(d)証拠排除の申立て(Motion in
Limine)において、原告側の損害専門家であるGeminiは{評価プロセスで認定された評価の幅のうちの}最低額である10ドルを採用して、Product
Activationの独自の価値であると証言しました。
→証拠排除の申立(Motion in Limine)とは
そして彼は、いわゆる25%目安ルールを適用しました。
このルールでは、製品から生ずる価値の25%が特許権者に支払われ、残りの75%を被告が取るというものです。
その結果として、仮想のライセンス料を一製品当たり2.5ドルと算出しました。
Geminiは、このルールは損害を決定するための適切な方法として複数の裁判所で受け入れられた実績があるとして、このルールを採用することを正当化しました。
こうした評価を調整するためのファクターとしてジョージア・パシフィック・ファクターがあります。
彼は、ジョージア・パシフィック・ファクターの幾つかを検討し、本件ではそれらの要因を被告に有利に評価するべきと判断しました。
そしてGeminiは、2.5ドルのライセンス料を、被告の製品(Office and
Windows製品)の総数(225,978,721個)に乗じて5.64億ドルという金額を算出しました。
Geminiは、この算出額が“物凄い金額”(significant amount of
money)になることから、この金額が合理的なものであることをチェックしようとしました。
チェックの方法として、ライセンスの総数(225,978,721)に平均的な販売価格(85ドル)を乗じて、総販売額を192.8億ドルと算出し、ライセンス料が総売上額の2.9%であると計算しました。
(e)被告は、25%目安ルールに異議を唱え、Geminiの証言を排除しようとしました。
(f)地方裁判所は、信頼性及び正確さが重視される法律の領域において“目安ルール”(rule of
thumb)という概念が混乱をもたらす(perplexing)ことに気づいていましたが、結局、被告の主張を退けました。
そのルールが広く認められていたからです。
(g)また被告は、Geminiが全体市場価値ルールをチェックに使用したことに反対しました。なぜなら、プロダクトアクティベーションは需要者がオフィス及びウィンドウズ製品を欲する理由ではないからです。
(h)地方裁判所は被告の主張に同意し、損害に対する新しいトライアルを許可しました。

[裁判所の判断]
(a)米国特許法第284条は、有効な特許の損害は合理的なロイヤリティを下回るものであってはならないとしている。そして合理的なロイヤリティは、仮想交渉(特許権者及び侵害者の間にライセンス交渉が行われた状況を想定する手法)に基づいて決定されることが多い。
(b)25%目安ルールは、仮想交渉において特許製品の製造者が進んでオファーするであろう合理的なロイヤリティ率を概算するためのツールである。
(c)このルールは、Robert
Goldscheider及び他2名の著作である“知的財産の評価における25%ルールの使用について”(2002年)において提唱された。
(d)このルールにおいて、ライセンシーに利益の大半(75%)を残す理由は、他の技術又は知的財産と組み合わせるなどの開発上・オペレーション上・商業化上の実質的なリスクを負った上で利益を出すのは、ライセンシーだからである。
(e)このルールは、ある米国企業が関わった18個の商業的ライセンスに関するGoldscheiderの研究を基礎としている。これらのライセンスは、3年契約であり、更新されることを前提としている。全てのライセンシーは、ライバルとの激しい競争にさらされており、それぞれの市場のセールスの規模及び収益性において1〜2位の地位にあった。
(f)このルールの支持者によれば、25%目安ルールは、さらに様々な企業及び業種のライセンス契約・収益データに対する長年の検討を経て確認されている。Goldscheiderは、さらに全ての産業を対象とする実践的研究を発表した。それによれば、現代的なロイヤリティの平均値は22.6%であった。従って、25%ルールを交渉のスタートラインとすると良いというのである。
(g)しかしながら25%目安ルールに対しては、根強い批判があり、それは主として次の3つに分類される。
第1に、25%目安ルールは、特許と係争物との特殊な関係性が考慮されていない。例えば、売上げに対して発揮される特許の重要度、代替技術の潜在的可能性、現実社会において交渉に与え得る特許の特異性(idiosyncrasies)が考慮されていない(Gregory
K. Leonard他)。
第2に、25%目安ルールは、当事者間の特有の関係性が考慮されていない。Ted
Hagelinによれば、“このルールは単独で使用されるべきではない。何故ならライセンサー及びライセンシーによって推定されるリスクの程度が異なるからである。”
第3に、25%目安ルールは基本的に恣意的なものであるため、仮想構想の基礎とするべきではない。例えば、Roy J.
Epstein and Alan J.
Marcusによれば、“25%目安ルール或いは5%目安ルールというものは、如何に善解するにしても、特定の場合に偶発的に(only by
chance)に成立するものと解釈することが相当である。”
(h)
25%ルールの受入れ可能性(admissibility)は、連邦控訴裁判所に対して決して十分に提示されていない。それにも関わらず、連邦控訴裁判所は、25%ルールが事件の焦点になっていないケースにおいて、当該ルールを受動的に受け入れてきた。例えば当事者がそのルール自体を受け入れている場合である。
地方裁判所は、25%ルールに基づく証拠を一貫して受け入れてきたが、それは単にこのルールが広く一般に容認されているという事実に基づいているか、或いは、相手方がそのルールに反対していないことに依拠している。例えば
・25%ルールはロイヤリティの分析の適正なスタートラインとして広く受け入れられている(632 F.Supp.2d)。
・証人は、彼の専門分野において25%目安ルールを適用することが慣習的であると証言した(598 F.3d 831)。
・被告は、目安ルールが合理的なロイヤリティを計算するための最も適当な方法であるとは信じていないけれども、原告が指摘する如く、判例法はこのようなやり方をすることを示唆している(Static
Control Components, Inc. v. Lexmark Int'l, Inc.)。
・目安ルールを正当化する特別な分析は存在しないけれども、ロイヤリティを見積もるための手段としてそれが一般的に用いられている(474
F.Supp.2d 592, 606)。
少なくとも一つの裁判例において、裁判所は、25%ルールに基づく証拠を採用したが、実質的な証拠としての重みを評価することを拒絶した。何故ならば、どの専門家も他のビジネスにロイヤリティ率として慣用的に使用される利益率を示すことがなく、またGeorgia-Pacific分析に利用可能な道標(guidepost)を示すことがなかったからである。

(i) ダウバート事件(509 U.S.
589)において、最高裁は、地方裁判所に対して、全ての専門家証言が連邦証拠規則702に基づいて、科学的、技術的、或いは他の専門的な知識に関連することを確認する義務を課した。このことは、裁判官は専門家証言が科学的又は技術的な確実な根拠に基ついていることを決定するべきことを意味する。“当該事件のいかなる論点にも関係(relate)しない専門家証言は、関連性がなく(not
relevant)、従って、その裁判の役に立たない(non-helpful)。”
(j)
当裁判所は、連邦巡回裁判所の法律問題として、25%目安ルールは仮想交渉でロイヤリティ率のベースラインを決定する方法として、基本的に傷を有するツール(flawed
tool)であると決定(hold)する。従って25%目安ルールは、ダウバートスタンダード及び連邦証拠ルールに照らして受け入れ可能ではない。何故ならば、このルールは、合理的なロイヤリティとケースの事実とを結びつける根拠に欠けているからである。
(k)
今回のケースでは、Geminiの証言が25%目安ルールの使用を基礎とすることは明らかであり、しかもこのルールを、本事案の事実と関連しない、恣意的な一般的ルールとして用いている。何故なら、この目安ルールを彼の意見の基礎として適用した理由について訊かれたときに、Geminiは、“そのルールが一般的に受け入れられているからである。私は今までもそれを用いてきたし、他人がそれを用いるのも見てきた。これは広く受け入られているルールである。”と答えているからである。
さらにGeminiの陳述によれば、彼は訴訟絡みの4〜5件の交渉に関係したに過ぎず、そのうちの1件で25%ルールを勧めたに過ぎない。
Geminiは、ここでの当事者が25:75の割り当ての習慣を有していたことを証言しておらず、また、オフィス及びウィンドウズ製品に対するProduct
Activationの貢献が前記割り当てを正当化することも証言していない。
さらに彼は、彼の25%ベースラインが当該特許に基づく別のライセンス或いは比較可能な別のライセンスに基礎を置くものであるとも証言していない。
結局、Geminiが25%のロイヤリティ率を{分析の}出発点とした理由は、本件の事実と関係がなく、従って恣意的であり、信頼性がなく、非関連的である。
でない
こうしたルールの使用は、ダウバートスタンダードの項目に該当せず、陪審による損害の計算の役に立たない。

[コメント]
25%目安ルールは、“目安ルール”(rule of
thumb)という言葉が示すように、ロイヤリティ率を決定するためのスタートラインを提供するための便利なツールとして提案されたものです。もともとは実在の米国企業との間で締結された18個のライセンスの研究をベースとして、そこに様々な修正を加えて25%という数字が導き出されたものです。
このルールの支持者によれば、ライセンス製品から生み出される利益の大半(75%)をライセンシーに与える理由は、特許発明を他の技術と組み合わせる等の開発上のリスクやオペレーション上のリスク、商業化のリスクを負いながら、利益を出すための努力をしなければなららないのは、ライセンシーだからであるということです。
しかしながら、この考察は、ロイヤリティの算定のスタートラインが25%より低い数字であってはならないという根拠とはなりません。
25%目安ルールは、25%程度のロイヤリティであれば、ライセンシーは通常は喜んで支払うであろうという想定の上に成り立っていました。
しかしながら、この推定は侵害対象である特許が侵害品(係争物)にとってどの程度重要なのかという考察に欠けているなどの根強い批判がありました。確かに単一の特許技術を導入することにより、市場のシェアを独占できるのであれば、ライセンシーは25%程度のロイヤリティを喜んで支払うかもしれません。しかし、近年では非常に多数の特許によって一つの製品が成り立っている場合が多々あるのです。
こうした批判が無視できない程に顕著になったのが本件事例です。およそ消費者のうちで、オフィス及びウィンドウズ製品を購入する際に、使用時の登録システムの使い勝手が良いので当該商品の購入を選択したという人は殆どいないと推定されます。そうであればマイクロソフトが、特許権者のソフトウェア登録システムを導入するために、この裁判で概算された巨額のロイヤリティを支払うであろうとは到底思えません。
損害専門家の意見が依拠する理論は、たまたま他に有力なルールがなかったために、世間に支持されていただけであり、一般論としては、決してそれ自体信頼に足るものではありませんでした。それゆえに連邦控訴裁判所は、証拠としての受け入れ可能性(証拠の適格性)を否定したのです。
|