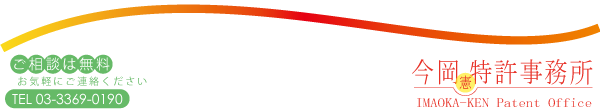
|
●平成24年(ワ)第2689号(相当の対価請求事件・請求認容)
職務発明/特許出願/実施料率方式/安定材付きベタ基礎工法
| [事件の概要] |
| ①事件の経緯 (a)本件は、被告乙の従業員であった原告甲が、被告に在籍中、被告の業務範囲に属し、かつ原告の職務に属する「安定材付きベタ基礎工法」に関する発明(本件発明1)及び「ベタ基礎の配筋方法」に関する発明(本件発明2)をし、平成14年7月頃、これらの特許を受ける権利を被告に承継させたとして、被告に対し、平成16年改正前の特許法(以下、単に「法」という。)35条3項に基づく相当の対価として、本件発明1につき、2億9031万8441円のうちの2700万円、本件発明2につき、798万7213円のうちの300万円及びこれらに対する遅延損害金の支払を求める事案です。 (b)事件の当事者・関係者は次の通りです。 (イ)被告は、丁を親会社とする、建築・土木工事の設計施工・建築資材の製造・販売等を業とする株式会社である。 (ロ)原告甲及び戊は被告の従業員であり、丙は、被告の元代表者である。 (ハ)丙、丁、被告の三者の間には、本件特許に先行する技術に関してライセンス契約が締結されていました。その概要は次の通りです。 平成10年7月31日、被告、丁及び丙は、「MS基礎工法に関する覚書」を作成し、丙が、被告及び丁に対して、丙各特許の無償の通常実施権(第三者に再実施させる権限がないもの)を許諾し、 平成11年12月18日、被告、丁及び丙は、覚書の内容を変更して、丙が被告及び丁に対し、丙各特許の再実施権付き通常実施権を無償で許諾するとともに、被告又は丁が丙各特許を第三者に再実施させた場合は、原則として1棟につき1万円を丙に支払う旨を合意し(→再実施権付き通常実施権とは)、 平成10年8月12日、丙と丁は、丁が丙から丙各特許の通常実施権の許諾を無償で受ける旨の通常実施権許諾証書を作成し、 平成10年9月1日、被告と丁は、丁が有する丙各特許の通常実施権をさらに被告に実施許諾し、被告が丙各特許に係る工法を実施して丁に販売した場合は、その販売棟数1棟当たり4万円を丁に支払うという内容の実施許諾契約書を作成した。 (c)本件特許出願の経緯は次の通りです。 (イ)被告は、戊及び原告を発明者とする「安定材付きベタ基礎工法」と称する発明について、平成14年7月30日に特許出願を行い、平成17年8月5日に特許権の設定登録を受けました(第3706091号・本件発明1) 特許出願人の発明は、もともと後述の如く安定材造成用の溝が逆台形(上方に向けて次第に横断面が大きくなる)ことなどを特徴とするものでしたが、進歩性の欠如などを理由とする拒絶理由通知を受け、これに対して“基礎の立ち上がり部分の下部をベタ基礎下面より下方へ突出させ、安定材の側面に係合する”などの限定を加えて特許になりました。 (ロ)さらに被告は、戊及び原告を発明者とする「ベタ基礎の配筋方法」と称する発明について、平成14年8月21日に特許出願を行い、平成17年1月21日に特許権の設定登録を受けました(第3639567号・本件発明2)  (d)被告の事業全体の経緯は、次の通りです。 [第1期] ・平成5年より、被告は、ベタ基礎工法にさらに安定材を設けた基礎補強工法(地盤に設けた断面形状が矩形型で格子状の溝内においてソイルセメント等で土壌を置換して安定材を形成し、同安定材を設けた地盤上にベタ基礎を設ける工法)を提案し、「MS基礎」の名称でその販売を開始した。 なお、この当時の被告の営業形態は、親会社である丁が請け負った建物建築に関して、同社から注文を受けて安定材を含むベタ基礎工事の全工程を実施し、これを同社に販売するということ(以下「内販」という)である。 [第2期] ・平成10年、被告は、丙から第1期のMS基礎を改良した工法につき特許(丙各特許)を取得した旨の申入れを受け、その結果として、被告及び丁が丙から、無償で丙各特許の通常実施権の許諾を受けることとなった。 この丙各特許に係る安定材付きベタ基礎工法は、地盤に溝を掘った上で、あらかじめ鉄筋を組み込んで配筋した安定材造成用の型枠組立体を溝内に落とし込む工法(丙特許1)と、安定材の上面に小溝を設け、そこにリブ用配筋を設けて、基礎配筋と安定材とを一体化する工法(丙特許2)である。 被告は、従前施工していた工法が丙各特許に係る工法であると誤解していたため、その後も第1期のMS基礎を(丙各特許を利用するものとして)そのまま施工していた。 ・同年8月12日、丁は、丙との間で、丁が丙から丙各特許の通常実施権を無償で許諾を受ける旨の契約を締結し、被告は、同年9月1日、丁との間で、丁から丙各特許の再実施許諾を受ける旨の契約を締結した。 被告は、同年7月31日付けの覚書に基づいて丙各特許の通常実施権を有していたが、丁との再実施許諾に係る契約に基づいて被告が、親会社である丁から基礎工事を下請けして施工した場合に、同社に対して1棟当たり4万円の実施料を支払うこととなった。 ・平成11年12月18日、被告は、丙との間で覚書を交わして、被告及び丁が丙各特許を第三者に再実施許諾することができることとした。親会社の丁以外にもMS基礎の販路を拡げることを希望したためである。 ・平成13年頃から、被告は、従前の内販の形態に加えて、丁以外の業者に対して下記の営業形態(「外販」という)を開始した。 (イ)被告が分譲住宅ビルダーからMS基礎のうち安定材部分のみを受注して施工し、ベタ基礎部分は分譲住宅ビルダーが施工すること。 (ロ)被告は、分譲住宅ビルダーに対し、ベタ基礎部分を施工する際の材料としてメッシュ鉄筋を販売すること。 (ハ)地盤改良業者に対して、丙各特許に関する実施許諾・技術ノウハウを提供して、同業者にMS基礎に係る安定材を施工させること。 その際、被告は、同業者との間で丙各特許に関する実施許諾契約を締結して、業者からその実施料を収受していた。被告が第三者に丙各特許の再実施を許諾した場合は、平成11年12月18日付けの丙との覚書に基づき、被告が丙に対して、その実施料を支払っていた。 ・平成12年末頃、被告は、実際に施工していたMS基礎について、丙各特許と実際のMS基礎との間に齟齬があるとの指摘を受けて、社外弁理士に意見を求め、その結果、実際に施工している工法が丙各特許と異なることを認識した。 [第3期] ・被告は、丙各特許に代わる新たな特許権の取得の検討を開始し、その結果、平成14年7月30日に本件特許1の発明を、同年8月21日に本件特許2の発明をそれぞれ特許出願し、本件特許2は平成17年1月21日に、本件特許1は同年8月5日に、それぞれ登録された。 被告は、遅くとも平成18年7月26日には、自己が施工するMS基礎において、安定材の断面形状を逆台形型とし、ベタ基礎の立ち上がり部分の下部に下方への突出を設けて、本件発明1を実施していた(被告による本件発明1の実施の開始時期については当事者間に争いがある。)。 被告は、内販においては、自己が施工するMS基礎工事でメッシュ鉄筋を使用し、外販においては、ベタ基礎を施工する他の業者に対してメッシュ鉄筋を販売していたが、平成20年9月26日以降は、MS基礎におけるメッシュ鉄筋の使用を原則として中止し、鋼材単体(いわゆる生材)を組み立てて配筋をすることとした(なお、被告がメッシュ鉄筋の販売を全面的に中止したかについては、後記のとおり当事者間に争いがある。)。 [第4期] 被告は、平成23年4月25日、MS基礎について、財団法人日本建築総合試験所から建築技術性能証明書を取得し、この建築技術性能証明書を取得した新たな工法を「MS工法」と名付け、被告社内では、平成23年6月28日にその仕様図面を作成して従来の仕様を変更し、親会社である丁に対して、同年7月2日にこの仕様変更について書面で通知した。なお、このMS工法については、性能証明の対象は安定材の部分のみであり、ベタ基礎の形状やベタ基礎と安定材との関連性などは対象とされていなかった。 平成22年12月6日付けの内容証明郵便により、原告は、被告に対し、職務発明対価を請求した。 裁判所において対価の請求が認められたのは特許発明1のみであるため、以下、これに関して解説します。  ②本件特許の請求の範囲 (a)特許発明1 小規模住宅建設予定地が軟弱地盤であるときに該軟弱地盤である基礎構築部分に平面が格子状の地盤安定材を打ち、地盤の不同沈下を抑止する安定材付きベタ基礎工法であって、 前記基礎構築部分に地盤の強弱により幅及び深さを調整した安定材造成用の溝を、溝底面より上方に向けて次第に横断面が大きくなるように掘削するとともに、ソイルセメントを含む改良土質と置換し、 該土質置換部分をランマー等で転圧して土質強度と靱性をもたせた改良土質による安定材を造った後、 ベタ基礎部分にコンクリートを打設して安定材とベタ基礎を一体化し、 その際に基礎の立ち上がり部の下部をベタ基礎の下面より下方に突出させ、 この突出した基礎の立ち上がり部の下部の側面と安定材の上部の側面が係合するようにする ことを特徴とする安定材付きベタ基礎工法。 (本件発明1) 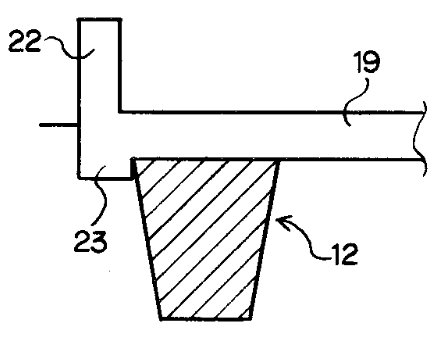 ③本件特許の発明の概要 ・この発明は、たとえば小規模の個人住宅建設予定地が軟弱地盤であるときに該軟弱地盤である基礎構築部分の近くに地盤安定材を打ち、地盤の不同沈下を抑止する安定材付きべタ基礎工法に関するものである(段落0001)。 ・従来の安定材は、断面がいわゆる縦長の長方形状を呈し、その底面と上面の横断面が等しくなるように造られているため、建物影響荷重など上方から負荷がかかった場合、該負荷をその側面で受け止めることが難しく、負荷を側面に分散できないという問題があった。…本発明は前記のような従来の問題点を解決し、安定材に上方から負荷がかかった場合でも該負荷を側面で受け止めて地盤への建物影響荷重を分散、軽減させてバランスと安定効果の向上を図ることができ、より不同沈下に強い安定材付きベタ基礎工法を提供することを目的とする(段落0003~0004)。 ・本発明の構成により、安定材とベタ基礎部分とで囲まれた土を剛体にしてベタ基礎の剛性を高めることができるだけでなく、上方から負荷がかかった場合でもその負荷を安定材の側面で受け止めて地盤への建物影響荷重を分散、軽減させてバランスと安定効果の向上を図ることができ、不同沈下に対してより強いものとなる(段落0024) ・地震の横揺れに対して基礎の立ち上がり部の下部の側面が安定材の上部の側面によって支持されることとなるため、強度が高くなり、ベタ基礎全体としても安定したものとなる(段落0021)。 ・安定材は残土の発生がなく、無廃土工法といえる上、安定材が小型掘削機にて簡単に現場構築でき、大型重機を必要としない等、施工、コスト面で他の工法と比較して優れており、また、通常の基礎工事機械で施工でき、搬入、騒音等の諸問題が解決できる(段落0023)。 (c)本件の特許出願の審査の経緯として次の事情があります。 乙1文献記載の先行技術には、土を掘削すると同時に土とソイルセメントを混合して土質を置換すること及び安定材とベタ基礎とで囲まれた土を剛体にすることによって、不同沈下を防止することが開示されており(乙1文献の段落【0011】及び【0017】)、 また、乙2文献記載の先行技術には、安定材の断面形状を上方に向けて次第に大きくすることによって、圧入のために及ぼされる押圧力が傾きのある面を通じてその周辺地盤を押し広げるように作用し、その結果、柱状体を圧入する場合よりも、軟弱地盤が効果的に締め固められることが開示されている(乙2文献の段落【0025】)。 そして、本件特許1は、その特許出願後、乙1ないし3文献を引用例として拒絶査定がされ、これに対して、被告が、特許請求の範囲請求項1に、基礎の立ち上がり部の下部をベタ基礎の下面より下方に突出させて、この突出した基礎の立ち上がり部の下部の側面と安定材の上部の側面が係合するようにするとの構成を付加する補正を行った結果、特許査定がされたものであることが認められるから、乙1ないし乙3文献にも記載された技術内容については、本件発明1に固有のものではないということができる。  ⑤本件の争点 (1) 本件発明1について ア 内販における独占の利益 イ 外販における独占の利益 ウ 使用者の貢献度及び共同発明者間の寄与割合 エ 相当対価の額 (以下省略) ⑥争点に対する原告及び被告の主張の要旨。 (a)被告の内販における特許発明1の実施期間 {原告の主張}平成17年10月18日から平成23年6月30日までである。 {被告の主張}平成18年7月26日から平成23年6月28日までである (b)売上超過額の割合(→超過売上額とは) {原告の主張}の諸事情を総合すれば、本件特許1の価値は非常に高く、自己実施分の超過売上高の割合は75%であり、少なくとも40%を下ることはあり得ない。 ∵型枠が不要で一工程で簡便に施工できるため低コストである上に、壁面が斜行しているために強度的にも有利である点で、従来技術より優れている。 {被告の主張} 被告が、本件発明1を排他的に実施することによって、通常実施権分の売上げを超える超過売上げを得たなどということはできず、超過売上高を認める余地はないから、被告の独占の利益はゼロである。 ∵被告は、親会社である丁が戸建建物建築を請け負った際に、子会社としてその基礎工事部分を受注していたにすぎない。すなわち、被告が行ったMS基礎は、専ら丁がその営業力によって建物建築と基礎工事を一体的に受注したことによるものであって、本件特許1による排他的効力の効果ではない。また、被告は、本件特許1についてライセンス許諾を求められたことはなく、ライセンスを付与したこともない。この事実は、本件発明1が第三者に対して排他的効果を有するものではなかったことを示している。 (c)仮想実施料率(→仮想実施料率とは) {原告の主張}内販分における本件特許1の仮想実施料率は2.5%を下回ることはない。 ∵被告は本件特許1が開発される以前、丙から丙各特許の実施許諾を受け、その実施料として1棟当たり4万円を支払っていたところ、その実施料率は2.5%であったといえる。本件発明1は丙各特許より優れているから、実施料率がそれより低くなることはない。 {被告の主張}建築技術分野における平均実施料率が3%程度であることを考慮したとしても、本件特許1の仮想実施料率は、せいぜい1%である。 ∵本件特許1は、もともと被告が平成5年頃より行っていたMS基礎の基本技術の応用技術にすぎず、それ単独において優越した技術的意義を備えるものではない。そして本件特許1の技術的意義は、MS基礎に係る工法全体の中でみれば、ベタ基礎の立ち上がり部の下部と安定材の係合という、極めて限定的な箇所に関する技術にすぎない。また、本件発明1の実施によって被告の市場占有率が増加したこともライセンスを付与したこともない。 (d)外販における独占の利益 {原告の主張}被告は、外販においては、被告が分譲住宅ビルダーから注文を受けて、MS基礎のうち安定材(改良材)の部分を自ら施工した上で、同ビルダーがMS基礎のうちベタ基礎を施工することについて、同ビルダーから実施料を収受していた。 {被告の主張}外販においては、分譲住宅ビルダーは、被告に対して安定材の施工のみを発注し、ベタ基礎部分は自己で設計したものを施工していたのであって、被告は、そのベタ基礎施工には何ら関与していないから、分譲住宅ビルダーがどのようなベタ基礎を設計し施工しているかは分からない。外販において、被告には、主観的に他者と共同して本件発明1を実施する意思などなく、客観的にも共同して本件特許発明1を実施していたことはない。  (e)使用者の貢献度 {原告の主張}使用者である被告の貢献度が80%を超えることはない。 ∵被告は、平成11年12月頃まで、MS基礎について丙各特許の特許番号を記載して営業を行っていたが、実際に施工していた工法が丙各特許の特許請求の範囲に入らない恐れが出てきたため、新たな技術を開発して特許出願することが必要となったのであり、その開発の中心となった原告以外に当時被告には地盤改良の専門家が在籍しておらず、原告の発明に対する貢献度は非常に高い。 {被告の主張}本件特許1に関する発明者の貢献度が非常に高いとはいえないことは明らかであり、被告の貢献度が90%を下回ることはない。 ∵本件各発明の特許出願は、当時の被告の代表者であった戊が主導したものであった。すなわち、平成14年当時、それまでの丙各特許を脱却して新たな特許出願を余儀なくされた被告が、会社の営業方針として実行したものである。 |
| [裁判所の判断] |
|
①裁判所は、“相当の対価”の算定の基礎となる「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」に関して次のように解釈しました。 (a)使用者等は、職務発明について特許を受ける権利等を承継しない場合でも、当該特許権について無償の通常実施権を取得すること(法35条1項)からすれば、同条4項に規定する「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」とは、使用者等が当該発明を実施することによって得られる利益の全体をいうものではなく、使用者等が被用者から特許を受ける権利を承継し、当該特許発明を排他的かつ独占的に実施し得る地位を得、その結果、実施許諾を得ていない競業他社に対する禁止権を行使し得ることによって得られる利益の額、いわゆる「独占の利益」の額をいうものと解される。(→独占の利益とは) (b)そして、職務発明に係る特許発明の実施を許諾した場合の実施料収入は、当該特許発明の排他権の結果得られた利益と評価し得るから、そのような実施料収入は、原則として、上記「独占の利益」に該当するというべきである。 (c)また、特許権者が他社に実施許諾をせずに、職務発明の対象となる特許発明を自ら実施している場合における「独占の利益」は、他社に対して職務発明の実施を禁止できることにより、他社に実施許諾していた場合に予想される売上高と比較して、これを上回る売上高(超過売上高)を得たことに基づく利益(超過利益)をいうものと解される。 (d)ここで超過売上高とは、仮に第三者に実施許諾された事態を想定した場合に使用者が得たであろう仮想の売上高と現実に使用者が得た売上高とを比較して算出された差額に相当するものというべきであるが、具体的には、職務発明対象特許の価値、使用者等が採用しているライセンスポリシー、ライセンス契約の有無、市場占有率、市場における代替技術の存在等の諸般の事情を考慮して定められる独占的地位に起因する一定の割合(超過売上げの割合)を乗じて算出すべきである。 (e)そして、超過利益は、上記方法により算出された超過売上高に、仮想実施料率を乗じて算出するのが相当である。  ②裁判所は、内販による特許発明1の実施時期に関して次のように判断しました。 (a)裁判所は、被告の内販における本件発明1の実施期間が平成17年10月18日から平成23年6月30日まで(原告が主張する期間)と認める。 (a)被告作成に係る平成17年10月18日付けMS基礎伏図の「A.断面」の図では、安定材の断面形状が逆台形型になっているものについて、ベタ基礎の立ち上がり部の下部が下方に突出しており、しかも、その突出部分の内側の側面が安定材の外側の側面と斜めに面接触していること、以上の事実が認められる。 (b)被告は、本件特許1の請求項1の「係合」(構成要件Ⅰf)とは、「両者が引っかかるように合わさって止まっている状態」を意味するから、上記の図のようにベタ基礎の立ち上がり部の下部の突出部分と安定材が面接触しているようなものは「係合」に当たらないと主張する。 (c)しかし、「係合」とは、一般的に、二つのものが「係わり合うこと」を意味する用語と解されるところ、本件特許1の請求項1及びその明細書等の記載に照らしても、「係合」の意味を、被告がいうように「両者がひっかかるように合わさって止まっている状態」と限定的に解釈すべき根拠は見いだせない。 また、ベタ基礎の立ち上がり部の下部の突出部分と安定材との係合の技術的意義は、「地震の横揺れに対して基礎の立ち上がり部の下部の側面が安定材の上部の側面によって支持されることとなるため、強度が高くなり、ベタ基礎全体としても安定したものになる」こと(本件特許1明細書等・段落【0021】)にあるところ、立ち上がり部の下部の突出部分と安定材が面接触しているような場合であっても同様の作用効果が得られると考えられることからすれば、そのような場合を「係合」に当たらないと解することはできない。 (d)従って被告の主張は採用できない。 (e)前記実施期間における被告の内販売上高は、以下の各期間の合計である72億4501万5433円と認められる。 ③裁判所は、売上超過高の割合に関して次のように判断しました。 (a)特許発明1の技術的意義は、明細書の記載によれば、“ベタ基礎に付加することで一定の地盤補強効果を得ることを目的として採用される工法”であり、被告が実践するMS基礎の後継技術として採用されたものである。 (b)MS基礎の代替技術となり得る技術として、コロンブス工法、スーパージオ工法及びジオクロスが存在した。これらは、その施工に大型重機が不要であり、小規模現場でも使用できたことが認められる。 なお原告はMS基礎がコストの点で最も優れると主張するが、たとえその通りであったとしても、技術全体の優劣(地盤補強効果など)については何ら具体的に主張立証されておらず、MS基礎が他の代替技術と比較して格別に顕著な技術的優位性を持っていたとまでは認められないから、採用できない。 (c)被告のライセンスポリシーに関しては、被告が本件特許1を特定の企業にのみ実施許諾をする方針(限定的ライセンスポリシー)を採用していたと認められない。 かえって、被告は、MS基礎について、内販では安定材付きベタ基礎全体を自社で施工して丁に販売する一方で、外販においては、その安定材を自社で施工した上で、分譲住宅ビルダーにベタ基礎部分を施工させていたのであり、これらの事情から被告は、MS基礎の販売に当たっては、MS基礎の全体の実施を第三者に許諾していたことはないものの、工事全体を自社で実施することにこだわらずに、外販において、分譲住宅ビルダーにMS基礎のうちベタ基礎部分を施工させていたことが認められる。 (d)市場占有率から見た特許発明1の排他的効力の程度 (イ)証拠によれば、平成17年下期から平成23年上期までの間における、被告によるMS基礎の販売棟数(内販及び外販)の全国着工戸数に占める割合は、約0.14ないし約0.32%とごくわずかなものであったが、被告が丁から受注した地盤補強工事の中では、MS基礎が約54ないし87%と高い割合を占めていたことが認められるところ、前記の通り、MS基礎が、地盤補強効果を得るためにベタ基礎に付加して用いられるものであることからすれば、全国着工戸数に占めるMS基礎の割合が僅少であることを以て、地盤補強工法の市場における本件特許1の排他的効力がなかったということはできない。 (ロ)他方、被告が丁の子会社であることを考慮すれば、被告が丁に対してMS基礎を販売できたのは、まず親会社である丁が戸建建物建築を受注したからであって、丁に対するMS基礎の販売数が多いことや、その割合が高いことをもって、直ちに市場における本件特許1の排他的効力が強かったと認めることはできない。 (e)以上のような本件発明1の技術的意義、代替技術の有無とその技術内容、被告のライセンスポリシー及び市場占有率その他の事情を総合考慮すれば、被告が、本件発明1を自社実施して得ることができた売上げのうち、本件特許1に係る通常実施権の行使を超えて、その禁止権の行使によって被告が得ることができた超過売上高の割合は、30%と認めるのが相当である。  ④裁判所は、仮想実施料率に関して次のように判断しました。 (a)原告は、本件特許1に先立つ丙各特許について被告が内販1棟当たり4万円の実施料を支払っており、これが内販1棟当たりの平均売上高160万円に対して、2.5%に当たるから、本件特許1についても仮想実施料率が2.5%を下らないと主張する。 確かに、前記第2、2(4)イ及びウのとおり、被告と丁は、平成10年9月1日に丙各特許に係る実施許諾契約を締結し、丁が被告に丙各特許の再実施を許諾することの対価として、被告が丁に対して1棟当たり4万円を支払うことが合意されたと認められるが、一方で、被告は、その直前の同年7月31日に、丙から無償の通常実施権を許諾されていたのであるから、本来であれば、被告が4万円の対価を払って丁から丙各特許の再実施許諾を受ける必要はなかったはずであるにもかかわらず、丁と被告との間で上記のような再実施許諾とこれに基づく丁に対する対価の合意がされたのは、親会社である丁と子会社である被告との間に何らかの経営上又は営業上の事情が介在したためであると推認される。 従って被告と丁との間の上記実施許諾契約で合意された1棟当たり4万円との金額については、これが丙各特許に関する純粋な実施料の趣旨であったと認めるのは相当でない。 (b)他方、前記のとおり、丙と被告及び丁との間では、平成11年12月18日、被告及び丁が、丙から受けた通常実施権を第三者に再実施させた場合、原則として1棟につき1万円を丙に支払うことが合意されているところ、これは、当時、丙各特許の実施品と考えられていたMS基礎の販路拡大を希望した被告が、丙に丙各特許の再実施についての承諾を求めたことにより、被告と丙との間で合意されたものであり、この許諾に基づいて被告が実際に第三者に再実施をしていたことが認められる。 もっとも、弁論の全趣旨によれば、丙は被告の前の代表者であって、純然たる第三者ではなく、しかも、特に丙特許2は当時被告社内で開発されていた技術を丙が抜け駆け的に出願したものであったとの事情もうかがわれることなどに鑑みれば、上記1万円の額(内販1棟当たりの平均売上高を160万円とすると、その0.625%に相当)が直ちに丙各特許についての適正な実施料額であったということもできない。 (ハ)これらの事情に加えて、証拠によれば、建設技術分野における実施料率(平成4年度ないし平成10年度の総件数累計)の最頻値及び中央値が3%であり、平均値が3.5%とされていることや、上記の本件発明1が有する技術的意義などを総合して考慮すれば、本件特許1に係る仮想実施料率は2%と認めるのが相当である。 ⑤以上のことから、裁判所は、内販における独占の利益の額を次のように計算しました。 売上高72億4501万5433円×超過売上高の割合0.3×仮想実施料率0.02=4347万0093円 ⑥裁判所は、外販における独占の利益に関して次のように判断しました。 分譲住宅ビルダーが被告から安定材の引渡しを受け、その上にベタ基礎を施工して、本件発明1の構成を有する安定材付きベタ基礎を完成させる行為は、本件発明1の実施行為に当たると認めるのが相当であるから、被告がこれを承知した上で、分譲住宅ビルダーからMS基礎の発注を受け、その代金を受領していたことは、被告が分譲住宅ビルダーに対して、ベタ基礎部分を施工して本件発明1を実施することについての許諾を与えていたものと評価することができる。 なお、仮に分譲住宅ビルダーが、何らかの事情で、ベタ基礎の立ち上がり部の下部に突出部分を設けなかったり、その突出部分と安定材との係合を設けなかったりして、完成した安定材付きベタ基礎に本件発明1の構成の全てが含まれていないことがあったとしても、前記「独占の利益」の意義に鑑みれば被告が分譲住宅ビルダーに対して実施許諾を与えることによってその対価を得ていたのであれば、分譲住宅ビルダーが現実にこれを実施していたか否かにかかわらず、その対価の額は、被告が本件特許1に係る独占的地位に基づいて得た利益であると解することができる。  ⑥裁判所は、使用者の貢献に関して次のように判断しました。 本件発明1は、 ・そもそも被告の営業戦略上、丙各特許に代わる特許の取得が必須であったことを契機としてその開発が進められたこと、 ・本件特許1は、その出願後、拒絶理由通知及び拒絶査定を受ける中で補正を繰り返し、拒絶査定に対する不服審判を提起して、社外弁理士との協議を重ねる等の経過を経てようやく特許登録に至ったものであること、 ・通常のベタ基礎に格子状の安定材を設けて地盤補強効果を得るとのMS基礎の基本的な技術は、平成5年から被告が培ってきたものであり、被告はこの技術を中心に営業を展開し、本件特許1の特許登録以前にも大きな販売実績を得ていたこと、 ・本件発明1は、原告が従前の丙各特許に類似した内容とすることを心掛けて開発したものであり、実際に特許登録された請求項の内容も、従前被告が施工してきたMS基礎の形態を取り入れたものであったこと、 ・被告の内販売上げは、全て被告の親会社である丁からの発注によるものであり、そこには本件発明1が有する技術的優位性以外の被告と丁との繋がりによる経営上又は営業上の要因が相当程度寄与していたと考えられること などの事情を総合考慮すると、本件発明1に基づいて被告が得た独占の利益については、本件発明1の技術内容以外の被告の貢献による部分が相当に大きい。 そうすると、原告が本件発明1の承継に基づいて被告から受けるべき相当の対価の算定に当たり考慮すべき被告の貢献度は、95%とするのが相当である。 (以下省略) |
| [コメント] |
|
①本件は、職務発明に関して特許を受ける権利(特許出願をする権利)を使用者に予約承継させた従業者が、相当の対価(現行法でいう相当の利益)の支払いを求めたものです。 相当の対価の算定に際して考慮するべき「発明について使用者等が受けるべき利益」は、職務発明の特許権により使用者等が享受する利益のうちもともと使用者等に保証されている法定通常実施権の利益を除いた、“独占の利益”と解釈されており、具体的には、第三者に通常実施権が許諾されていると仮定して、この仮定の元で特許対象から生ずる売上額(超過売上額)から得られる利益(超過利益)として算出します。算定方法としては、超過売上額に利益率を乗ずる利益率方式と、超過売上額に仮想実施料率を乗ずる実施料率方式とがありますが、従業者等が利益率を立証することは難しいために、裁判では実施料率方式が採用されることが多いです。こうして算出した超過利益のうち売上に使用者等が貢献した割合に対応する部分を除外して、相当の利益が間算出されます。 [相当の利益]=[超過利益]×[1−(使用者等の貢献の割合)] ②本事例では、職務発明の技術的意義(既存の事業に使用されていた先行技術に代わるべき後継技術であったこと)や同種の技術的効果(大型重機を導入せずに小さい現場に適用できる)を発揮できる代替技術が存在したことから、超過売上額は小さく、また仮想実施料率は低く見積もられることになりました。 また本件では、発明品の発注者と受注者とが親会社と子会社という特別な関係にあり、売上につながって要因として、発明自体の優秀さよりも、親会社と子会社という関係性が大きいと判断されたため、売上に対する使用者等の貢献の割合が通常よりも大きくなりました。 ③独占の利益に関しては、特許発明全体の実施ではなくとも、特許発明の一部(これによって特許出願の実体審査で進歩性を認められた特徴部分)であっても、独占の利益に該当し得るという判断が示されています。 ④仮想実施料率を設定するに際して、業界の実施料率のデータなどの標準的な要素に代えて、特許発明に関して第三者との間で締結された特許ライセンスの実施料率が仮想実施料率の算定に使われることは、しばしばあります(→仮想実施料率のケーススタディ1)。 しかしながら、本事案では次の事情から判断材料とはなりせんでした。 ・本件発明に先行する他の発明について実施許諾された実施料率を引用していること。 ・先行発明の特許ライセンスの実施料率は、親会社と子会社との間で締結され、親会社から仕事を発注する代わりに実施料を徴取するという取引形態であり、普通の実施料率とは異なること |
| [特記事項] |
| 戻る |
今岡憲特許事務所 : 〒164-0003 東京都中野区東中野3-1-4 タカトウビル 2F
TEL:03-3369-0190 FAX:03-3369-0191
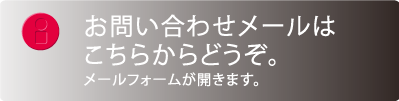
営業時間:平日9:00~17:20
今岡憲特許事務所TOPページ | はじめに | 特許について | 判例紹介 | 事務所概要 | 減免制度 | リンク | 無料相談
Copyright (c) 2014 今岡特許事務所 All Rights Reserved.

