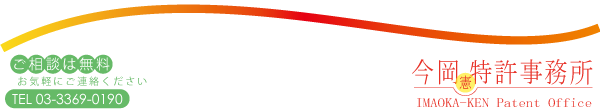
|
●MARKMAN v. WESTVIEW INSTRUMENTS, INC. No.95-26
特許クレームの解釈/特許出願/インベントリー
| [事件の概要] |
|
(a)Markmanは、“インベントリーの管理及びレポートのシステム”と称する発明について特許出願を行って、特許権を取得しました。 この特許発明は、ドライクリーニングのプロセスに亘って衣服(clothing)を追跡するシステムに関するものであり、具体的には、キーボード及びデータプロセッサを用いて、光学検知器で読み取り可能なバーコードを含む取引記録を生成するものです。 (b)この特許のクレーム、特許権者の範囲を定義する特許書類の一部、によれば、マークマンの装置は次のことができるとされていました。 ・全体としてのインベントリー(an inventory total)を維持すること。 ・前記インベントリーに対する偽り(spurious)の追加を検知して場所を特定(localize)すること。 (b)Markmanは、Westviewの製品が彼の特許権を侵害しているとして提訴しました。 Westviewの製品もキーボード及びプロセッサを使用するものであり、光学的検知器で読み取り可能なバーコード付きのチケットに、ドライクリーニングの代金をリストとして出力することができました。 (c)地方裁判所において、陪審は、前記クレーム中の文言についての専門家証人の証言を聴いた後にWestviewの製品の製品がMarkmanの特許を侵害していると認定しました。 しかしながら、地方裁判所の裁判官は、Westviewに有利な評決を出すように指示しました。その理由は、Westviewの装置は、特許クレームで規定されているようにインベントリーを追跡することができないからです。 (d)連邦巡回裁判所は、原判決を支持しました。その理由は、クレームを解すること (interpretation)は裁判所の排他的な職分(province)であり、そのように結論することは憲法修正第7条(the Seventh Amendment)にも合致するということです。 [特許発明/特許出願に係る発明の内容] {発明の目的} ・ドライクリーニングの個人向け店舗のニーズに応える自動的なインベントリー管理システムを提供すること。 ・ドライクリーニングの店舗において自動的にスキャンされ、装置によって生成されるバーコード・ラベルを提供すること。 {発明の構成} インベントリー(inventory)を管理しかつレポートするためのシステムであって、 接客係(attendant)によって手動で操作され、かつ一連の(sequential)取引に関する物品(article)を符号化(encode)するためのスイッチを有し、当該情報を前記物品の同一性及び物品の説明に関するものとしたデータ入力装置と、 前記情報を記憶するメモリー及び全体としての在庫を維持する手段を有し、かつ前記一連の取引を特別な一連の証印(indicium)に関連付ける(associated with)とともに全体として在庫及び前記一連の取引について少なくとも一つのレポートを生成(generate)する手段を有し、前記特殊な一連の証印と前記製品の説明とが相互に一致するように構成したデータプロセッサと、 前記データプロセッサで制御されており、前記一連の取引に関連する証印の書面による記録を生成するように操作することができ、当該記録は、適宜間隔を開けた光学的に検知可能なバーコードを含み、このバーコードは前記取引が一致した場合にのみ印刷され、前記書面による記録の少なくとも一部が物品に付着されるように構成されたドットプリンタと、 前記データプロセッサと連結され、かつ所定の場所を通過する全ての物品を検知するために操作される光学的スキャナと、 を具備し、前記在庫に対する偽り(spurious)の追加を検知することが可能な、 インベントリーの管理及びレポートのシステム。 ※インベントリー…商品や財産の目録、あるいは商品な財産の目録を作成する在庫調査や棚卸しを意味する用語です(ウィキペデイア)。 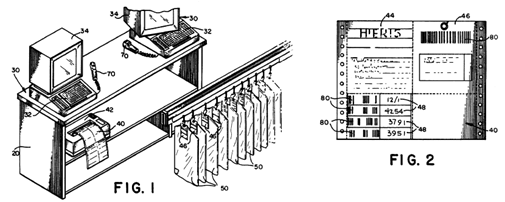 {明細書の開示内容} ・インベントリー管理の基本的な機能は、物(material)の出入り(incoming and outgoing)をカウントするとともに、全体として運用し続けることである。ある状況では、物品の同一性(identification of articles)を監視しなければならない。このことは、インベントリー管理をより複雑にしている。 ・より洗練された、一般的なインベントリー管理システムは、ベック特許(米国特許第3,478,316号)である。この特許は、ランドリーの小口客用店舗において、自動的にスキャンできるタグを、洗濯物である物品に添付するものである。 ・本発明は、主として小口客向けのドライクリーニングのオペレーションにおいて、手動で打ち込むデータをインエントリー管理システムにより効率的に入力するものである。 ・インベントリーに対して物品及びキャッシュを取り込むために調和させる(reconcile)べき情報は、一定のプロコトルに従って提供される。 ・物品の同一性、顧客の同一性、並びにコストの発生及び価格レポートに関する事柄は、入力されるべきである。 ・バーコード及び物品の間の積極的なクロスレファランス(相互参照)は、機械管理の下において、物品とキャッシュとインベントリーとの最適な調和のを可能とする。 ・本発明は、様々に変化する複雑さに対応する実施形態を提供する。 インベントリー管理及びマネジメント情報の報告に関する最適なシステムは、インベントリー中の物品の現在位置を決定して報告する能力を有する。 このシステムは、またインベントリーに対する手渡しのキャッシュ(cash on hand)をも調和させることができる。 |
| [裁判所の判断] |
|
ここで問題となっているのは、特許書類の一部であって、特許権者の権利の範囲を規定する、いわゆる特許クレームを解すること(interpretation)が法律問題であるのか、それとも憲法修正第7条の保証を与えられたものであるのかである。 法律問題であれば、その判断は、全体として(entirely)、裁判官に委ねられる。 憲法修正第7条の保証が与えられたものであれば、陪審が当事者間に争いのある技術用語の意味を決定する。そしてその意味について専門家の意見を聴取させることができる。 当裁判所は、クレームの解釈(construction)は、クレーム中の用語を含め、もっぱら裁判官が行うものと決定した。 (I)アメリカ合衆国の憲法は、議会に対して“科学及び有用な技術の発見を促進するために”、一定の期間に限り、著作者及び発明者に、その著作及び発見に関する排他的権利を付与することの権限を与えた。 (a)1790年、議会は、この権限を用いて、発明者に対して、“その発明の全部を開示することの見返りとして(in exchange of)、他人が特許発明について使用・譲渡の申出・販売・輸入を行うことを禁ずる権利”を与える法律を創った。 特許に関しては長い間に亘って次のように理解されてきた。 すなわち、特許権者が手にした全ての権利を明らかにするとともに、何が公衆に残されているのかを明らかにする(apprise)ために、当該特許には、発明の正確な範囲及びその製法が示されていなければならない。 McClain v. Ortmayer, 141 U.S. 419, 424 (1891) 現代のアメリカの特許制度では、これらの目的は、特許書類の2つの要素によって実現される。 特許種類が含む第1の要素は、明細書である。明細書は、発明の全部を正確かつ簡潔に、正確な用語で記述して、その技術分野の通常のレベルを有する者が{発明者と}同じように製造し、使用できるようにしなければならない(米国特許法第112条)。 特許書類が含む第2の要素は一つ又は二以上のクレームである。クレームでは、特許出願人が発明であると考える主題(subject matter)が明確に請求されていなければならない(同条)。 クレームが保護対象としてカバーするのは、プロセス・装置・製法・物の組成又はデザインであり、決してそのいずれかの機能又は結果、あるいはそれらの作用の科学的な説明であってはならない。 クレームは、特許が許可された範囲を定義するものであり、次のものを禁止する機能を有する。 ・発明の正確なコピー ・発明の核心をついている(go to the heart of the invention)が、文言侵害を回避するために些細な変更(noncritical change)を加えた製品 以下、この判決理由では“クレーム”問いう用語を、特許法固有のクレーム{日本語で言う請求項}の意味用いる(中略)。 侵害訴訟に勝つためには申し立てられた侵害品またはプロセスが特許クレームによってカバーされている事実認定が必要である。 故に事実認定の際にクレーム中の用語が何を意味しているのかを決定する必要がある。 (b)上告人であるMarkmanは、“ドライクリーニング店のためのインベントリー・コントロール及びレポートシステム”と称する発明に対する再発行特許第33054号のオーナーである。 ※再発行特許とは、最初の特許出願について特許が付与された後の所定期間内に、再発行特許出願をすることにより、最初の特許の内容に一部変更・追加を加えて付与される特許を言います。 →再発行特許とは 本件特許は、ドライクリーニングの設備(establishment)において衣服の状況・場所・動きを監視してレポートするスステムを記述する。 Markmanのシステムは、各取引についての文書による記録(written record)を発行するためのキーボード及びデータプロセッサからなる。前記レコードは、光学的検知器によって読み取ることができるバーコードを含む。 このシステムでは、従業員は、前記ドライクリーニングの進行状況を記録(log)する。 被上告人であるWestviewの製品も、キーボード及びプロセッサを含み、当該プロセッサは、ドライクリーニングサービスの料金をバーコード型のチケットの上にリストとして出力する。このチケットは、携帯可能な光学的検知器によって読み取ることができる。  (c)Markmanは、Westviewと、Westviewの製品を使用したドライクリーニング設備のオペレータであるAlthon Enterprisesとを特許侵害で訴えた。 Westviewは、自分のシステムがMarkmanの特許を侵害しないと主張した。何故なら、Westviewのシステムの機能は、インボイス及び取引全般を追跡することにより、売掛け金(receivables)のインベントリーを記録することであり、衣類の現物のインベントリーを追跡するものではないからである。 論争の一部は、“inventory”という言葉の意味にかかっている(hinged upon)。 “インベントリー”という用語は、Markman特許の独立クレームで次のように現れる。 ・全体としてのインベントリー(an inventory total)を維持すること。 ・前記インベントリーに対する偽り(spurious)の追加を検知して場所を特定(localize)すること。 この裁判は陪審によって審理され、陪審はMarkman側が用意した専門家がインベントリーの意味について証言するのを聴いた。 (d)陪審は、本件特許をWestviewの装置と比較したのちに、Markman特許の独立クレーム1及び従属クレーム10の侵害を認定した。 それにも関わらず地方裁判所は、法律問題としての判断の申立て(JMOLの申立て)を許可した。 →JMOL動議(Motion for Judgment as a matter of law)とは その根拠の一つは、Markman特許の“インベントリー”という用語は、“キャッシュ・インベントリー”及び物理的な物である衣服のインベントリーの双方を含む、ということである。このトライアル裁判所による特許の解釈(construction)によれば、特許発明は、クリーニングプロセスの間、衣服を追跡することができ、かつ衣服の状況及び所在に関してレポートを発行するこうとが必要である。この要件が満たされない限り、ドライクリーニングのための追跡システムの製造・販売・使用は、Markmanの特許の侵害とはならない。 Westviewの装置は、そうしたことをしないため、地方裁判所は、指揮権を行使して、下記の評決を出させた。その内容は、Westviewの装置は、全体としてインベントリーを有しておらず、インベントリーに対する疑わしい追加や削除を検知できないというのである。 (e)Markmanは、地方裁判所の判決に対して控訴した。 控訴の理由は、クレーム中の争いのある用語である“インベントリー”について、陪審が有していたであろうと推定される解釈(construction)を裁判所の解釈(construction)に置き換えたことは誤っているというものである。 連邦裁判所は、原判決を肯定し、クレームの用語を解すること(interpretation)は裁判所の専権事項(exclusive province)であり、このように結論することは憲法修正第7条と矛盾するものではないと決定した。 Markmanは、各ポイントについて裁判所の見直しを求め、我々は、裁量上訴(certiorai)を許可した。 →certiorai(裁量上訴とは) 我々は、原判決を肯定する。 (II)憲法修正第7条は、“コモンローの法廷において、訴訟の対象が20ドルを超える価値を有する時には、陪審によるトライアルを受ける権利が保障される。”旨を定めたいる。ジョセフ・ストーリー判事の時代より(1812年のStates v. Wonson, 28 F. Cas. 745, 750)、我々裁判官は、“このように保障された、陪審によるトライアルを受ける権利は、前記修正が採用された時点においてイギリスのコモンローの下で存在した権利である。”と理解してきた。 Baltimore & Carolina Line, Inc. v. Redman, 295 U.S. 654, 657 (1935年) こうした判断手法−歴史的テスト(historical test) −の長年に亘る遵守を踏まえてを踏まえて、我々は、第1に、我々が取り扱っている訴因(cause of action)が我々の建国の時点(at the time of Founding)にコモンローで審理される(tried at law)事柄、或いは、これに類似するものであったかどうかを問わなければならない。 この点に関して例えば次の判例を見よ。 Tull v. United States, 481 U.S. 412, 417 (1987年) もしこの訴訟が当該コモンローのカテゴリー(the law category)に属するのであれば、我々は、次に、1791年の時点で存在したコモンローの実態を維持するために特定のトライアルの決定が陪審によって行われるべきかどうかを判断する。 (A)第1の論点に関して、先例は次のように述べている。 訴因の性質に関して、“我々は馴染みのある方法を有している。まず、我々は、制定法上の訴訟を、イギリスにおいてコモンロー裁判所(court of law)及び衡平法裁判所(court of equity)が統合される前の同国の訴訟と比較する。” Granfinanciera, S. A. v. Nordberg, 492 U.S. 33, 42 (1989年) 同じように馴染みのある手法は、18世紀においてコモンロー上で審理されていた侵害訴訟から、現代の特許侵害訴訟を関連付けること(descent)である。 2世紀以上前からの先例がそうであったように、今日、侵害訴訟が陪審によって審理されるべきことに関して議論の余地はない。例えば次の判例を見よ。 Bramah v. Hardcastle, 1 Carp. P. C. 168 (K. B. 1789年)  (B)上記の結論から、第2の質問が生ずる。すなわち、陪審トライアルにおける特定のイシュー、ここでは、特許クレームの解釈(construction)が、それ自体、陪審イシューでありかつ主要事実を陪審によって解釈する権利を留保(preserve)することが保証されているかどうかである。 幾つかの例では、第2の質問に答えることは簡単である。まさに、この従属(subsidiary)の質問を陪審に委ねるものとする英国のプラクティスについて歴史上の証拠があるような場合である。 しかしながら、本件のように、古いプラクティスが明確な答えを与えない場合には、我々は、誰にでも扱える(foolproof)テストの恩恵なしに、憲法修正第7条が保障される範囲を判断しなければならない。 (a) 裁判所が繰り返し述べているように、第2の質問に対する答えは、陪審によるトライアルのコモンロー条の権利の実体を留保するために、陪審がその責任を背負う(shoulder)べきか否かで判断するべきである。 前述のTull v. United Statesの判決では、先の判例(Colgrove v. Battin, 413 U.S. 149, 157 1973年)を引用して、次のように述べている。 “陪審によるトライアルのシステムにとって基本的で固有(inherent in)かつ核心的なこれらの事柄(incidents)のみがlegislature(立法府)の枠の外に置かれるのである。” この点に関して、次の判例を見よ。 Galloway v. United States, 319 U.S. 372, 392 (1943年) (b)しかしながら、コモンロー上の権利の実体(substance)という概念は、区分(distinction)をつける上では、全く不便(pretty blunt)な道具である。 当該裁判所は、その概念を鮮明化(sharpen)して確実なものとするため、当該実体と手続とを区別しようとした。この点に関して例えば次の判例を見よ。 Baltimore & Carolina Line, supra, at 657 Galloway v. United States, supra, at 390-391 Walker v. New Mexico & Southern Pacific R. Co., 165 U.S. 593, 596 (1897年) Sun Oil Co. v. Wortman, 486 U.S. 717, 727 (1988年) 我々は、また、事実問題及び法律問題のイシューの間の境界線(line)についても論ずる。 例えば、次の判例を見よ。 Baltimore & Carolina Line, supra, at 657 Ex parte Peterson, supra, at 310 Walker v. New Mexico & Southern Pacific R. Pullman-Standard v. Swint, 456 U.S. 273, 288 (1982) (c)より根拠のある(sound)手法は、混合的 (mongrel) な手続があるときに、当該手続をヒストリカルな方法(historical method)で分析することである。 混合的な手続とは、例えば証拠の受領に続いて技術の用語を解釈すること(construe)である。 こうした手続は、我々が訴訟及びアクションを特徴付けるときに行われる。 ぴったりの前例(exact antecedent)がない場合に望み得る最善の方法は、現代のプラクティスを、判事又は陪審のどちらに権限が割り当てられたかを我々が知っている初期の事例と比較することである。そして新旧の事例の間での最良のアナロジーを見出すのである。 Tull v. United States, supra, at 420-421 (C)1790年よりも前において、イギリスのプラクティス及びアメリカのプラクティスには、クレームの性質を有する書類は現れない。故に我々は史料(historical sources)の中に現代のクレームの解釈(construction)についての直接の前例を見い出せない。 クレームのプラクティスは、1836年法が廃止されるまで立法者によって認識されておらず、また特許書類にクレームを含めるという要件は、1870年までは認識されていなかった。 しかしながら、ある歴史家の観察によれば、1850年までには、“判事は、しばしば、発明を確認するために特許中にクレームされたアイディアを表記するようになっておらず、そのクレームされた事項、すなわち、発明のサマリーに限定された範囲で{裁判上の論点に関する}問い(inquiry)が設定するようになっていた。もっともそうしたクレームの記載が明細書や図面ほどでないにせよ重要であるというアイディアは、1870年の改正までは発達していなかった。 明細書は、これ自体比較的新しい書類であるが、憲法修正第7条の類似例に関連して、特許を取得するためのキーであった。 初期の特許制度は、いわゆる‘新規性アクション’及び“実施可能ケース”として代表化(typify)されいた。 前者は、{特許の}エッセンスの部分がすでに社会に公開されたものであるかどうかをテストするものである。” Huddart v. Grimshaw, Dav. Pat. Cas. 265, 298 (K. B. 1803) 後者は、取引業界の適当な一員 (member)により発明を再生産(reproduce)できる程度に明細書が当該発明を開示している否かを陪審が決定するものである。  (a)現代のクレームの解釈(construction)に最も近似する18世紀の類似例は、明細書の解釈(construction)のようである。 当該書類の機能に関して、我々が入手し得た特許のケースは僅かであるが、それらによると、今日のクレームの解釈(construction)を陪審イシューとするべきことを裏付ける類似性の議論をサポートする陪審のプラクティスは確立されなかった。 幾つかのケースでは、明細書中の用語を如何に回するか(interpretation)が争点となった。例えば、次の判例を参照せよ。 Bramah v. Hardcastle, 1 Carp. P. C. 168 (K. B. 1789年) King v. Else, 1 Carp. P. C. 103, Dav. Pat. Cas., 144 (K. B. 1785年) Dollond's Case, 1 Carp. P. C. 28 (C. P. 1758年) Administrators of Calthorp v. Waymans, 3 Keb. 710, 84 Eng. Rep. 966 (K. B. 1676年) しかしながら、いずれの事例も、そうした用語の定義が陪審によって決定されるべきものであることを(demonstrate)していない。 こうした確立されたプラクティスが存在していなかったことは、我々にとって驚きではない。何故なら、18世紀末において、陪審制度は、この分野において目新たしい(new)制度であり、陪審による特許プラクティスも原始的(primitive)な段階にあったからある。 コモンローの下で、モノポリーの有効性を決定することを定めた専売条例(Statute of Monopoly)の執行から1791年まで1世紀以上の時が経過しているが、特許訴訟(patent litigation)は1752年まで枢密院(privy council)の管轄であった。そしてその時点までは陪審トライアルというオプションは存在しなかった。 コモンロー裁判所の元での1800年までの特許法の有り様は次の如くであった。 “レポートされた事例では、いかなる重要な判決をも欠乏していた。…従って、18世紀末のコモンローの判事は、最近の信頼できる先例の助けなしに幾つかの法律の原則を拾い集める(pick up)しかなかった。” Hulme著, “On the Consideration of the Patent Grant, Past and Present”, (1897年) これら初期の書籍のライター達は、特許法のあいまいな(amorphous)性質に異口同音の落胆(similar discouragement)を表明している。そして1830年までは、イギリスの論評者達は、この分野での混乱に耐えなければならないということに困り果てていた。 (b)Markmanは、次の2つの判例に依拠しており、そして初期のケースのレポートに欠落していることを多くの言葉で補おうとしている。 Turner v. Winter, 1 T. R. 602, 99 Eng. Rep. 1274 (K. B. 1787年) Arkwright v. Nightingale, Dav. Pat. Cas. 37 (C. P. 1785年) そしてMarkmanは、18世紀の陪審が特許用語の定義者であった筈であると主張した。 それらのケースの論点が実施可能性(enablement)や新規性(novelty)であれば、彼らが至った結論と同様の評決に到達したであろう。しかしながら、簡単にそうした結論にはならない。 陪審が特許書類の用語について、他の分野の書面中の用語に比べてより完全に解すること(plenary interpretation)ができる理由はない。 そして我々は、この時期に、陪審ではなく判事が別の種類の文書を解釈(construe)していたことを知っている。この当時において、特許に関連して判事が同様に役割を果たしていたであろうことは、次の事情から確認できる。すなわち、{その次の時代に}イングリッシュレポートが特許書類の解釈(construction)を掲載し始め、そこでは判事が明細書中の用語を解釈する(construe)する様子が描かれていたのである。例えば次の判例を見よ。 Bovill v. Moore, Dav. Pat. Cas. 361, 399, 404 (C. P. 1816) この事例では、判事が陪審に対してある表現(language)について説明した後にのみ、新規性について問いを設定し、かつどのような用語(term)で明細書が語られている(run)のかを述べていた。 Russell v. Cowley & Dixon, Webs. Pat. Cas. 457, 467-470 (Exch. 1834) Haworth v. Hardcastle, Webs. Pat. Cas. 480, 484-485 (1834) これら事例では、{判事が}評決を見直す際に明細書を解釈(construe)した。 これらのエビデンスは、我々の裁判所の複数のケースで裏付けられる(buttressed)。これらのケースは、判事が特許を解釈する(construe)実際のプラクティスを示すものである。例えば次の判例を見よ。 Winans v. New York & Erie R. Co., 21 How. 88, 100 (1859); Winans v. Denmead, 15 How. 330, 338 (1854); Hogg v. Emerson, 6 How. 437, 484 (1848) 用語を解する(interprete)実務の現代的な類似例として、我々のパテントプラクティスに関するしるし (indication)において印象的なことは、全ての事案がランドパテント(land patent)に関するものであることである。 ※ランド・パテント…政府が公有地を譲渡した時に発行する土地権利証 そしてこれらの事案において、用語を解釈すること(construe)は、陪審ではなく、判事の仕事であった。 (D)Markmanは、18世紀において用語を解する責任(interpretive responsibilities)を主に負っていたのは判事であるという彼の論点(contention)を失った後に、より穏やか(modest)な論点について、類似性に関することなる論拠(anchor)を見出そうとした。 その論点とは、特許の殆どの用語を解釈すること(construe)が判事の職務であるとしても、明細書に採用された用語を適宜する技能(art)は、陪審の職分(province)に属するものである。 しかしながら、Markmanは、問題の時期におけるオーソリティを示しておらず、後のケースであるNeilson v. Harford, Webs. Pat. Cas. 328 (1841)に依拠するのみである。 この事件では、判事と弁護士とのやりとり(exchange)から、特許の解釈(construction)は通常は裁判官が行うものであるが、技術用語に関する問いは陪審に委ねるべきことが示されている。 我々は、この資料の執筆者の見解を軽視する(disparage)ものでは決してないが、このイングリッシュレポートは、我々が問題としている時代から70年以上も後のものであり、そうした例外的な事例がそれ以前にもあったかもしれないということを示唆するにすぎない、と考える。 例外的なプラクティスが1791年に存在したというMarkmanの推論(inference)については、それがあった可能性が存在すると言えるだけである。従って、我々はMarkmanの見解に関して学術的なオーソリティを見出すことができない。  (III)合衆国憲法の制定(Framing)の時点でコモンローのプラクテイスが存在することは、クレームの解釈(construction)に対して必ずしも憲法修正第7条の陪審の保証を適用することを伴う(entail)するものではない。 そこで我々は、この意味を決定するという作業を特徴付け(characterize)、それを裁判官又は陪審のいずれかに割り当てなければならない。 そこで我々は、現存する先例を検討し、判事及び陪審の相対的な用語を解するスキル並びに制定法のポリシーを考察して、どちらにその作業を割り当てるのかを決定しなければならない。 (A)単純な特許のケースの2つのエレメント、すなわち、特許を解釈すること(construe)及び侵害があったかどうかを決定することは、かつての特許実務者 (practitioner)であるCurtis判事によって特徴付けられた。 第1のエレメントは、法律問題であり、裁判官によって決定される。前述の特許を解釈することとは、特許証、並びに発明の記述(the description of the invention)及びこれに付されたクレームの明細(specification of claim)を解釈すること(construe)である。 第2のエレメントは、事実問題であり、陪審により提示(submit)される。 Winans v. Denmead, 15 How., at 338; Winans v. New York & Erie R. Co., 21 How., at 100; Hogg v. Emerson, supra, at 484; Parker v. Hulme, supra, at 1140 (a)マークマンは、第1の問いに関する責任の割り当てを異なる観点から論ずるために、次の2つのケースに依拠(rely on)している。 Bischoff v. Wethered, 9 Wall. 812 (1870) Tucker v. Spalding, 13 Wall. 453 (1872) Markmanによれば、これらは次のことを示すエビデンスであるとされている。 ・19世紀において特許用語の意味は陪審に提供 (offer)されていたこと。 ・このことは、書面上の用語のイシューは、それが事実の証明の問題であるかどうかを問わずに陪審イシューであることを示していること。 しかしながら、それらは2つの判決が示すものではないというのが我々の立場である。 (b)Bischoff事件は、競合関係にある特許(rival patents)の解釈(construction)が問題となった事件である。 この事件を解決するため、我々は、裁判官が2つの明細書を比較して、そこに記載された発明同士が同一であるか否かを法律問題として陪審に判断させる義務を負うかどうかを検討しなければならない。 我々は、彼らがその義務を負わないと解する。 その理由は、そのように裁判の結果に直結する(dispositive)役割を裁判官に授ける(invest)ことは、侵害の主要な質問に答えるという陪審の機能を阻害するからである。 主要イシューに関して、例えば異なる特許に記述されたメカニズムや製品(manufacture)の性質及びそれらの間の同一性(identity)及び異質性(diversity)についての専門家の意見を聴取することができる。 一般には、侵害の問いに答えるために陪審が専門家証人の意見を考慮することは、“書証(written document)の意味を解釈する(construe)することは、陪審ではなく裁判官の職分である。”という確立された原則を破る(impinge upon)ことになると言われてきた。 当裁判所は、それは違うということを決定する。 (c)我々の見解は次の通りである。 “明細書は、メカニズムや複雑な機械類、化学的合成物、製造物を記述することを明言している。” これらは、法廷の外の存在 (existence in pais)、すなわち、書類自体の外にある物である。これらの物は、それらが属する技術又は秘訣(mystery)における用語で記述されることが一般的である。そしてそれらを正しく理解するためには、通常、固有の知識及び教育を必要とする。 特許全体としての主題は、特許それ自体の外側で実施化されたコンセプトである。 特許に含まれる用語の外部態様(outer embodiment)は、発明された物(thing invented)である。外部の物を記述することにより潜在的な不明確性(latent ambiguity)は、書面以外の証拠(evidence in pais)により正しく説明される。 →書面以外の証拠(evidence in pais)とは  Bischoff事件は、Markmanが主張するように専門家証人を用いることは、陪審に対して彼らの解釈(construction)への問いを投げかけるものではない。そうする代わりに、この事件において、裁判所は、文書を解すること(interpretation)と製品との同一性(identification)との間に線引きをした。そして、専門家の証言は、後者の問題、すなわち、特許によって製造された物と物理的に同一であるか否かについて適法に提供され得ると決定した。 裁判所は、この決定が当事者間で争いのある用語の適当な取り扱いに関係あると見なさない。 判決理由(opinion)が強調しているように、この事件において、裁判所は、文書を解すること(interpretation)と、製品の同一性の判断(identification)との間に線引きし(draw a line)、専門家の証言は、陪審に対して、後者の問題、すなわち、特許によって製造された物と物理的に同一であるかという主要イシューについて、適用に提供され得ると決定した。 裁判所は、この決定が争いのある用語の適当な取り扱いに関係があるとは見なかった(did not see)。 判決理由(opinion)が強調している通り、この裁判所の見解は、“文書(written instrument)の解釈(construction)は裁判所のみの職分である。”という原則を破る(trench upon)ことを意図していないし、現に破っていない。 発明の同一性又は異質性(diversity)に関する問いにおいて探求するべきであるのは、文書の解釈(construction)ではなく、発明された物の特製(character)である。 Markmanによって引用された2番目のケース、Tuckerも同様の影響を有する。 その理由付けは、Bischoffに依拠しており、事実と法律とが絡み合った主要イシューに関して、陪審に対して彼らを支配する法律を当てはめる(lay down)のは裁判官であると述べている。 (d)仮にこれら2つのケースにおける線引きがもっともなものであれば、それは特許訴訟において裁判官が陪審及び判事のそれぞれの役割を説明するために度々設定する境界線と同じであろう。またそれは、Markmanが引用したケースの直後の時期(aftermath)に書いたコメンテータが理解していたものと基本的に同じである。 “Patent Law”と言う書籍(1895年)の著者であるWalkerは、Bischoffの判例を、これは新規性に関する問いが先行技術の解釈(construction)によって決まるものではなく、むしろ先行技術に含まれる外面的形態(outer embodiment)により決まる。こうした外面的形態の意味合いは、法廷外での証拠によって求められる。それは、外部の物(external thing)を記述する時に生ずる隠れた曖昧さ(latent ambiguities)を説明する場合と同じである。 そしてWalkerは、同じ書籍においてクレームの解釈(construction)に関することは、たとえ専門家証人の助けを借りるとしても裁判官に対して問われるべきであるとしている。 (e)解釈(construction)上の問いは、判事に対する法律的な問いであって、陪審に対する事実上の問いではない。しかしながら、特許証に持ちられている技術又は科学上の用語の意味について裁判官が常に十分な知識を有している問いうことは期待できない。 従って、それら用語やフレーズの重要性に関連する専門家によって裁判官が知見(light)を得ることが重要なのである。 しかしながら、判事はその証言に従う義務は追わない。裁判官が証拠を使用する際に、その役割に言及した別の現代的な論文にも、前述の見解と同様のことが記載されている。 (f)“特許証を解する(interprete)義務は、裁判所に委ねられている。特許は、法律的な文書 (instrument)であり、他の法律的な文書と同様にその意味(tenor)に応じた解釈(construe)が行われなければならない。そこに技術的な用語が用いられていたり、そこに記載された物の特性や作用あるいは類似のデータであって特許の言い回しを理解するために必要なものを判事が知らない場合には、その主題に関して証言が認められ、あるいは他のインフォメーションの手段が取られる。しかしながら、実際に特許を解する(interpretation)ときには、裁判所は、法律の従事者(arbiter of the law)として、自らの責任でそれを実行し、特許に対して真実かつ最終的な性質及び効力を付与する。” 結論として、Bischoff及びTuckerのいずれも特許を解釈する(construe)際に陪審に技術用語の意味を解明する(resolve)ことを示唆するものではない。 従って、この2つの事例は、前述のジャスティス判事のオーソリティを損なうものではない。 (B)ヒストリー及び先例のどちらも明確な答えを与えない場合には、機能的な考察もまた、判事及び陪審のどちらが技術用語を定義するのかを選択するのかについて、その役割を果たす。 Miller v. Fenton, 474 U.S. 104, 114 (1985) この判決によれば、{史料の解明が}いわば手付かずの状態(pristine)にある法律的スタンダードと簡単な歴史的事実との間に論点が存在する場合には、その時の事実問題及び法律問題の区別(fact/law standard)は、健全な行政的公平性(sound administrative justice)の問題として決定される。すなわち、問題の論点に決定を下す一人の司法的主体(judicial actor)がより良い立場になる方を選ぶのである。この考え方を本事案に当てはめると、特許用語の既得の意味(acquired meaning)を見出すのにより適任であるのは、判事であり、陪審ではない。また文書の解釈(construction)は判事が度々行う事柄の一つである。そして、それは、評釈(exegesis)に関してトレーニングを受けない陪審に比べて判事の方がより適切に行うことができるものと理解される。 特許の解釈(construction)は、特別な仕事であり、他の職種と同様に、特別のトレーニング及びプラクティスを必要とする。判事は、トレーニング及び鍛錬(discipline)によって陪審よりもそうした文書を適切に解する(interpretation)ものと考えられ、故に陪審よりも正しくその責務を果たすであろう。 Parker v. Hulme, 18 F. Cas., at 1140 1世紀半以上の前からこのように考えられており、そして現代のクレームに対して判事及び陪審の能力の優劣についてこの考え方を変更しなければならない理由はない。むしろ今日の方が特許のクレームは、様々な観点で大変テクニカルなものとなっている。それは、裁判所や特許庁によって、適当なクレームの形式及び範囲に関して多くの原則が発展させられた結果である。 Woodward著,“Definiteness and Particularity in Patent Claims”, 46 Mich. L. Rev. 755, 765 (1948). (a)Markmanは、次のような反論によって前述の考察に打ち勝つ(trump)ことができるかもしれない。 すなわち、陪審は、家業乃至職業(trade or profession)に特有の意味に関する問いに答えればよい。 何故なら、その問いの主題は、信頼性の判断(credibility determination)を要求する証言である。そしてそうした判断こそ陪審の強み(forte)であるからである。 特許訴訟で証言する専門家について信用性判断をしなければならないことは本当であり、理論上は、特許の世界のロジックにどちらの専門家が合致するのかを単純な信用性の判断で決定できることもあるかもしれない。 しかしながら、我々の書類の解釈(construction)の経験上、そのような方法で多数のケースのトライアル裁判を運用できるのかと言えば疑わしい。 我々の予測によれば、概して、いかなる信用性判断も書類全体の洗練された分析に組み込まれる。こうした分析においては、文書全体に適合するように用語を用いる標準的な解釈(construction)が要求される。 Bates v. Coe, 98 U.S. 31, 38 (1878年) U.S. Industrial Chemicals, Inc. v. Carbide & Carbon Chemicals Co., 315 U.S. 668, 678 (1942年) そして特許訴訟の審理において、陪審が ・{証人の}態度(demeanor)を評価したり(Miller v. Fenton, 474 U.S. 104, 114)、 ・人間の行動の動機(mainsprings)を推認したり(Commissioner v. Duberstein)、 ・社会的基準(community standard)を{判断に}反映させる (United States v. McConney)ことは、特許の構造全体から見て証拠を評価する訓練された能力に比べて重要ではない。 決定者(decisionmaker)は次のことを確かめる(ascertain)するためにより良いポジションを得て特許を解釈する(construe)権限を与えられている。 ・専門家が提案した定義が全体として明細書及びクレームに適合すること。 ・その定義が特許の内面的な一貫性(internal coherence)を保持すること。 従って、我々は、証拠による根拠(evidentiary underpinning)の有無に関わらず、トライアルの通常のコースにおいて、判事に譲り渡した他の多くの責務と同様に、技術用語の解釈(construction)を取り扱うに足る十分な理由があると考える。 (C)最後に、我々は、全ての解釈(construction)のイシューを裁判所を割り当てることに対する独立の根拠として、付与された特許の取り扱いを統一することの必要性に言及する。 General Elec. Co. v. Wabash Appliance Corp., 304 U.S. 364, 369 (1938年)によれば、“特許の限界は、次の理由から公衆に了知されなければならない。 第1に特許権者を保護するため、 第2に、他の人々の発明的才能を奨励するため、 第3に、特許の主題が最終的には公衆に捧げられる(dedicate)ことを保証するため、 である。 これについて次の判例をみよ。 ・United Carbon Co. v. Binney & Smith (1996) “特許の限界を了知させなければ、事業や実験を行うことで侵害tなり得る不確定な領域が生ずることで発明意欲を阻害することになる。 それは、当該領域に対する明確な独占(unequivocal foreclosure)を認めるのと殆ど変わらないであろう。” ・Merrill v. Yeomans, 94 U.S. 568, 573 (1877). ( “公衆が自らの権利を制限する事柄に関して明確に説明されないとすれば、自らに属するはずの権利を奪われたことになる。”) 特許専門の控訴裁判所として、連邦巡回控訴裁判所が創設された理由はまさにこの好ましい統一性を高めるためである。 統一性を増すことが技術の成果や産業のイノベーションを促すように米国の特許制度を強化する上で有利であると考えたのである。 しかしながら、こうした統一性は、書類の解釈(construction)のイシューを陪審に委ねることにより悪影響を受ける(ill served)。 これらの事柄を陪審イシューとすることは、特許訴訟の裁判において、証拠に関する意義の問いを広く開かれたものとすることにつながらない。 イシュー排除効(issue preclusion)の原則は、通常、統一性を育む(foster)からである。 Blonder-Tongue Laboratories, Inc. v. University of Ill. Foundation, 402 U.S. 313 (1971). →イシュー排除効とは 仮にイシュー排除効が或る管轄区における新しい独立の侵害被告に対して主張されなかったしても、{或る用語を}解釈するイシュー(interpretive issue)で純粋に法律的に扱うことは、内部司法権利上の確実性(intrajurisdictional certainty)を促進する。 何故ならば、未だ単一の控訴審のオーソリティにより内部司法統一性(interjurisdictional uniformity)が認められていない問題に対して、それらの問題に関する先例拘束性(stare decisis)が適用されるからである。 以上のことから、我々は、 “インベントリー”という用語を解すること(interpretation)はな陪審ではなく判事のイシューであると決定し、連邦巡回控訴裁判所の判決を肯定する。 そして上記の通り命令する(It is so ordered)。 |
| [コメント] |
|
①本件では、まず原審において、特許出願人がクレームに用いた“インベントリー”と言う用語を、“キャッシュ・インベントリー”として解釈することの可否が論じられています。 (a)原告側の専門家証人の意見を聴いて前記解釈を可とした陪審の評決が出されましたが、裁判官は、被告の申立に応じてこの評決を退け、異なる解釈(インベントリーは物品及び金銭を対象とする旨の解釈)に基づいて評決を出すように陪審を支持しました。 こうした申立をJMOL(Motion for Judgment as a matter of law)と言います。 (b)“インベントリー”は物の在庫及び出入りを対象とするのが普通であり、“キャッシュ・インベントリー”と言う解釈は耳慣れない言葉です。 (c)しかしながら、発明の作用・効果として物とキャッシュとを区別する必要がない場合には、特許出願人が言葉の意味合いを国語的な意味より広げてクレームや明細書に用いることはなくはありません。 (d)本事案において、特許出願人は明細書を記述する際に、インベントリーの対象として46か所で物品(article)という言葉を用いていますが、2か所で“article and cash”のように物品とキャッシュを併記しており、また一か所でこの“この発明はまたキャッシュにも用いることができる。”旨の表現があります。 (e)仮に、専門家証人が、こうした“キャッシュ”に関する記載を強調して、この発明はキャッシュインベントリーをも対象としている旨を“断言”したとすれば、一般人である陪審がその意見に納得してしまうということはあり得ることです。 (f)しかしながら、実際の特許出願の手続きでは、発明の範囲を広く見せるために、明細書中の用語の説明がクレームの記載に比べて不相応に広くなっている場合があります。 また特許出願をした時点では、明細書中の用語の説明とクレームの記載との釣り合いが取れていたものの、特許出願の審査の過程で先行技術などが示され、それを回避するために、クレームを減縮する補正が行われた結果として、明細書中の説明とクレームの記載とが整合しなくなっている場合もあります。 最高裁判所は、特許の解釈においては、 ・専門家が提案した定義が全体として明細書及びクレームに適合すること。 ・その定義が特許の内面的な一貫性(internal coherence)を保持すること。 に留意するべきである旨を強調していますが、それは正に上記のような事情を考慮したものであると言えます。 (g)この判断基準に照らして、本件のクレームを検討すると、このクレームには、 ・“物品”という用語が用いられていること。 ・“物品の同一性”及び“物品の説明”に関するデータをデータ入力装置に入力すること。 ・それらのデータを反映したバーコードを含む記録(タグ)を物品に付すること。 が記載されています。 要するに、ドライクリーニング店において、異なる客から預かった品物を混同してしまうと大変なことになるので、これを防止するためにデータ入力装置やバーコードを用いるのです。 いうまでもなく、“物品の同一性”が問題となるのは、物品の種類(例えばワイシャツ)が同じであっても、その物品の一つ一つに顧客の思い入れやこだわりがあることを前提としています。 キャッシュの場合には、そうした同一性が問題になることはまず有り得ません。 顧客Aが支払った100ドル札と顧客Bとが支払った100ドル札とを区別して扱わなければならない理由は何もないからです。 そうした観点からすれば、クレーム中の“インベントリー”を“キャッシュ・インベントリー”とした専門家の定義は正当ではなく、採用するべきではなかったと考えられます。  ②本案件の主要な論点は、修正憲法第7条との関係で、クレームの解釈が陪審イシューであると言えるかどうかです。 (a)最高裁判所は、前記第7条の導入当時以前のイギリスの判例に踏み込んで、関連する史料を調査しましたが、このクレームの解釈が陪審イシューであることを示す判例は見つかりませんでした。 (b)そもそもこの時代には、特許の範囲をクレームで判断するというプラクティスが未だ確立されていませんでした。そこで類似の事例として、明細書中の用語を解釈する若干の事例を検討しましたが、やはりこれを陪審イシューとすることが判例上確立しているとは言えませんでした。 (c)そこで最高裁判所は、陪審と判事とのどちらが特許クレームの解釈の主役として適当かの観点から考察し、このイシューを判事が判断するべき専権事項であると決定しました。 (d)事実問題として、特許侵害があったかどうかを陪審が判断する際に、侵害係争物をクレームの記載に照合することが必要となりますが、このクレームの解釈に最終的に責任を負うのは判事であるということになります。 (e)本事例では、クレーム中の“インベントリー”という用語が、キャッシュインベントリーに適用するのかどうかは、最終的に判事が決定しなければなりません。 陪審は、判事が決定したインベントリーの用語の定義に従って、特許侵害があったかどうかを評決するべきことと指示されます。 ③特許クレームの解釈が判事の職分であるとしても、控訴審の裁判官が原審で採用された特許クレームの用語の解釈を好き勝手に覆して良いということにはなりません。 TEVA PHARMACEUTICALS USA, INC., v. SANDOZ, INC., (No.95-26) (a)TEVA事件では、ジェネリック製薬の発明に関して、特許出願人がクレーム中に用いた、“molecular weight”(分子量)という用語の解釈が問題となりました。 この事件では、本件と異なり、非常に技術専門的でありかつ微妙な判断が要求されました。 (b)“molecular weight”の解釈の候補として、特許出願時の技術常識として、ピーク平均分子量・数平均分子量・重量平均分子量の3つが考えられました。 (c)そして、特許出願人が願書に添付した図表のうちで当該成分の分子量のピークを示すグラフから読み取られることができる分子量のデータと、明細書に実際に記載された分子量データとを比較すると、クレーム中の“molecular weight”をピーク平均分子量と解釈することが有力な解釈でした。 (d)しかしながら、被告は、グラフから読み取られたデータと明細書に記載したデータとの間には(僅かな)ギャップがあるから、“molecular weight”をピーク平均分子量と解釈するのは妥当ではないと主張しました。他方、原告は、そうしたギャップは、データを採取した実験方法(クロマトフラフィー)の性質から予測される誤差の範囲内であり、前述の解釈を採用することの妨げとならない、と判断しました。 この点に関して原告側及び被告側がそれぞれ専門家証人を立てて、主張し合ったのです。 (e)本件のように“インベントリー”を“キャッシュインベントリー”と解釈できるのかどうかという問題とは異なり、ここまで事案が技術専門的になると、裁判官の一般常識のみでは到底正しい判断はできず、専門家証人の証言が重みを有します。 (f)TEVA事件で最高裁判所は、専門家証人の証言を裁判記録だけで読む裁判官よりも、専門家証人の証言を生で聴いた陪審の方が、正しい判断を下し易いと判断し、この判断に明確な誤りがない限り、控訴審の裁判官が原審の判断を覆すべきではないと判断したのです。 |
| [特記事項] |
| 戻る |
今岡憲特許事務所 : 〒164-0003 東京都中野区東中野3-1-4 タカトウビル 2F
TEL:03-3369-0190 FAX:03-3369-0191
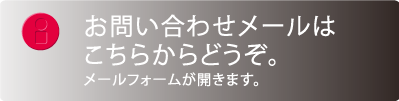
営業時間:平日9:00~17:20
今岡憲特許事務所TOPページ | はじめに | 特許について | 判例紹介 | 事務所概要 | 減免制度 | リンク | 無料相談
Copyright (c) 2014 今岡特許事務所 All Rights Reserved.

