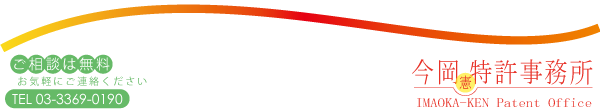
|
●Jorgen V. KIERULFF v. METROPOLITAN STEVEDORE COMPANY (315 F.2d 839)
黙示ライセンス/特許出願/禁反言/移動式船積み用クレーン
| [事件の概要] |
|
(a)控訴人であるKierulffは、訴外会社(National)に勤務するものであり、自らが発明したと主張する、移動式船積み用クレーンと称する発明について、自分の名義で1956年10月8日に特許出願をして特許権を取得しました。 (b)ところが、前記特許出願の日前である1955年7〜8月頃に、被控訴人であるMetropolitanの役員が前記特許の対象である発明品を見ていました。 (c)この発明品は、1955年7月に訴外会社(Modern Crane & Conveyor Company)で製造され、Kierulffの雇用者であるNationalに供給されていたものです。 (d)Kierulffは、Metropolitanが単に彼の発明を見ただけではなく、Nationalからその装置の設計を製造・製作する許可を得ていたことを知ったが、その時点では特に不服を申し立てませんでした。 (e)Kierulffは、後日、Metropolitanを特許権侵害で提訴したが、地方裁判所が、黙示ライセンスが成立しているという理由により、Kierulffの請求を棄却したため、控訴しました。 |
| [裁判所の判断] |
|
控訴裁判所は次の理由で原判決を支持しました。 ①この訴訟は、控訴人(原告)が、1959年12月29日に発行された本件特許(米国特許第2,919,042号)が侵害されたとして提訴されたものである。 当該特許を付与された特許出願は、1956年10月8日に行われた。 この発明は、船積み装置に関し、とりわけ、金属製のスクラップを積み込む装置に関する。 この訴えに対する答弁は、特許の無効性、ライセンス、侵害の不存在、及びエストッペル(禁反言)を構成する怠慢(laches)による抗弁を含んでいた。 ②特許の無効の議論は、複数の無効理由を含んでいた。クレーム1の文言の不明確さ、進歩性の欠如、先使用、先行技術などである。 しかしながら、被控訴人(被告。以下Metropolitan)というは、主として次の2つの主張を展開した。 A National (控訴人の雇い主であり、発明のオーナーであると主張されている)からの口頭によるライセンス B 控訴人がMetropolitanによる被疑侵害装置(accused device)の建設を耳にしながら(to one’s certain knowledge)、これを黙認(acquiescence)したことによる口頭のライセンス或いはショップライト →Shop-right(ショップライト)とは トライアル判事は、1961年3月20日に、部分的な略式判決を許可する命令を発した。再審議の申立が認められ、事実の認定、法的結論及び判決が1961年3月21に出されたが、これらは1961年9月6日に破棄された。 1961年9月12日に、トライアル判事は次の命令(order)を発した。 “この訴因は審理され、決定のために提出(submit)された。原告は1955年に被告に対してショップライトの性質を有する黙示のライセンス、すなわち、訴訟の対象である特許(第2,919,042号)の装置{スクラップローダー}を製造及び使用に関して、取消不可能で非排他的でありかつ譲渡不可能な権利を許諾した。” ③我々は、特許の有効性又は侵害の欠如に関して、これらの通常の用語の意味において、これらのイシューに踏み込むことを要しない。何故なら、{トライアル}裁判所の所論によれば、その両方について被控訴人にはショップライトが生じていると判断されているからである。 すなわち、KierulffがMetropolitanのスクラップヤードにおいて彼の設計によるスクラップローダーを見ていながら不平を申し立てなかったときに、黙示のライセンスが生じているというのである。 ④控訴人は次のように主張している。 被控訴人はNationalからのライセンスのみを得ていると力説しており、その根拠として次の2つの理論が審理されかつ議論された。 ・NationalからMetropolitanへ許諾された口頭による黙示のライセンス ・Kierulff からMetropolitanへ直接許諾された口頭による黙示のショップライト又はライセンス 後者の理論が陪審によりこの事件の支配的な要素として採用された。 すなわち、陪審は彼が1961年9月12日及び1961年9月18日に2件の注文を発したことを指摘し、黙示のライセンスに言及した。このライセンスは、訴訟対象である特許に記載された機械を製造・使用することに関するショップライトの性質を有する権利である。具体的には、取消不可能、非排他的、譲渡不可能な権利である。 ⑤当裁判所に要請されているのは、控訴人の訴訟に対するこの抗弁の是非を考慮することだけである。但し、我々がトライアル裁判所に同意せず、この問題が支配的でないと考えたときにはこの限りではない。 我々が控訴に対して決定をするにせよ、或いは、原審にケースを差し戻すにせよ、我々がこの第1の論点に関して判決するまではさらなる事実認定に関して{地方裁判所は}判断をする必要がない。 本件において許可された黙示のライセンスに関して、トライアルコートは “ショップライト”と称していないことに当裁判所は気付いたが、当該ライセンスは、そうした性質のものである。 巡回裁判所における黙示ライセンスのリーディングケースはおそらく、1949年のGate-Way, Inc. v. Hillgren, D.C., (82 F.Supp. 546)である。 この事件において、Judge O’Connor判事は、ショップライトは法律の適用(by operation of law)により発生したのであり、詐欺防止法(the statute of frauds)の範囲にあるのではないと述べた。  ⑥“ショップライトの原則は、衡平法上の起源によるものである。基本的な考え方は、発明者又は発明のオーナーが第三者による発明の使用を黙認 (acquiesce)した場合に、それらオーナーらが使用者に対して、取消不可能な(irrevocable)衡平法上のライセンスを授けた(vest)ものとみなされるということである。 特に、それらオーナーらが、補償の要求することも、また権利の継続を制限する旨を通知することなく、当該発明を使用することを誘導し(induce)かつ支援(assist)する場合が該当する。 発明者及び雇用者の間のこうした状況は、もちろん両者の間の合意によっても生じ得る。しかしながら、一般的には、発明者は、彼の雇用者が当該発明の使用に向かうように誘導(induce)し、単に発明の使用することに反対しないだけではなく、その使用者に寄り添いかつ使用することを支援している。そして彼の雇用者が発明の実施のために投資することを許容し、他方、自分は、発明の使用の放棄することを強制される犠牲的な立場に置いている。 Gate-Way, Inc. v. Hillgren, supra, at 555 次に示す法廷においては、4つのケースを引用し、依拠している。それらの全てが、ショップライトの一般的な理論、その制限及び範囲、衡平法の原則の適用によるその起源を支持している。” ⑦“{黙示ライセンスが}効果を奏する (give effect)ためには、まずライセンスの正式の許諾がないことが必要である。 特許のオーナーが発した如何なる言葉であれ、その行動であれ、それによって相手方が、特許を使用して特許対象の製造・使用・販売をすることに関して特許のオーナーが同意したと適切に推察し、そして当該推察に基づいてある行動したときには、{黙示の}ライセンスが構成され、当該行動を不法行為(tort)とする争いにおける抗弁となる。 それが無償の(gratuitous)ライセンスとなるのか、それとも合理的な補償を要するものとなるのかは、もちろん、状況次第である。しかしながら、その後の当事者の関係は、契約上(contractual)で決定されるべきであり、オーナーの権利の違法な(unlawful)侵害に基づかない。” ⑧Lukens Steel Co. v. American Locomotive Co.,事件(197 F.2d 939, 941)において、事実関係は下記の点を除いて本件のそれと類似している。 ・発明者(Lukens)は、American Locomotive Companyに対して特許発明を使用することのオーソリティを付与する前に、特許を取得していたこと。 ・American Locomotive Companyは特許の存在を常に知っていたこと。 ⑨“ショップライトに関する問いは、一般的には雇用主及び従業者の間で生ずるものであるが、こうした権利は雇用主のケースのみで生ずるものではない。何故ならば、そのドクトリンはエストッペルの広範なドクトリンの一つの表現(phrase)に過ぎないからである。ショップライトは、発明のいかなる許容された使用においても発生するが、特に発明者が当該発明の使用を持ちかけ(instigate)、その使用に参加している場合に発生する。” Gate-Way v. Hillgren ⑩このケースにおいて、我々は、通常のルールとしての衡平禁反言が当てはまると解釈する。 衡平禁反言は3つのクラスを含む。記録による禁反言(或いは既判力)、証書(或いは譲渡)による禁反言、そして、法廷外の行為(法廷外での言動)による禁反言である。 この禁反言に関してしばしば指摘される明白な要素は、ある当事者が禁反言の適用により{主張を}規制されるためには、当該当事者は、実際の事実に関する知識、又はconstructive knowledge(建設的知識)を持ってある行為をし、又はある行為をしなかった者であるべきであるということである。 ⑪“[衡平禁反言又は法廷外の禁反言の]基本的な原理は、自分の言葉や行動により、他者を、それらの言葉や行動がなかったら取らなかったであろう行為を行うように導いた者は、当該行為により生ずる他者の期待を裏切ることにより、その他者に対して損害や被害を与えてはならないということである。 このような立場の変更は、厳格に(sternly)禁止されている。 禁止事項には、詐欺や虚偽(fraud and falsehood)が含まれ、法律はこれらのどちらも禁止している。 この救済(remedy)は、正義の目的(ends of justice)を促進するために常に認められる。” Dickerson v. Colgrove, 100 U.S. 578 at 580, 25 L.Ed. 618. ⑫James v. Nelson事件(90 F.2d 910 1937年)において、裁判所は、前述の事柄を肯定するために、次の先例の文章を(Nelson事件)引用している。 “‘エストッペルの基本的な要素は、この裁判でも適用可能であるが、次のようなものである。 (1)訴えに係る事柄の禁止を要求する当事者を知らないこと。 (2)重要事実の不実表示又は隠蔽(misrepresentation or concealment)に言及する義務がある事柄に関して沈黙すること。 (3)不実表示又は隠蔽に依る当事者のアクション (4)エストッペルが否定された場合に生ずるダメージ’” (Nelson v. Chicago Mill & Lumber Corp., 1935年, 76 F.2d 17, 21)  ⑬我々は、その事件で認定された事実関係に法廷外の禁反言の基本的な要素が存在するかどうかを検討した。その事実関係を我々は次のように要約する。 (1)エストッペルを要求する一方の当事者(METROPOLITAN STEVEDORE COMPANY)を知らないこと (2)主要事実の不実表示又は隠蔽を陳述する義務が存する他方の当事者(Kierulff)の沈黙 (3)他方の当事者{の言動}に依拠する一方の当事者の行動 (4)エストッペルの原則が適用されない場合の一方の当事者の不利益 このイシューは、控訴人準備書面の{原判決の}エラーの明細書に挙げられている。すなわち(to wit) “裁判所は、黙示ライセンス、すなわち、エストッペルによるライセンスを認める決定をした点において誤っている。何故ならば、控訴人が被控訴人による彼の発明の使用を見つけたときに、強制可能な特許権を有しておらず、それどころか、初期の権利(inchoate right)も有しておらず、不服を申し立てる義務もなかったからである。さらに被控訴人は、発明を使用することに関して控訴人の沈黙を必要としておらず、更に、その立場を変更したことも全くない。” ⑭Metropolitanの無知に関しては、このポイントは、控訴人によって提起されていない。また控訴人はそうすることができなかったのであろう。何故から、仮に、Kierulffが特許権も前述の初期の権利も所有していないとすれば、どうしてMetropolitanが彼の所有を予期したことを期待できるのか分からないからである。この事実認定(裁判資料22)に関しては証拠中に裏付けがある。 Metropolitanの行為に関しては、裁判所は、そうした行為を認定する。この行為は、裁判の当事者が申し立てた、所定の性質の“沈黙”に依拠するものである。この行為は、事実認定に関する裁判資料10、12〜14、16、17に見出される。我々は、これらの記録の中に、この認定の裏付けであって、実質的でありかつ当事者によって議論されたものを見い出した。 Metropolitanの損害に関しては、我々は、特別の事実を見出すことができないが、幾つかの事実に関して、実質的な出費及びこれに伴うダメージが内在する(inherent)ものと認める。特に事実認定に関する裁判資料16を参照されたい。故にこの認定を裏付ける実質的な証拠が存在する。 ⑮しかして、我々は、Kierulffの沈黙について検討する。彼が沈黙していたことに関して、当事者間で争いはない。 しかしながら、彼は、声を上げるべき時に沈黙していたのであろうか。 その沈黙は、重要事実に関する不実の表示或いは隠蔽に該当する性質のものだろうか。 トライアルコートは、そうであると認定した。 我々が見るところ、控訴人はジレンマに陥っているようである。 仮に控訴人が“強制力のある権利を有しておらず、また彼の発明の使用を目撃した時点で初期の権利すら有していない”のであれば、そして、発明者又は発見者として、“公衆又は正当な手段でそれを見い出した者に対して排他的な権利を有していない”のであれば、仮は声を上げる義務を有しない。なぜなら、彼は、声を上げるべき、或いは、クレームするべき何物も有していないからである。 しかしながら、裁判で勝つ(prevail)ためには、彼が何らかの(特許ではなく発明)財産権を有していたことを主張(claim)しなければならない。しかも、その財産権は、不法に専有(appropriate)できたものでなければならない。 Taney主任判事によれば、この権利は、(発明者の選択により)後日特許を取得することにより完全な権利となる、初期の権利を意味する。すなわち、発明者は、それ{特許出願の手続}をとることができることを条件として、後日完全な名義を取得する法律上の権利を有する。 Kierulffは何故1956年10月8日より前に特許出願をしなかったのであろうか。 早い時点で特許出願をするに越したことがないが、裁判資料10〜18による事実認定によれば、Metropolitanの役員であるBuchholzがこの訴訟の対象である特許の主題である装置を最初に見たのは、1955年7月〜8月のことであると言われている(その時点で彼が発明をしたか否かは不知である)。 この装置は、1955年7月にModern Crane & Conveyor Companyより製造され、かつNationalに供給された。 2つの装置を改良することが同年5月に注文され、その改良品が1955年7月に届けられた。これについても、Buchholzは1955年8月には目撃している。 1955年7〜8月以降において“数日”程度の様々な局面で、事実認定されたこれらの機会が存在していたが、Kierulffは不平を述べ或いは抗議することがなかった。正確な日数は不明である。1955年8月の2度の数日間の機会の後に、Kierulffは、Metropolitanが単に“彼の”装置を見ただけでなく、Nationalからその装置の設計を製造・製作する許可を得ていたことを知った。 ⑯控訴人は、Kierulffの立場で抗議する義務が存在しなかったという彼の立場を裏付けるための2つのケースを引用し、衡平禁反言(equitable estoppel)の理論は拒絶されるべきであると主張した。 M’Millin v. Barclayの事件(1871年, 16 Fed. Cas. 302)において、申し立てに係る侵害は発明者が特許出願をした後に発生した。そして裁判所は、禁反言の適用となる如何なる発明者の発言又は行動の証拠も見出せないとした。 McWilliams Mfg. Co. v. Blundellの事件(1882年, 1 Cir., 11 F. 419)において、被告は、欠陥のある(defective)オリジナルの特許の再発行の直後に、侵害者として訴えられた。その特許発明を実施したというのである。これに対して、裁判所は、欠陥のある特許の下での先の使用は、その後に発行された再度の特許の使用の根拠とならないと正しく判断した。 我々は、この結論に同意するが、このケースが本件で説得力があるとは思わない。 沈黙による禁反言の認定は、一つの事実に過ぎず、法律の結論ではない。 次の判決を見よ。 Gill v. United States, 1895, 160 U.S. 426, 16 S.Ct. 322, 40 L.Ed. 480 この事件において、Gillは、知り合いに対して発明の使用を提供することは同意を構成すると主張した。Gillのケースにおいても、その行為は、ライセンスのために特許出願が行われた後に行われていた。 ⑰当裁判所は、地方裁判所が認定する主要事実に関して、Gate-Way v. Hillgrenの判例によって拡張されたGill v. United Statesの判例がこのケースを支配するものと決定する。 そして我々は、原告の作為及び不作為により、被告に対して禁反言による黙示のライセンスが許諾された旨の原判決を肯定する。 但し、このライセンスは、ショップライトの如き性質を有し、当該特許を侵害したと申し立てられた装置に関する、取消不可能、非排他的、譲渡不可能で、ロイヤリティフリーの権利である。 ⑱このライセンスは、特許が許諾された時又はそれ以前に実施されていた装置にのみ適用される。被控訴人は、それらの装置を、通常の耐用期間の間、修理することができる。 仮に控訴人が当該結果のセーフガードのために、特許の有効性に関して明確な結論を得たいというのであれば、当裁判所は、その論点に限定して審理が行われるように、事件を原審に差し戻すであろう。 この指摘は、黙示のライセンスは有効な特許に対して付与されたのであり、そうでなければ特許侵害が成立したであろうという結論に、十分な審理の結果として到達したのではないことを推定させる。 控訴人は、30日以内に、特許の有効性の決定を求めるためにケースを差し戻す旨の動議を行うことができる。そして我々の判断は、その動議に最終的な決着がつくまでの間、保留される。 仮に控訴人が差し戻しを希望しない時には、単純に原判決を肯定する判決が出される。 |
| [コメント] |
|
①本件では、企業の従業員である発明者が直ちに特許出願をせずにいたところ、単に雇用者に発明を使用されるだけではなく、第三者(Metropolitan)に発明品の製造・使用を許諾したことを知ったが、それに対して特に抗議をしなかったため、黙示ライセンスが成立したという事件です。 ②米国では、日本の特許法第35条の職務発明に関する法定通常実施権によく似たショップライトという権利が判例上認められています。 しかし、このショップライトは、非排他的な権利です。発明者としては、雇用者が実施するだけならともかく、第三者への製造・使用は看過できないと思ったのでしょう。 その間にどう言うやり取りがあったのかは不明ですが、その後、発明者は、自ら特許出願を行い、特許権を取得して、Metropolitanを特許侵害で訴えます。 ③しかしながら、Metropolitanによる発明の使用を知った時点で直ちに抗議しなかったために、発明の実施を黙認したものと認定され、黙示ライセンスが許諾されたものと裁判所は判断しました。 その裏付けとなる論理を法廷外の行為による禁反言(estoppel in pais)と言います。 ④なお、現在の米国特許法では、新規性・進歩性(非自明性)の判断時は原則として特許出願の時です。従って、このケースと同じ状況では、特許出願の前に第三者が実施している時点で、新規性が否定され、特許にならないので、黙示ライセンスの問題も生じません。 これに対して、この当時は、発明時が新規性等の判断時でしたので、こういう問題が生じてしまいました。 ⑤また、禁反言の原則との関係で黙示ライセンスが論じられた事件としては、他に次のものがあります。 AMP INCORPORATED v. THE UNITED STATES 389 F.2d 448 これは、技術開発請負契約の中で開発の成果である発明に関して、開発者が相手方に実施のライセンスを与えるという条項を含んでいたところ、契約締結後に、開発者が、自分が開発した発明が第三者の発明(基本発明)の利用する発明であることに気づき、第三者から、基本発明の特許権を譲り受けて、技術開発請負契約の相手方を訴えたというものです。 裁判所は、そうした行為は許されるべきではないので、黙示ライセンスが成立すると判断しました。 |
| [特記事項] |
| 戻る |
今岡憲特許事務所 : 〒164-0003 東京都中野区東中野3-1-4 タカトウビル 2F
TEL:03-3369-0190 FAX:03-3369-0191
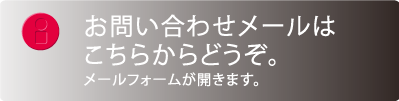
営業時間:平日9:00~17:20
今岡憲特許事務所TOPページ | はじめに | 特許について | 判例紹介 | 事務所概要 | 減免制度 | リンク | 無料相談
Copyright (c) 2014 今岡特許事務所 All Rights Reserved.

