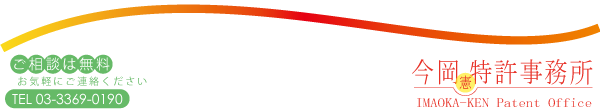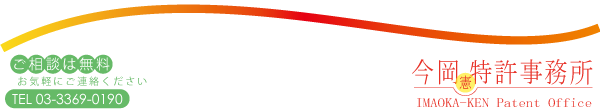| 内容 |
①職務発明の意義
(a)従業者等(従業者・法人の役員・国家公務員・地方公務員)が特許出願した発明が職務発明である場合には、使用者等(使用者・法人・国・地方公共団体)に無償の法定通常実施権が発生します。
その職務発明であることの条件は、その性質上使用者等の業務範囲に属し、かつ発明をするに至った行為が使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属することです。
(b)職務とは、一般に従業者等が使用者等の要求に応じて使用者などの業務の一部を遂行する責務を言いますが、企業によっては、その従業者の肩書きと実際の仕事の内容にズレが生じている場合があります。例えば“開発部長兼任”となっているけれど、実施にはそうではないという場合です。こうした場合にどのように解釈するべきかをケーススタディします。
②職務発明の事例の内容
[事件の表示]昭和42年(ネ)第804号
[事件の種類]琺瑯製和風浴槽控訴事件(控訴棄却)・職務考案該当性を否定
[判決の言い渡し日]昭和44年5月6日
[考案の名称]琺瑯製和風浴槽
[事件の経緯]
(a)琺瑯株式会社に勤務していた被控訴人甲は、
昭和三一年頃、控訴人乙であるA工業株式会社に入社して、その化工機部長となり、
昭和三十三年十二月一日開発部長に、
昭和三十四年十一月八日開発部長兼取締役に就任しました。
(b)甲がその在職中に、別紙目録記載の各登録実用新案を考案し、被控訴人名義で登録出願して登録を受けました。
(c)右登録出願の費用および登録料は、すべて乙が負担しました。
[裁判所の判断]
(a)控訴人は、甲と乙との間に右各登録実用新案について、乙の請求があったときは、その登録名義を甲から乙に移転すべき旨の黙示の契約があったと主張する。
しかしながら、本件のすべての証拠を検討しても、そのような事実を認めることはできない。かえって、当審証人Wの証言、ならびに原審および当審における甲本人尋問の結果によると、次のことを推認できる。
・乙の親会社にあたる丙においても、従業員のした発明考案はその個人名義で登録されていて、その従業員が会社を退職した後も、登録名義を会社名義に移転したようなことはなかったこと
・甲が乙に入社して間もない頃、当時乙が販売していた琺瑯浴槽について、甲がかねて研究して得た考案につき実用新案登録の出願をするに際し、乙の常務取締役であるWと話し合って、登録出願手続は従前から乙の仕事をしていたU弁理士に依頼し、そのための費用およびその後の権利維持のため費用は乙が負担するが、登録を受けた考案については乙が無償で実施すべきことを約定し、その結果、本件各考案の実用新案登録が甲名義でされたこと
・甲は現在までその対価とみるべきものは受領していないこと
(b)控訴人は、また、本件各考案は甲の職務考案に属する旨主張する
(イ)しかし、原審証人T、当審証人Wの各証言、原審および当審における甲本人尋問の結果を総合すると、次のことが認められる。
・乙は、昭和二十八、九年頃、それまで主に酒造用琺瑯タンクを製造販売していたW琺瑯株式会社が、製品分野を拡げて、琺瑯製の化学機器、浴槽などを製造するについて、その販売を主として取り扱う会社として設立された、いわゆる販売会社であって、生産会社ではない。
・甲は、旧東京美術学校工芸科を卒業し、乙が設立された頃はⅠ琺瑯株式会社に勤務していたが、乙に化工機部長として入社し、化工機部長として浴槽を主とする丙の製品の販売に従事し、開発部長に就任してからは、市場開発、販売企画などに従事するとともに、関係会社であるE工業、N工業、D化工機等の経営にも助言していた。
・これら職務のかたわら、かねて興味をもっていた琺瑯製和風浴槽の研究を行ない、W取締役と相談して、試作を要するものは丙に試作してもらって研究を重ねた結果、本件各考案を完成したものであることを認めることができる。

(ロ)前項認定の事実を合わせ考えると、本件各考案は、乙の業務範囲に属するものとはいえても、甲の職務に属するものであったとはいえないことが明らかであり、したがって、本件各考案をもって甲の職務考案とすることはできないものというべく、控訴人のこの点の主張も理由がない。
されば、本件各考案について、控訴人主張のような黙示の契約が成立していたこと、または、それらが甲の職務考案であることを前提とする控訴人の本訴請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由のないことが明らかであり、これを失当として棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がない。よって、これを棄却する。
[コメント]
本事例では、浴槽の販売を主たる業務とする会社の社員の職務のかたわらで完成した考案について、職務考案ではないと判断された事例です。この“職務のかたわら”をどう考えるのかが難しいところです。単に会社から所定の発明をすることを指示されなかったからと言って職務発明とは言えないとした判例があります。
→職務発明のケーススタディ4(指示がなかった場合の職務発明該当性)
|