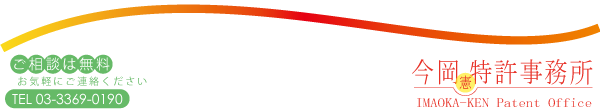
|
●昭和51年(行ウ)第178号(異議申立棄却決定取消請求事件/否認)
特許出願と不可変更力/分割出願/米菓の製造法
| [事件の概要] |
| ①本件特許出願の経緯 (a)原告は、 昭和四三年九月八日、発明の名称「油としよう油とで味付された米菓の製造法」について、昭和四三年特許願第六四七三八号として特許出願Aをし、 昭和四六年五月六日、拒絶査定を受け、その謄本が送達されたため、 昭和四六年六月二八日、原告は、これを不服として、拒絶査定審判の請求をし、昭和四六年審判第四八一七号として審理されたところ、 昭和四七年三月二二日付で審判請求書に貼用すべき収入印紙に不足があるとして審判請求書について却下の決定を受け、その決定書謄本が送達されたため、 昭和四七年六月五日、東京高等裁判所に対し、右却下決定の取消訴訟を提起したが、同年一二月八日、請求棄却の判決の言渡を受けたので、これに対し最高裁判所に上告し、 昭和五〇年七月四日、上告棄却となり、右判決は確定しました。 (b)他方、原告は、 昭和四六年六月二八日(右取消訴訟が上告審に係属中、すなわち拒絶査定がまだ確定していない間である)にAの分割出願である特許出願Bをしました。 なお、特許出願Aは、昭和四五年の特許法改正法の施行(昭和四六年一月一日)前にされたものであり、右改正前の特許法第四四条第二項(以下「第四四条旧第二項」という。)は、特許出願の分割は当該出願について査定又は審決が確定するまですることができる旨規定していました。 (c)被告(特許庁)は、一たんは特許出願Bを出願番号昭和四八年特許願第一三一三一号として受理しながら、その後の 昭和四九年六月一五日付で原告に対し、特許出願Bの願書は受理しない旨の処分(以下「本件処分」という。)をし、右処分の通知は、その頃、原告に到達しました。 被告の本件処分の理由は、特許出願BはAについて昭和四六年五月六日にされた拒絶査定の確定後にされたものであるというのです。 (d)そこで、原告は、 昭和四九年七月一五日、被告に対し、本件処分について、行政不服審査法による異議申立てをしたところ、被告は、 昭和五一年七月一日付で本件処分を正当として、右異議申立てを棄却する旨の決定をし、右決定書謄本は、同年一一月四日、原告に送達された。 ②特許出願人の異議申立に対する決定の理由は次の通りです。 原告は、特許出願Aについて、右のように拒絶査定を受け、これを不服として、審判の請求をしたところ、その審判請求書は不適法として却下され、右却下決定書謄本は昭和四七年五月一一日、原告に送達され、右却下決定に対して、原告が提起した取消訴訟は、原告敗訴として、昭和五〇年七月四日、上告棄却により終了したので、右査定は、これに対する右却下決定書謄本が原告に送達された右昭和四七年五月一一日から三〇日を経過した同年六月一〇日確定したから、その後にされた特許出願Bは、特許法第四四条旧第二項により受理できない。  ③特許出願人が主張する取消事由 本件処分は、次の理由により、法律の解釈及び適用を説つた違法なものであるから、取り消されるべきである。 “1 特許出願Aに対する拒絶査定の確定時期について、本件処分は、右査定に対する審判請求についての請求書却下決定書謄本が出願人に送達された日から三〇日を経過した時点(前記昭和四七年六月一〇日)とする見解をとるが、これに反し、右確定時期について、右審判請求についての請求書却下決定に対する取消訴訟の請求棄却の判決が確定する時点(本件においては、上告棄却の判決の言渡がされた昭和五〇年七月四日)とする説があるところ、後説が正当なものである。すなわち、 (1) 特許出願Aについての拒絶査定に対する審判請求書は、却下されたが、原告は、右却下決定に対し、適法な手続により取消訴訟を提起した結果、右査定は、その確定が阻止され、上告棄却の言渡がされた昭和五〇年七月四日まで未確定の状態にあつたのである。 (2)次に、本件処分は、特許出願Aについての拒絶査定に対する審判請求書が却下された以上、右却下決定が取消訴訟の判決で取り消されない限り、右査定は、右却下決定書謄本の送達された日から三〇日を経過した時点で確定すると解している。 しかし、右の「判決で取り消されない限り」ということからすれば、本件処分は、却下決定の命運がその取消訴訟の結果によるものとしているのであるから、その確定が取消訴訟の提起により阻止されていることを自認すものほかにならない。また、右の「却下決定書謄本の送達された日から三〇日」とは、右却下決定に対する取消訴訟の提起期間をいうものであるが、原告は、右期間内に取消訴訟を提起しているのであるから、右却下決定の確定が阻止されていることは明らかである。もし右各見解が認められないとすれば、原告の提起した右取消訴訟自体がすでに確定している却下決定を争うものであつて、不適法として排斥されなければならない筈のものであつた。 以上のとおりであるから、特許出願Aに対する拒絶査定は、右取消訴訟について上告棄却の判決の言渡がされた昭和五〇年七月四日に確定したものであるので、これより先昭和四八年二月一日にされた特許出願Bは、特許法第四四条旧第二項の規定に違反せず、適法な出願として受理されるべきものであつたから、その願書を受理しないものとした本件処分は、違法である。 2 仮に特許出願BがAについての拒絶査定の確定後にされたものであり、特許法第四四条旧第二項所定の分割出願として取り扱うことができないとしても、通常の特許出願として受理されるべきものであつた。しかるに、被告は、この点について、何ら考慮することなく、その願書を全面的に受理しないで、本件処分をしたのであるから、右処分は違法である。” ④原告に対する被告の反論 1 特許出願人の“1、(1)”の主張について、 特許法第四四条旧第二項によれば、分項出願は、特許出願について査定又は審決が確定した後はこれをすることができないと規定されていたところ、昭和四五年法律第九一号による改正後の特許法第四四条第一項によれば、分割出願は、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる時又は期間に限り、これをすることができると改定されたが、他方、右改正法附則第二条によれば、右改正法施行当時現に特許庁に係属している特許出願については、別段の定めがある場合を除き、その出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例によると規定されている。ところで、原告の特許出願Aは、右改正法が施行された昭和四六年一月一日当時、現に特許庁に係属していたことは、当事者間に争いのない事実から明らかであるから、特許出願Bは、特許法第四四条旧第二項により特許出願Aについての査定又は審決が確定した後にされたものである場合には、不適法ということになる。 ところで、右のように特許出願についての査定又は審決が確定した後において、分割出願を許さないのは、次の理由による。すなわち、分割による新たな出願は、特許出願Aのときにしたものとみなされる(右改正前の特許法第四四条第三項)から、特許出願Aについて出願公告をすべき旨の決定がされた後に分割出願を許すときは、その遡及効により第三者に不測の損害を被らせ、不当な結果を招来することになり、また、拒絶査定がされたが、審判の請求がなく確定した場合又は審判の請求が不適法あるいは方式違背を理由として審判請求書が却下されて確定した場合にも、なお分割出願を許すときは、その遡及効により既に形成された法秩序が無に帰する不当な結果を招来することになるのみならず、場合によつては、右分割出願により第三者に不測の損害を被らせる結果となるのである。右のように考えると、特許出願についての査定が確定したときというのは、 特許出願Aについて、特許庁における審査、審許判手続上の終局的処分がされ、処分者みずからの手によつて、その手続においては、その取消がされる可能性がなくなつたとき と解するのが相当である。 しかして、これを本件についてみるのに、当事者間に争いのない事実によれば、原告は、特許出願Aについて、昭和四六年五月六日に拒絶査定を受け、遅くとも同年六月二八日までに、その謄本の送達を受けたことが明らかであるから、右査定は、遅くとも同日から三〇日を経過した同年七月二九日までには確定したものというべきである。なお、原告が右拒絶査定についてした審判の請求は、その請求書が方式に違反したものとして却下されたから、審判の請求がなかつたことに帰し、右確定の日に何らの影響もない。  2 原告(特許出願人)の“1、(2)”の主張について、 原告は、本件処分がその理由中で、「判決により却下の決定が取消されない限り」と述べている点を捉えて、却下決定の確定が取消訴訟の提起により阻止、保留されていることを自認するものである旨主張するが、すでに述べたとおり、拒絶査定は、その謄本が原告に送達されると同時に公定力ある行政行為として、原告に対して効力を生じており(→公定力とは)、その送達の日から適法な審判の請求がされないで三〇日が経過すると不可変更力が生じて確定するのである(→不可変更力とは)。 また、原告は、本件処分がその理由中で、「却下決定の謄本の送達がされた日から三〇日」と述べているのは、当該決定に対する取消訴訟の出訴期間を指したものにほかならない旨主張するが、その理由は、すでに述べたとおり、拒絶査定の謄本が送達された日から三〇日と述べているうえ、三〇日というのも出訴期間を指したものではなく、特許法第一二一条第一項所定の審判を請求すべき期間を指すことは明らかである。 右のとおりであつて、原告の右各主張は、理由がない。 3 以上の次第であるから、原告が特許出願Aについて受けた拒絶査定は、昭和四六年七月二九日までには確定しているので、その後昭和四八年二月一日にされた特許出願Bは、不適法であり、本件処分には何らの違法もないから、原告の本訴請求は、失当として、棄却されるべきである。 |
| [裁判所の判断] |
|
○裁判所は、特許出願の不受理処分の違法性に関して次のように認定しました。 ”1まず、原告は、特許出願BはAに対する拒絶査定の確定前にされたものであつて、特許法第四四条旧第二項の規定に違反せず、適法なものである旨主張するので、検討する。 特許出願の分割は、特許法第四四条旧第二項によれば、当該出願について査定又は審決が確定した後は、することができない、とされていたが、同項は昭和四五年法律第九一号の特許法を改正する法律によつて削除された。しかし、右改正法附則第一条及び第二条によれば、右改正法は、昭和四六年一月一日から施行されるが、その施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、別段の定めがある場合を除いて、その出願について、査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例によるものとされている。しかして、すでに判示したところからすれば、原告の特許出願Aが右改正法が施行された昭和四六年一月一日当時、現に特許庁に係属していたことは明らかであるから、特許出願Bについては、特許法第四四条旧第二項の規定が適用されるものである。 ところで、特許出願について拒絶すべき旨の査定に対して不服がある者は、査定の謄本の送達があつた日から三〇日以内に審判を請求することができ(特許法第一二一条第一項)、さらに、審決に対して不服がある者は訴を提起することができる(同法第一七八条第一、第二項)から、右査定について法定の期間内に審判の請求がされなかつたとき又は法定の期間内に審判が請求されたが、審決がされ、法定の期間内に訴が提起されなかつたとき若しくは法定の期間内に訴が提起されたが、その審理において拒絶査定不服の審判を請求した者に不利な終局判決がされ、不服申立の方法が尽きたときは、右査定は、取り消される可能性がなくなり、確定したということができる。そして、特許出願についての拒絶査定に対して不服がある者が審判の請求をしたが、その審判請求書について、特許法第一三三条第二項により却下の決定がされたときは、たとえ右却下決定に対して取消訴訟が提起されたとしても、右却下決定を適法として維持する旨の判決が確定すれば、右拒絶査定は、遡つて、その謄本の送達があつた日から三〇日を経過したときに確定することになると解される。右の理は、民事訴訟において、当事者が上訴期間内に一たん上訴したが、上訴期間経過後に上訴却下の確定判決を受ければ、原判決は上訴期間経過とともに確定したことになるのと同様である。 しかして、本件についてみるのに、すでに判示したとおり、原告は、特許出願Aについて、昭和四六年五月六日、拒絶査定を受け、遅くとも同年六月二八日には右査定の謄本の送達を受けたが、右査定に対して不服があり、同日審判の請求をしたところ、昭和四七年三月二二日付で、その審判請求書について、特許法第一三三条第二項により却下の決定がされたので、東京高等裁判所に対し、右却下決定の取消訴訟を提起し、同年一二月八日、原告の請求棄却の判決の言渡を受け、これに対し、最高裁判所に上告し、昭和五〇年七月四日、上告を棄却され、右判決は同日確定したが、原告はこの間、昭和四八年二月一日に特許出願Bをし、昭和四九年六月一五日に本件処分を受けたのである。 以上の事実によれば、本件処分がされた昭和四九年六月一五日当時、特許出願Aについての拒絶査定に対する審判請求書の却下決定の取消訴訟は最高裁判所に係属中であつたので、いまだ右拒絶査定は確定しておらず、したがつてその確定前である昭和四八年二月一日にした特許出願Bは、特許法第四四条旧第二項により許されるべきものであつたといわなければならず、これを不受理とした本件処分は、違法であるといわなければならない。” ②しかしながら、裁判所は下記の理由により本件処分の瑕疵は治癒したとして、特許出願人の主張を退けました。 “しかし、他方、前記事実によれば、その後昭和五〇年七月四日、右審判請求書却下決定の取消訴訟は原告敗訴として、上告棄却により終了したから、特許出願Aについての拒絶査定は、前説明のとおり、遅くとも、その謄本の送達がされた昭和四六年六月二八日から三〇日を経過した同年七月二八日の経過とともに確定したものというべきところ、審判請求書却下決定の取消訴訟が上告審に係属中であつて、特許出願Aについての拒絶査定がいまだ確定していない間にされた本件処分は前説明のように違法ではあるが、その瑕疵は、前説明のように特許出願Aについての拒絶査定が遡つて、遅くとも昭和四六年七月二八日の経過とともに確定したことによつて治癒されたものというべきであり、結局本件処分には違法の瑕疵はないものといわなければならない。 2 次に、原告は、特許出願Bを右のように分割出願として取り扱うことができないとしても、これを通常の特許出願として受理すべきであると主張するが、出願の分割を通常の新たな特許出願として取り扱わなければならないとする法律上の根拠はないから、原告の右主張は、理由がない。 3 以上の次第であるから、原告が本件処分について、その取消理由として主張するところは、いずれも理由がなく、結局本件処分には何らの違法の瑕疵もないことになる。 三 してみれば、原告の本訴請求は、失当として、棄却されるべきであるから、訴訟費用の負担について、民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。“ |
| [コメント] |
|
特許出願の分割には、遡及効が発生しますが、その遡及効がどこまで及ぶのかを考える題材として本件事案を紹介しました。 親出願から子出願を経て孫出願という如く分割出願を繰り返すと、通常は複数の分割出願の遡及効の組み合わせにより特許出願の日は最先の出願まで遡りますが、子出願の段階で遡及効が否定されるような行政処分があると、いわゆる公定力により当該処分は後日取り消されるまで有効なものと扱われます。こうした行政処分は行政庁が自ら取り消すことはできず(不可変更力)、そして不服申立の手段が尽きると行政機関に対して特許出願人はこれを争うことができません(不可争力)。 その結果として、孫出願から子出願までは遡及効が働きますが、親出願までは遡及効が働かない、というのが特許庁の考え方であり、裁判所もその考え方を大筋で支持しました。直ちに特許出願Bを不受理としたのは不適法としましたが、最終的な結果は変わりません。 |
| [特記事項] |
| 戻る |
今岡憲特許事務所 : 〒164-0003 東京都中野区東中野3-1-4 タカトウビル 2F
TEL:03-3369-0190 FAX:03-3369-0191
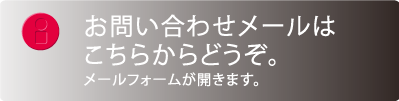
営業時間:平日9:00〜17:20
今岡憲特許事務所TOPページ | はじめに | 特許について | 判例紹介 | 事務所概要 | 減免制度 | リンク | 無料相談
Copyright (c) 2014 今岡特許事務所 All Rights Reserved.

