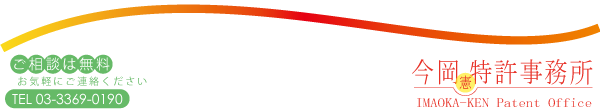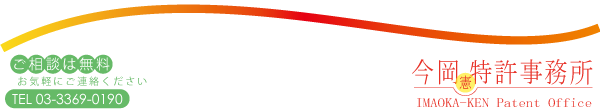| 内容 |
①通常実施権の登録義務の意義
(a)平成23年の法律改正により通常実施権の登録対抗の制度が採用されたため(→通常実施権の当然対抗とは)、通常実施権の登録義務の有無を論ずる必要性は、現在の法律の下ではなくなってしまいました。
そもそも通常実施権は特許原簿に登録する対象ではないからです。
(b)しかしながら、司法の考え方を学ぶ上で良い教材となるため、通常実施権の登録義務の事例を紹介したいと思います。
(c)特許出願が特許査定されると、特許料の納付を条件として特許権の設定登録が行われ、特許出願人は特許権者となります。特許権者は、専用実施権を設定し、或いは通常実施権を許諾することができます。
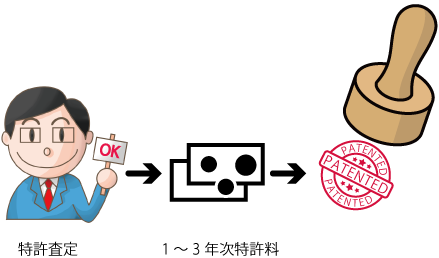
(d)特許権は物権であるため、登録により効力を発生するものと定められており(特許法第66条第1項)、専用実施権も用益物権と解釈されているため(→用益物権とは)、設定の登録をしなければ効力を発生しないものと規定されています(特許法第98条第1項第2号)。
(e)このため、他人に専用実施権を設定することに合意したライセンサーは、その設定登録に協力する義務を負うと解釈されます。具体的には、登録権利者(ライセンシー)とともに登録義務者として設定登録の申請を特許庁に行うのです。
他方、通常実施権は、債権的な権利ですから、通常実施権の許諾に関して契約を締結したとしても、ライセンサーが登録に協力することの合意があったとは認められません。
通常実施権の本質が“ライセンサーがライセンシーに対して差止請求権等を行使しない”ことを定めたものであるとすれば、その合意内容を実現するのに登録は必要ないからです。
これが司法の原則的な考え方ですが、契約に至るまでの具体的事情により、登録への協力を認めないのは不公平であるとして、訴訟に至ることがあります。

②通常実施権の登録義務に関する事例の内容
[事件の表示]昭和47年(オ)第395号(最高裁)
[事件の種類]通常実施権設定登録等請求事件(請求棄却)
[判決の言い渡し日]昭和48年 4月20日
[発明の名称]墜道管押板工法
[経緯]
(a)この事例は、甲が自ら発明し実施していたヒューム管の埋設方法と同一の発明を乙が特許出願したとして、新規性の欠如により異議申立をし、その後に異議申立を取り下げるとともに、乙から甲に対して許諾された独占的通常実施権に関して、
・契約による通常実施権の確認及び当該通常実施権の登録手続をとること。
・予備的請求として、先使用権の確認をすること(→予備的請求とは)。
を求めたものです。
(b)甲によれば、“従来の管埋設工法は、地中に埋設するヒユーム管を後方から推進工具であるジヤツキの圧力で全延長を推進するため、管自体の大小・強度や施行場所の地質等の関係からジヤツキの推進能力に限界があり、埋設する管の延長がジヤツキの推進能力限界距離以上に及ぶときは管の推進が著しく困難であった。そこで原告は埋設するヒユーム管をジヤツキの推進能力限界範囲内で段階的に分割推進する工法(中押工法)を発明し直ちにこれを実施した。実施実績として昭和二八年一一月二〇日からの横浜市内での工事、昭和三〇年二月の東京都内での実施がある。”というものです。
(c)乙は、“墜道管押板工法”の発明について、
昭和31年6月30日に特許出願を行い、
昭和33年6月21日に出願公告となり(→出願公告とは)、
昭和33年8月11日に甲から特許異議申立があり、
昭和34年3月28日に乙と甲との間に実施権許諾契約が行われ、
昭和34年4月9日に甲の異議申し立ての取り下げを受けて特許査定となり、
昭和34年5月14日に特許権の設定登録が行われました(特許第252019号)。
(d)異議申立事件に関して、地方裁判所は次のように事実認定しています。
“原告は本件特許発明が原告が既に右出願前の昭和二八年一一月ごろから横浜市外二ヶ所において実施していた工法と技術思想及び実施形態において全く同一であるところから、その特許出願公告に対し新規性なきものとして、昭和三三年八月一一日特許庁に対し特許異議の申立をなし、該異議手続の進行中、被告は証拠調の直前に至って原告に対し右異議申立の取下を懇請し、その代り右特許発明の実施権を許諾する旨申入れて来たので、原告はこれを受入れ、その結果、昭和三四年三月二八日原・被告間で本件発明を相互に独占的に実施する旨の示談が成立し、被告は原告が異議申立を取下げることを条件に原告のため本件特許発明の実施権を許諾し、原告は前記異議の申立を取下げ、かくて原告は本件特許発明を無条件的に実施するに至った。”
(e)この事件に関して、地方裁判所及び控訴裁判所は、甲の主意的請求を認めますが、最高裁裁判所は前記請求のうち登録の手続を求める部分の判決を棄却しました。以下、関係する判決部分を引用します。
[地方裁判所の判断]
以上のように、本件実施権は、既に登録された特許権者が任意にその特許発明の実施を許諾する通常の場合と異なり、異議手続という特殊の事情のもとで、被告が本件特許出願の拒絶査定という危険を認証するに至って已むを得ずかつ被告の積極的懇請により設定されたものであり、且つ通常の実施権許諾に際してなされうるところの時間的、地域的、内容的等の一切の制限なき全く無条件、かつ全面的の実施の許諾であるから、かかる場合は登録義務につき何ら明示の取極めをしなかったとしても、特に反対の意思表示がない限り黙示に登録義務の約旨がなされたものと云うべきである。

[控訴裁判所の判断]
被控訴人が本件特許権につき通常実施権を有すること右の如くである以上、控訴人に対し右権利の設定登録手続をすることを求める被控訴人の請求も亦理由がある。なぜなら、特許権につき許諾による通常実施権の設定を得たものは、特約による登録禁止その他特別の事情がない限り(本件において右特別の事情は認められない。)特許権者に対し右権利の設定登録を請求しうるものと解すべきであり、この理は許諾による通常実施権が債権的権利であり、登録が対抗要件であることによって左右されるものではないからである。
[最高裁判所の判断]
原判決は、特許権につき許諾による通常実施権の設定を得た者は、特約による登録禁止その他特別の事情がないかぎり特許権者に対し右権利の設定登録を請求しうるものと解すべきであるとして、右通常実施権の設定を得た被上告人の設定登録手続請求を認容した第一審判決を是認している。
しかしながら、特許権者から許諾による通常実施権の設定を受けても、その設定登録をする旨の約定が存しない限り、実施権者は、特許権者に対し、右権利の設定登録手続を請求することはできないものと解するのが相当である。その理由は、次の通りである。
すなわち、特許権の許諾による通常実施権は、専用実施権と異なり実施契約の締結のみによって成立するものであり、その成立に当って設定登録を必要とするものではなく、ただ、設定登録を経た通常実施権は、「その特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる」(特許法九九条一項参照)ものとして、一種の排他的性格を有することとなるにすぎない。そして、通常実施権は、実施契約で定められた範囲内で成立するものであって、許諾者は、通常実施権を設定するに当りこれに内容的、場所的、時間的制約を付することができることはもとより、同時に同内容の通常実施権を複数人に与えることもでき、また、実施契約に特段の定めが存しないかぎり、実施権を設定した後も自ら当該特許発明を実施することができるのである。これを実施権者側からみれば、許諾による通常実施権の設定を受けた者は、実施契約によって定められた範囲内で当該特許発明を実施することができるが、その実施権を専有する訳ではなく、単に特許権者に対し右の実施を容認すべきことを請求する権利を有するにすぎないということができる。許諾による通常実施権がこのような権利である以上、当然には前記のような排他的性格を有するということはできず、また右性格を具有しないとその目的を達しえないものではないから、実施契約に際し通常実施権に右性格を与え、所定の登録をするか否かは、関係当事者間において自由に定めうるところと解するのが相当であり、したがって、実施権者は当然には特許権者に対し通常実施権につき設定登録手続をとるべきことを求めることはできないというべく、これを求めることができるのはその旨の特約がある場合に限られるというべきである。
してみると、これと異る見解のもとにかかる特約の存することを確定しないで上告人の設定登録義務を肯認した原判決には法令解釈の誤りがあり、この違法は原判決の結論に影響を与えることが明らかである。論旨は理由がある。
したがって、原判決中右の部分は破棄を免れず、右部分についてはなお審理の必要があるので、この部分につき本件を原審に差し戻すのが相当である。
[コメント]この事例では、もともと特許出願前にライセンサーが公然実施していた方法と同一であり、新規性がないとして異議申立をしていたものです(→付与前異議申立とは)。ライセンシー側から新規背の有無をとことん争うと特許出願が拒絶になってしまい、双方にとって利がないため、ライセンシーがいわば相手(特許出願人)に譲る形で特許権者からの独占的通常実施権の許諾を受けたものです。
その通常実施権が特許権の譲渡により転得者に対抗できなくなるということを事前に承知していれば、ライセンシーとしては当然納得できる話ではなく、登録義務を契約書に記載させるなどしていたと推測されます。
そうした事情を汲み取って控訴審では、ライセンサーの登録義務を認めましたが、最高裁は控訴審判決を棄却しました。そうした法律が存在することを知らない方が悪いということなのでしょう。このように裁判官の考え方というものは融通が利かないものなので、事前に契約内容に関連する法律をよく調べ、後日紛争になりそうな事柄があれば、当事者同士の暗黙の了解という形で済まさずに、契約書に明記することが肝要と考えられます。
|