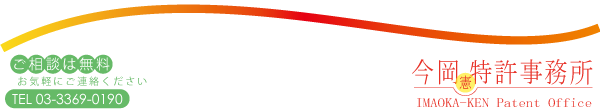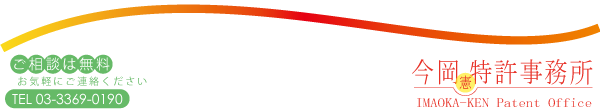| 内容 |
①均等論の積極的要件の立証責任の意義
(a)均等論の積極的要件とは、対象製品等との相違部分が特許発明の本質的部分ではないこと(第1要件)、置換することで作用・効果の同一性を損なわないために置換が可能であること(第2要件)、及び当該置換が容易であること(第3要件)です。均等論の消極的要件と対になる概念です。
消極的要件とは、要素を置換した物・方法が、特許出願前に公知の技術又はこれから当業者が容易に推考可能なものでないこと、及び、置換しようとするものが対象製品等との相違部分が特許発明の本質的部分ではないことです。
(b)立証責任とは、裁判をするにあたって裁判官がある事実の有無について確信を持てないときに、その事実の有無を前提とする法律効果の発生又は不発生により当事者の一方が被る不利益のことをいうとされています(→立証責任とは)。
立証責任について通説的とされる見解は「修正された法律要件分類説」と呼ばれる見解であり、条文の構造等を基礎にしつつも修正を認めるものです。この説によれば、次のように説明されます。
・権利の発生を定める規定の要件事実は、その権利を主張する者が立証責任を負う。
・条文が本文と但し書の組み合わせで構成されており、その但し書が本文の適用を除外する形で規定されている場合には、本文に掲げられた事実の効果を否認する方に但書に掲げられた事実の立証責任がある。
しかしながら、均等論の根拠は、判例であり、判決内容の構造に従って立証責任を定めるべきです。
(c)ボールスプライン判決の要旨は、均等論の適用要件に際して、それまで通説とされていた積極的要件の他に、消極的要件が必要であるというものです。その理由を次のように説明しています。
「けだし、(一) 特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり、相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば、社会一般の発明への意欲を減殺することとなり、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となるのであって、
(二)このような点を考慮すると、特許発明の実質的価値は第三者が特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一なものとして容易に想到することのできる技術に及び、第三者はこれを予期すべきものと解するのが相当であり、
(三)他方、特許発明の特許出願時において公知であった技術及び当業者がこれから右出願時に容易に推考することができた技術については、そもそも何人も特許を受けることができなかったはずのものであるから(特許法二九条参照)、特許発明の技術的範囲に属するものということができず、
(四)また、特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど、特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されないからである。」
この判例の解釈に関して、積極的要件(第1〜第3要件)は、均等を主張する側に、消極的要件(第4、第5要件)に関しては、均等を否定する側に課することが、下級審の傾向となっています。そうした事例を紹介します。

②均等論の積極的要件の立証責任の内容
(a)平成6年(ワ)第17185号(特許権侵害差止等請求事件)は次のように判示します(判年月日平成11年2月26日)。
“特許請求の範囲に記載された方法の構成中に相手方が使用する方法(以下「相手方方法」という。)と異なる部分が存在する場合であっても、
〈1〉右部分が特許発明の本質的部分ではなく、
〈2〉右部分を相手方方法におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏するものであって、
〈3〉右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が、相手方方法の使用の時点において容易に想到することができたものであり、
〈4〉相手方方法が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、
〈5〉相手方方法が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、右相手方方法は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当であり(最高裁第三小法廷平成一〇年二月二四日判決・民集五二巻一号一一三頁)、
右各要件のうち、少なくとも〈1〉ないし〈3〉の要件は均等を主張する者が、主張・立証責任を負うと解すべきである。”
(b)平成27年(ネ)第10014号(知財高裁)
“第1要件ないし第5要件の主張立証責任については、均等が、特許請求の範囲の記載を文言上解釈し得る範囲を超えて、これと実質的に同一なものとして容易に想到することのできるものと認定される範囲内で認められるべきものであることからすれば、かかる範囲内であるために要する事実である第1要件ないし第3要件については、対象製品等が特許発明と均等であると主張する者が主張立証責任を負うと解すべきであり、他方、対象製品等が上記均等の範囲内にあっても、均等の法理の適用が除外されるべき場合である第4要件及び第5要件については、対象製品等について均等の法理の適用を否定する者が主張立証責任を負うと解するのが相当である。”
|