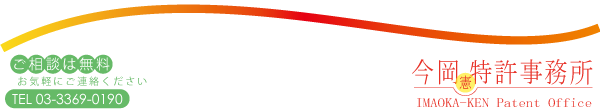
|
●Winans v. Denmead, 56 U.S. 15 How. 330 330
均等論/特許出願/石炭運搬用車両
| [事件の概要] |
| この事件は、Ross
Winanが提起した特許侵害訴訟である。 Ross Winanは、“石炭などを運搬するための車両”と称する発明について特許出願を行い、1847年6月26日に特許権を取得している(特許番号5175号)。 陪審は、地方裁判所の判事の説示を受けた上で、被告を支持する評決を下した。これに対して原告は、writ of errorにより裁判所に持ち込んだ。 本件特許は正しい手続の下で付与され、特許の有効性に関しては争いがない。 そして被告は、原告の特許を侵害したことを否定している。 [発明の内容] (a)本件特許は、鉄製シートでできた大荷重用貨車(burden railroadcar)のボディを製造することに関する。このボディは、その上部が円筒状であるとともに、下部が円錐台状であって、この下部の縁に連設されたフランジに移動式底部が取り付けられている。 (b)本件特許のクレームには、次のように記載されている。 私(特許出願人)がクレームするのは、 石炭運搬するための車両のボディを製造することに関して、 このボディは、円錐台状のものであり、 こうすることにより、貨物の荷重が全ての方向に均等に作用するので変形を生じにくく、かつ全てのパーツが(力の)均等な配分(equal proportion)に対して抵抗するものであり、 前記車体の下部は、運搬車(truck)のフレーム内で(一対の車輪の)車軸の間を延びるように減径されており、 こうすることにより、貨物の容積を減少させることなく、貨物の重心を低くすることができるものである。 さらに私がクレームするのは、 前記車両のボディを、前記運搬車の連続用ピース及び牽引バーを超えることで、運搬車の連結ピース及び牽引ラインの下方へ延びるように構成すること、である。 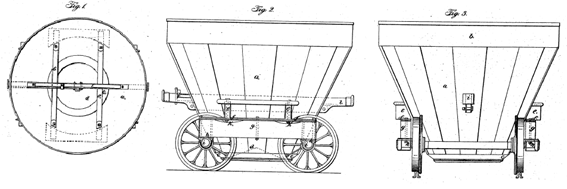 |
| [裁判所の判断] |
|
①裁判所は、本事案について次のように判示しました。 (a)本件特許は単に機械の形状を変更するものではない。その変更によって、別の機構的原理(principle)と自然力と作用モードを導入し、これらを用いて新規かつ有用な結果(new and useful result)をもたらすものである。 (b)特許権者は、八角形(octagonal)又はピラミッド型の車両を製造した人物に対して、特許権侵害訴訟を提起した。 地方裁判所は、本件特許は円錐の形状に対して有利(good for)であるが、直線で囲まれた(rectilinear)形状のボディに対しては有利でない旨を述べた。この判断は誤りである。 両者の構造・作用モード及びそれによって導かれる結果には、変わるところがなく(same)、本件特許の明細書は直線的な形状の車両をカバーしている。陪審に対しては、こうした説示をした上で侵害の成否を事実問題として委ねるべきである。(中略) (c)この事件では、他の特許侵害事件と同様に次の問いかけをすることが必要である。 1.特許権者の発明として記述された構造又は装置は何か? 2.特許権者の構造又は装置にはどのような作用モードが導入され、採用されているか? 3.その作用モードの結果は何か? 4.その結果をもたらす作用モードを当該明細書のクレームがカバーしているか? (d)本件特許の発明の要旨は、前述のクレームに記載した通りである。 (e)本件特許の車両用ボディに導入されかつ採用された作用モードを理解するためには、明細書の記載及び専門家の証言について述べればよい。これらによると、 ・車両用ボディを円形にしたことにより全ての方向に荷重による圧力が均等となり、従って荷重を最大限に支持することができ、 ・移動式底部を取り付けるための僅かの部分を除いて車両用ボディの下部が円錐形に形成されており、 ・当該車両用ボディの下部は、円錐形に形成されることにより、運搬車の車軸の間を通って運搬車の下方へ延びており、こうすることで貨物の重心が低くなり、 ・円周の全ての部分に作用する外向きの圧力が均等となるので、正方形上の車両と比較して、鉄の引張り強度を最大限に利用することができ、 ・そして最後に、この車両の下部の形状は、(移動式の)底部が外されたときに、石炭の敢然な排出を容易とする。 こうした形状の変更により、特許権者は、従来の大荷重用車両で採用されていなかった作用モードを導入した。この作用モードは、前荷重に在る直を、移動式底部を係止させるための僅かな部分を除いて、全ての方向に均等にすることであり、 その作用による効果は、荷重を最大限に支えるとともに鉄の引張り強度を活用し、貨物の重心を低くし、かつ石炭の排出を容易とすることである。 (f)前記作用モードによってもたらされる結果は、特許権者によって正確に記述されており、これについてはトライアルにおいて矛盾のない証拠が示されている。 本件特許の明細書には次のように記載されている。 “石炭や他の重い品物を一まとめにして(in lumps)運搬することは、車両に対して大きなダメージを与えるものと考えられている。従って前記車両は、その側壁部が外向きの圧力に耐えられるように、またその底部が垂直荷重に耐えられるようにそれぞれの強度を設計することが必要である。前記垂直荷重は、当該貨物の単なる質量(mass)としての重さだけでなく、塊(lump)同士が相互に移動することに依存する。経験的に言えば、古い型として構成された車両は、それ自身の重量を超える荷重を運搬できるようには設計されていない。しかしながら、私の発明によれば、より耐久性の大きい車両を提供することができ、それ自身の2倍の重量の石炭を運搬することができる。”  (g)発明の構成、作用モード、及び結果が明らかになったので、次の質問は、その結果を実現する作用モードを明細書のクレームがカバーしているかどうかである。(中略) 証拠によれば、被告は、原告のものと類似した車両を製造しており、相違点は、円形状の代わりに八角形状としたことである。実用的な用途において、八角形の車両は円形の車両と殆ど相違ないことを証明することを意図した証拠が提出されている。 その中の一つとして、James Millhollandの証言を取り上げる。 “車両が円錐形であれ八角形であれ、車両の底部を減径したことの利益は達成されるのであり、 円錐形の形状を達成したことにより車両の底部を補強したという点も、円錐形の代わりに八角形状としても殆ど変わりがない、 例えばスチームボイラーにおいて圧力に抵抗するためのベストの形状は円形であるが、八角形の形状も正方形に比べてベターである、 八角形の車両が円形の車両よりベターであるということはないが、実用的な用途においては、どちらも同じように良好であり(one is as good as together)、 多数の辺を有する八角形は、円形と均等(equivalent to)であり、 八角形の車両は、実用的には(practically)、円形の車両と同じように良好であるから、証人は、両者の間に実質的な相違を見出すことができない。” (h)しかしながら、地方裁判所の判事は次のように判示(rule)した。 “この特許は、(特許出願人が)記述した通りのもの、すなわち、全部又は一部が円錐形である車両について良好なのである。当該車両は、(特許出願人によって開示された)何の発明のモードにも支持されている。すなわち、明細書には、運搬車の上に載置された円錐形のボディが開示されており、図面についても同様である。これらの機構の原理(principle)は、円錐形の車両のみに起因するものであって、直線で囲まれた形状に起因するものではない。被告の車両は直線に囲まれた形状のものと認められるから、特許権の侵害は成立しない。” この判示の要旨は、クレームは明細書に開示された特定の幾何学的形状(geometrical form)に限定されるのであり、被告の車両は、前記特定の形状ではないから、特許権の侵害とはならないということである。そして、この結論は、たとえ被告の製品が特許権者のそれと同じ作用モードでありかつ同じ結果をもたらすものであっても、変わりがないというのである。我々は、この判示が誤りであると考える。 ②裁判所は、以上の判断の根拠として、次の見解を示しました。 (i)我々の法律は、単に形状の変化を保護するものではない。1793年2月21に成立した法律(後の1836年に改正されている)は、新規な発明に対して特許を付与すると宣言している。単に機械の形態を変更するのは設計者の仕事であって、発明者の仕事ではない。原告の発明も単なる変化に留まるものではない。 既存の機械の形態を変更し、それにより別の機構的な原理及び自然力と作用モードとを導入し、以って新規で有用な結果を達成することが特許の主題である。そのために、特許権者は、機械の幾何学的形態(geometric form)を限定したのである。 証拠によれば、本件の場合、原告の発明の作用モードを具現化する他の形態が存在し、この形態によって同じ新規かつ有用な結果がもたらされる。問題なのは、特許権者が彼の発明を具現化する他の形態を除外するように発明を限定したかどうかである。 いうまでもなく、特許権者(特許出願人)が保護範囲を自分の発明よりも狭く限定することは可能であり、他の全ての形態を除外して、一つの形態のみに限定することも自由である。 しかしながら、次に述べる理由から、そうすることが合理的であると認められる場合を除いて、そうした解釈を彼にクレームに対してとるべきではない。  第一に、発明者は、自分の発明の全体をカバーしかつ保護する権利を有しており、そのようにすることを意図したいと考えるのが合理的な推測だからである。 Haworth v. Hardcastle,Web.P.C.484. 第二に、明細書は、憲法及び米国特許法の意図(design)に照らして有用な技術の進歩を促進するとともに発明者に自分自身の使用を保有(retain)させるように関係者の権利を尊重する立場で(liberally)解釈するべきである。 Grant v. Raymond, 6 Pet. 218; (j)特許権者が{特許出願の明細書に}装置を記述するとともに記述した装置をクレームした時には、特許権者が記述した装置の特定の態様(form)そのものだけではなく、自己の発明を具現化する他の全ての態様をクレームしたと考えるのが一般的なルールであり、そして法律はこのように発明をカバーしてきた(※1)。 (※1)…これは中心限定主義を重視する当時の米国法の立場です。 そして記述された装置の原理または作用のモードをコピーしたら、特許侵害となるというのが馴染みのあるルールである。 その結果、オリジナルの形態又は{部材同士の}プロポーションと異なるコピー品が侵害されることもある。 このルールが本件特許に適用されない理由があろうか。 (k)本事件において、本特許発明が単なる{機械の}形態の変更に過ぎず、かつ特許権者が単一の形態しかクレームしていないと認めるに足る十分な証拠は存在しない。 機械類において特許可能な改良は、通常、一つ又は複数のパーツの一つ又は複数の形態を変更させ、それにより従来の機械に存在しなかった機械的原理又はアクションのモードを導入し、しかした新規かつ改良された結果を担保(secure)するものである。 そして多くのケースでは、特許権者の作用のモードがコピーされたら、たとえ明細書に記載されておらず、かつ請求項にクレームされていない用語で表される形態又はプロポーションが実施されたとしても特許侵害となる。 もしそうでなければ特許侵害であるか否かの問題は生じない。 仮に侵害と申し立てられた機械が明細書に記載された形態のコピーであるときには、もちろんそれは特許侵害であると一見してわかる。 争いが生ずるのは、特許品とは外観が類似しない巧妙な相違(ingenious divergence)が存在する場合のみである。 仮に被告が“あなたの特許は形態の変更に過ぎないのであり、あなたは一つの形態を記述しかつクレームしており、そして我々はあなたが記述した形態を採用していない。従って特許侵害は成立しない。”と主張して足りるのであれば、発明者の財産(発明)は無価値なものになってしまう。 これに対する回答はこうであるべきである。 “私の改良は、形態の変化にあるのではなく、新しい多様のモードにおいて新規な原理又は自然力を導入し、一つの形態によって具現化することができ、それにより新規で良い結果を生ずる。これが私の発明を構成するものであり、これがあなたによってコピーされたものである。そのコピーは単にものの形態を変えたに過ぎない。”これが本件特許に適用可能な回答である。 特許明細書が{発明品の}特定の態様のみを含むようなケースは間違いなく存在する。 例えば、Davis v. Palmer事件(2 Brock. 309)はそうしたケースの一つのようである。 この事件の当事者は、全く前述の問答の通りに対応している。 こうした事例で当該特許がただ一つの幾何学的形態のみをカバーしている理由は、特許権者が{特許出願の手続において}一つの形態のみを記述しかつクレームしたからではない。その形態のみが発明を具現化することができるからである。この場合には、その形態がコピーされなければ特許侵害とはならない。  (k)発明の形態(form)と要旨(substance)とが分離不可能であれば、形態のみを見れば十分である。両者が分離可能であれば発明の要旨は異なる形態にコピーできる可能性がある。 この場合には、形態を通じて発明の要旨を探求する(look for)のは判事及び陪審の義務である。 その発明の要旨こそが発明者に特許を受ける資格を与えるものであり、これを保護(secure)するために特許が設定されたのである。 そして発明の要旨が{係争物に}見出されたときには、特許侵害が成立する。 この際に係争物が特許権者によって記述されかつクレームされた形態でないことは、抗弁(defense)にはならない。 (l)特許権者は、{特許出願人として}クレームする際に“当該クレームは、特許された事物に及ぶ。”旨の表現を追加することがあるが、当該事物の形態やプロポーションが変わり得るのである、従ってそうした表現は必要なく、法律は、そうした追加の表現を除いて、クレームを解釈するのである。 仮に公衆が発明の形態やプロボーションを変えることにより、実質的に発明をコピーすることができるのであれば、特許の対象への排他的権利は確保されない。 従って{特許出願の際に}発明を記述し、その原理を示し、発明を完全に具現化できる形態でクレームした特許権者は、法律の塾考によって(in contemplation of law)、彼の発明がコピーされ得る全ての形態をクレームしたと見做すべきである。 (m)他のルールを適用すること、特に本案件のようなケースに適用することは、難しい。 このような特許に対してどのような質問を陪審に投げかけるべきか。 特許権者であれ、或いは他の設計者であれ、正確に円形の車両を設計することはないと推察される。 現実には真円からのズレ(deviation)は常に生ずるのである。侵害であるというには、{製造された}車両はどれだけ円形に近くなくてはならないのか? 僅かな楕円などのズレは許されるのか。許されるとすればその範囲はどの程度か。 これらの質問に対する我々の答えは、 ・実質的に特許権者の作用のモードを具現化することができ ・その結果として、本件発明が達成するのと同種の結果(same kind of result)を得られる 程度に真円に近いことである。 この際に被告の車両が原告の車両と同じ位のアドバンテージを有している必要はなく、また前記結果が正確に{原告のそれと}同じ程度である必要もない。 同じ種類の結果であって、発明の趣旨において特許権者の作用のモードを採用した結果として実現するものであれば良い。 実際のところ(in point of fact)、被告の車両は前述の通り原告の発明をコピーしており、このことが陪審に対して投げかけられるべき問いであった。 原審は、本ケースにおいて証拠に基づいてこの質問に答えるように陪審に求めなかったという点で誤っている。 従って当裁判所は、原判決を取り消す。 |
| [コメント] |
| ①Winans v.
Denmead事件(1853)は、講学上で最初に均等論が適用された事例であると評されます。 クレームに記載された“円錐”状の車両の概念を超えて、八角形状の車両に特許権の効力を及ぼした点は、均等論と共通します。 もっともクレーム上の発明特定事項に対する“均等”(equivalent to)という言葉は、証人の証言中に現れるに過ぎず、裁判官は、こうした言葉を用いていません。 特許権の効力を拡張する根拠となったのは、“機械的な原理”及び“作用的モード”であり、特許権の効力はクレームされた形態(円錐形)だけでなく、それらを共通する別の形態(八角形)にも及ぶとしたのです。 この条件は、我が国のボールスプライン事件で言う均等論の第2要件に共通する考え方であると考えられます(→均等論の第2要件とは)。 ②この判決中の“特許権者(特許出願人)が装置を記述するとともに記述した装置をクレームした時には、特許権者が記述した装置の特定の態様(form)そのものだけではなく、自己の発明を具現化する他の全ての態様をクレームしたと考えるのが一般的なルールである。”旨が記載されていますが、これは1836年に改正された米国特許法が立脚する立場です。 中心限定主義とは、クレームを中心として、明細書の記載を参照して、発明の基本的な考え方(機構的原理や作用のモード)を読み取りながら、保護範囲に一定の広がりを認め、その広がりの中に他人の行為が入れば、特許侵害と認定するものです。 →中心限定主義とは しかしながら米国特許法は1870年に再び改正され、(特許出願人に対して)“発明の範囲を特別に指摘し、明確にクレームする”ことを求める規定振りに変わりました。その結果として、権利範囲をクレームに記載された範囲に限定し、それ以上の考え方を認めないという周辺限定主義に転換することになったと言われます。 →周辺限定主義とは ③中心限定主義は、均等論と馴染みが良く、従って本判決においても“均等論”的な思想が当然のことのように出てきます。 1870年の改正後のバーンズ事件(Burns v.Meyer)では、「裁判所はクレームを拡張しないように配慮しなければならない。クレームとは特許庁が権利を付与した対象であり、クレームこそが特許権者が所有しているものである。権利範囲のクレームの文言の公正な解釈を超えることがならない。」と判示され、均等論に対して抑制的な見解が示されます。 しかしながら、現実問題として、特許出願人による記載の不備を均等論で救済したいという要請はなくなることがなく、以来、米国の司法の判断は、「権利範囲のクレームの文言の公正な解釈を超えることがならない」という立場を前提としつつ、 ・均等論を利用して保護範囲を拡張することは許されるという立場とクレームからの保護範囲の拡張は一切許されないという立場との間、 ・或いは均等論を認めるにしても特許出願の補正をすればもはや均等論は適用しないという立場(→コンプリート・バー(complete bar)とは)と、補正の内容次第ではなお均等論が適用されるという立場(→フレキシブルバー(flexible far)とは)との間 を揺れ動くことになります。 ④この後の均等論の流れを概説すると、 1879年のBurns v. Meyer事件(100 U.S. 671)では、1870年の特許法改正を反映して、司法の傾向はコンプリートバーに大きく傾き、 1942年の Exhibit Supply Co. v. Ace Patents Corp.,事件(315 U.S.126)で均等論に対する抗弁として禁反言という概念が現れ、 1950年のGRAVER TANK & MFG. CO., Inc., v. LINDE AIR PRODUCTS CO事件 (.339 U.S. 605)において、改正米国特許法に対応した“近代的な”均等論が登場し、 1983年のHughes Aircraft Co. v. United States事件(717 F.2d 1351)で、フレキシブルバーよりの判決(特許出願に補正が行われたことを理由に画一的に均等論を適用しないとした原判決は不当とするもの)が出され、 1984年のKINZENBAW v. DEERE & CO. 事件(741 F.2d 383) では、一転して“コンプリートバー”(特許出願の補正を行ったときに均等論を一切認めない立場)が提唱され、 2002年には、前述のフレキシブルバー及びフレキシブルバーの争いに終止符を打ついわゆるフェスト判決が出されます。 |
| [特記事項] |
| 戻る |
今岡憲特許事務所 : 〒164-0003 東京都中野区東中野3-1-4 タカトウビル 2F
TEL:03-3369-0190 FAX:03-3369-0191
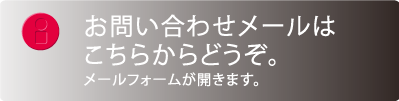
営業時間:平日9:00~17:20
今岡憲特許事務所TOPページ | はじめに | 特許について | 判例紹介 | 事務所概要 | 減免制度 | リンク | 無料相談
Copyright (c) 2014 今岡特許事務所 All Rights Reserved.

